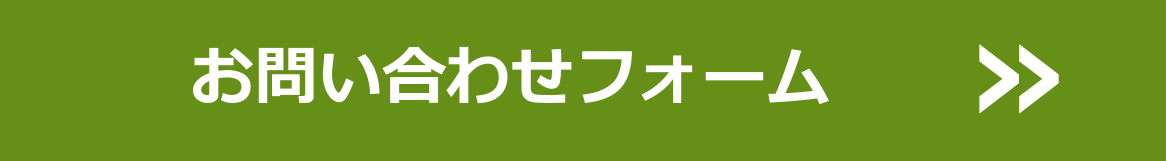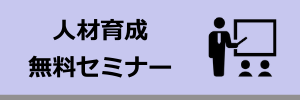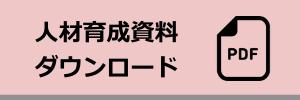ブログ:コンサルタントの視点
部下指導・育成のために「育成(OJT)力」を高めよう(前半)
2015.02.23
マネージャーの部下育成力を強化したいというご相談をよくいただき

大学卒業後、外資系人材サービス会社にて金融機関を中心とする法人向け採用戦略コンサルティング、およびキャリアカウンセラーとして1000名以上のキャリア支援に携わった後、グロービスに入社。
グロービスではスクール部門を経て、現在は法人部門・製造業チームのマネージャーとして、化学・金属・機械・製薬・食品など幅広い企業に対する、人材開発・組織開発のコンサルティングに従事。
人材マネジメント・組織行動研究グループにも所属し、研究やコンテンツ開発、講師を務める。
グロービス経営大学院経営学修士(MBA)修了。
目次
マネージャーの指導力はなぜ落ちているのか?
「うちの会社のマネージャー(管理職)は人材育成が苦手だ」「指導・育成ができるマネージャーを増やしたい」――これらの言葉は、多くの企業で聞かれる話しではあるが、「指導・育成ができるマネージャーが増えた」という話はあまり聞こえてこないのが実情だ。
このような場合、「マネージャー自身がプレ-ヤーであるため指導・育成の経験がないこと」が原因であろうと考え、「指導・育成の型の理解」と「指導・育成行動のシミュレーション(疑似的な経験)」を通じて育成力を高めようと試みる。しかし、残念ながらそれだけでは育成行動が定着せず、研修などを終えても実業では元の行動に戻ってしまうというケースも少なからず耳にする。
本気で指導力と育成力を高めるには別のポイントに力点を置いた取り組みが必要というわけだ。
筆者はここ数年、製造業を中心とするさまざまなお客さまと「指導力・育成力の強化」に二人三脚で取り組んできた。モチベーションマネジメントを含めた幅広い意味での育成力の強化に取り組むことは多くの日本企業の命題であると考える。本稿が「指導力・育成力が高まらない原因」とそこから導かれる「解決の方向性」についてヒントになれば幸いである。
なぜマネージャーは育成ができないのか? 自社を振り返る4つのポイント
指導力・育成力不足の要因を「指導・育成の経験がないこと」と置き、それを補完する施策を打つが効果が持続しないという現象は冒頭に述べたとおりである。では、要因は別にあるのだろうか。
筆者は以下の4つがポイントであると考える。
①マネージャー自身の「上司から育てられた経験」
②効率化や生産性向上を背景とするトップダウンの文化
③育成の時間が取れない悪循環
④人材マネジメントシステムの形骸化
まず、本稿では原因仮説としての2つのポイントを見てみよう。
①マネージャー自身の「上司から育てられた経験」
弊社の研究グル―プの調査によれば「なぜ人材育成に目を向けられないのか」という質問に対して驚くほど多くのマネージャーが「自分が育てられた経験がない」と答えた。
同時に「上司からされていないので経験(実体験)がなく必要性を感じていない」という回答も多くみられたのである。
単に「経験がない」ならば「経験を付与」すれば身に付くが、身に付かないのはその「必要性の理解・納得」にまで切り込んだ対策を描く必要があるのだろう。
また、裏を返すと育成をしてもらったという経験が、「育成をしよう」という意欲を引き出すのである。そしてそれは好循環するのかもしれない。
②効率化や生産性向上を背景とするトップダウンの文化
前述の調査で、育成しなかった上司の多くが「トップダウン(指示的)」のコミュニケーションスタイルであったことも共通項としてわかってきた。
よく言われることだが「トップダウン(指示的)」だと部下の考える力や主体性を奪ってしまう。新たな場を与え、問いかけを通じて考えさせ、主体的に行動できる人材をつくることを育成というならば、「トップダウン(指示的)」であることは育成行動とは逆の行動となる。
しかしこれらの企業の戦略を紐解くと「トップダウン(指示的)であることが当時の戦略実現の肝」とされてきたことがうかがえる。具体的には、たとえばこのような状況である。
2002年後半から2007年までは中国を中心とする海外需要に支えられ、日系企業の経済状況が大きく好転した。
一方、組織はどうだったかというとその前年までに金融不安やITバブルの崩壊があり、組織のリソース(モノ・ヒト)は最小化されていた。そこに急転直下の景気回復である。
設備の増強や人の採用を行うものの、そのチャンスを逃さないためには、いかにスピーディーに拡大する需要に対応できるかが命題であった。当然上位層の意思決定もスピーディーかつトップダウンにならざるを得ない。
結果2007年までに多くの国内企業は業績を伸ばし、成功体験を持ったのだが、その代償としてトップダウンのコミュニケーションスタイルが身に付き、①で述べたように「指示ばかりを受け育成をされた経験がない」今のマネージャー層を生んでしまったのである。
話はそれるが、同じ環境下にあっても「効率化」や「生産性向上」だけでなく「新たな事業や製品を生み出すこと」に戦略の軸足を置いていた企業では、さまざまな階層で自ら考え動く機会が豊富にあった。上司もこれまでの戦い方や考え方では新たなものを生み出せないので、おのずと部下への問いかけを主体とし現場の情報を引き出し一緒に考えるなど、関わり合いのスタイルが異なっていたのである。結果、育成の肝となる「自ら考え主体性を持つ」という実体験につながっている。
この「自ら考え主体性を持つ」ことの重要性を理解している企業とそうでない企業ではいざ「育成」に取り組む際のイメージの持ち方が大きく異なる。
話を戻すと、この効率化の推進や生産性の向上に力点を置いた戦略が長く続いている場合、上位層の経験が優位に立ち、トップダウンのコミュニケーションスタイルになりがちである。結果、育成をされた経験がない層が増えるのである。
自社の事業を俯瞰して、効率化/生産性向上にばかり偏りすぎていないか? 結果トップダウンのコミュニケーションになりすぎていないか? を問いかけたい。
ここまで、育成力不足の背景となる要因仮説をみてきた。次回は解決の方向性としての2つのポイントについて考えていきたい。
※「今こそ組織をあげて「育成(OJT)力」を高めよう―後半」に続きます。
人材育成セミナー・資料ダウンロードはこちら
※文中の所属・役職名は原稿作成当時のものです。