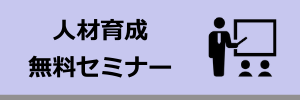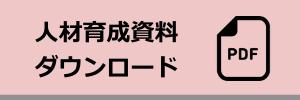グロービス流「リーンスタートアップ」~企業内研修を通じたイノベーション創出~
米国発の新規事業創出ワークショップ「リーンスタートアップ」 とは
2015.10.27
イノベーション、特に「新規事業創出」は企業の永遠の最重要課題の1つであり、しばしば人材育成の目標ともなります。今、多くの日本企業に求められる社内イノベーション人材育成のソリューション「リーン研修」について、グロービス経営大学院教員の川上慎市郎が3回にわたってご紹介します。

早稲田大学政治経済学部卒業
学位:経済学士
その他プログラム:IESEビジネススクール(スペイン)IFDP修了
日経BP「日経ビジネス」誌記者として流通・自動車・家電・IT業界等の企業取材、(社)日本経済研究センター研究員等を経て、複数のネット媒体のマーケティングやシステム開発等に従事。その後グロービスに入社し、グロービス経営大学院のマーケティング領域リード・ファカルティを務める。同領域のプログラムやケースの開発、経営大学院や企業研修での講師を務める傍ら、ケースメソッドによる経営教育の方法論の研究に従事する。共著書に『プラットフォームブランディング』(ソフトバンククリエイティブ)、『MBAマーケティング 改訂3版』(ダイヤモンド社)、『メディア・イノベーションの衝撃』(日本評論社)、『WEB2.0キーワードブック』(翔泳社)など。電子コンテンツサイト「Cakes(ケイクス)」にて、コラムを連載中。
目次
はじめに
国内の既存市場における事業が成熟・停滞するなか、グローバル市場への展開も見据えた新規事業創出力の向上は、企業にとって重要なテーマの1つだ。
成功確率を飛躍的に高める米国発の新規事業創出ワークショップの方法論として、2012年頃からベンチャー業界で話題になってきた「リーンスタートアップ」。昨年頃から大企業においても社内教育研修のプログラムとして取り込む動きも増えつつある。
これから3回の連載で、この発想を企業研修に組み込む「リーン事業開発」研修の方法論を、そのメリットや懸念点、およびそれを克服して研修を成功に導くためのポイントを解説する。
1回目の今回は、なぜリーンスタートアップが注目されているのかを、日本企業におけるイノベーションの課題と絡めて見てみよう。
リーンスタートアップとは?
リーンスタートアップという発想はシリコンバレーで生まれた新規事業創出ワークショップの方法論だ。「多産多死」はベンチャーの習わしだが、壮大な机上の空論を元にプロダクト開発をスタートさせて失敗すると、投資側も経営側も痛手が大きい。
そこで「プロダクトより先に顧客を探してくる」「小さなコンセプトレベルのプロダクトでまず顧客の反応を探る」といった取り組みが生み出された。つまりリーンスタートアップとは、最低限のコストと最短のサイクルで仮説と検証を行い、顧客の反応を探る手法だ
ではなぜ、ベンチャー以外の日本企業において今リーンスタートアップが注目されているのか?それは日本企業のイノベーション創出における課題を解決してくれるとして期待されているためだ。
日本企業のイノベーション発想の落とし穴
日本企業におけるイノベーションの問題点は2つある。1つは心理ハードルの高さだ。しかし、逆説的にみえるかもしれないが、日本企業においてはイノベーションとは日々起こっているものだ。
「カイゼン活動」などと呼ばれる、いわゆる漸進的な(インクリメンタル)イノベーションはその典型例である。多くの日本企業では当たり前に行っていることなので、それがイノベーションと言われてもピンとこない。
生産ラインが固定的であることが多い海外では、プロセスにおけるちょっとした創意工夫が大きなインパクトを持ち得るのとは対照的だ。だが、現場におけるカイゼン活動に慣れた日本企業では、それは「大したこと(イノベーション)ではない」となってしまう。イノベ―ションと銘打つからには、とてつもないもの、飛び石的な(ラディカル)イノベーションでなければならないという、心理ハードルが高くなっているのだ。
では日本企業にはインクリメンタルなイノベーションだけで十分で、ラディカルなイノベーションは不要なのだろうか。そうではない。前者は既存製品のコスト低減や性能向上には確かに有効かもしれない。
しかし残念ながらインターネットが登場して以来、世界の競争はもはやコストダウンや性能アップよりも、まったく新しい価値創出の競争に代わっている。カイゼンだけでは、現在の世界規模の競争に勝利することはできない。
新しい価値をどう創出するかという命題に対して、日本企業では新技術を想起しがちである。しかし、数年研究に打ち込めば技術的なブレークスルーが生み出せていた高度成長期と違い、今は多くの分野で画期的な新技術を実現しようとすると、基礎研究からはじまりとてつもない時間がかかるものだ。
例えば、1964年の東京オリンピックで使用されたセイコー製のクオーツ時計は、テーブルの上に載る重量3キログラムの機器だったが、その5年後の69年には驚異的な小型化が成し遂げられ、わずか数十グラムの腕時計として発売された。
しかし現在はどうだろうか。たとえば、回路と回路の間隔が14ナノメートル幅まで高密度化している半導体チップの性能を、これまで同様に回路幅を狭め続けることで向上させるのはもう無理とも言われている。
技術の複雑化・高度化が極まりつつある昨今、性能を向上させるには、従来とはまったく異なる技術的アプローチが必要だし、そのハードルは日々上がっているのである。
組み合わせのイノベーションを苦手とする日本企業
単線的な技術のさらなる高度化というイノベーションの難易度が高まる一方で、この20年で劇的に進行したのがインターネットと情報通信技術(ICT)の発達である。それにより、異なる分野の既存技術の要素を組み合わせ、ICTを使って融合することによって生み出される、まったく新しい顧客体験がむしろ価値を持つようになってきた。
ありがちな例だが、世界で最もたくさん売れているiPhoneの部品は、その大半が日本企業により作られている。しかし、iPhoneの価値とは個々の部品の性能ではなく、その組み合わせによって生じる革新的な使用体験である。
この、「組み合わせによるイノベーション」こそが、日本企業がイノベーションにおいて抱える問題点の2つめである。
乱暴な一般化ではあるが、日本人は既にある組み合わせを、よりスピーディーに、より低コストで再生産することばかり考えようとする傾向がある。これは筆者がさまざまな企業事例を研究するなかで感じてきた感想だが、皆さんの周辺はいかがだろうか。
多くの企業で、異質な要素同士を自由に組み合わせるという素養が不足している。厳密には研究所の中には多少あるかもしれないが、研究所のアイデアは事業部門の高いハードルを乗り越えることができず、斬新な組み合わせのイノベーションを世の中に出していくことは非常に難しい、というのが多くの企業の現実であると見ている。
この指摘は決して新しいものではない。「イノベーション」という言葉を最初に使った経済学者、J.A.シュンペーターも、初期の頃には「新結合(New-Combination)」という言葉を使っていた。今また、インクリメンタルなイノベーションから、ラディカルに要素の組み合わせを変えるイノベーションの存在感が増す時代の流れのなかで、いよいよ日本企業の乗り越えるべき壁は高くなっていることを改めて強調したい。
斬新なイノベーションを生む「外」への目線
では組み合わせのラディカル・イノベーションを実現するには何が必要だろうか。キーワードは「外」への目線である。自社の既存の技術要素、提供価値だけを見ていては、どうしてもそのカイゼンの発想を捨てられず、新しい組み合わせも思いつけない。
極端な言い方をすれば、社外の優れた人材に事業構想を丸投げする位の思い切った発想の転換を経営陣ができると良い。しかしそれは現実的には難しい。第一歩としては自社の人材を「外」の発想に触れさせ、それを取り入れる能力を強化することが大事だ。
「外」との出会いを通じて新たな発想を具現化するためのプロセスがリーンスタートアップであり、日本企業が自社のエースにリーンスタートアップを学ばせたいと考える所以はここにある。ここでいう「外」はすなわち顧客をさす。
筆者が人事部様との議論のなかでよくうかがう期待値としては、「座学ではなく実際の顧客に接しながら、実際の事業を創るプロセスを踏ませたい」という声がある。
従来の多くの社内新規事業では、顧客ニーズは調査会社の出しているアンケートや統計などの二次データに基づいて語られる。しかし、二次データから読み取れる顧客ニーズは、あくまでそのデータを作成した他人の解釈のフィルターを通したものに過ぎない。
もちろん、それでも事業計画を作成する練習にはなるだろうが、それはあくまで「素振り」である。そして素振りの重要性を知り抜いてもなお、「実際の顧客に接すること」を重要視する人事部がいらっしゃるのもまた事実だ。
リーンスタートアップでは、素振り練習よりも実際に購買意向を持つ顧客を見つけ、整然とした事業計画より前にその顧客がカネを出しても良いと評価する「モノ」を作らせる。統計データよりも生の顧客の声を聞け、というのがその考え方だ。
顧客は往々にして、既存の製品や事業の前提にとらわれた人には思いもつかないような、切実な不満や不安を抱えている。それらをうまく酌み取り、解決手段を提案することによって、気がつくと「新たな発想のイノベーション」が生まれることになる。
ここまで、なぜ日本企業でリーンスタートアップが注目されるのかの背景を見てきた。次回は実際にリーンスタートアップを埋め込んだプログラムを学びのステップに沿って見ていこう。
人材育成セミナー・資料ダウンロードはこちら
※文中の所属・役職名は原稿作成当時のものです。