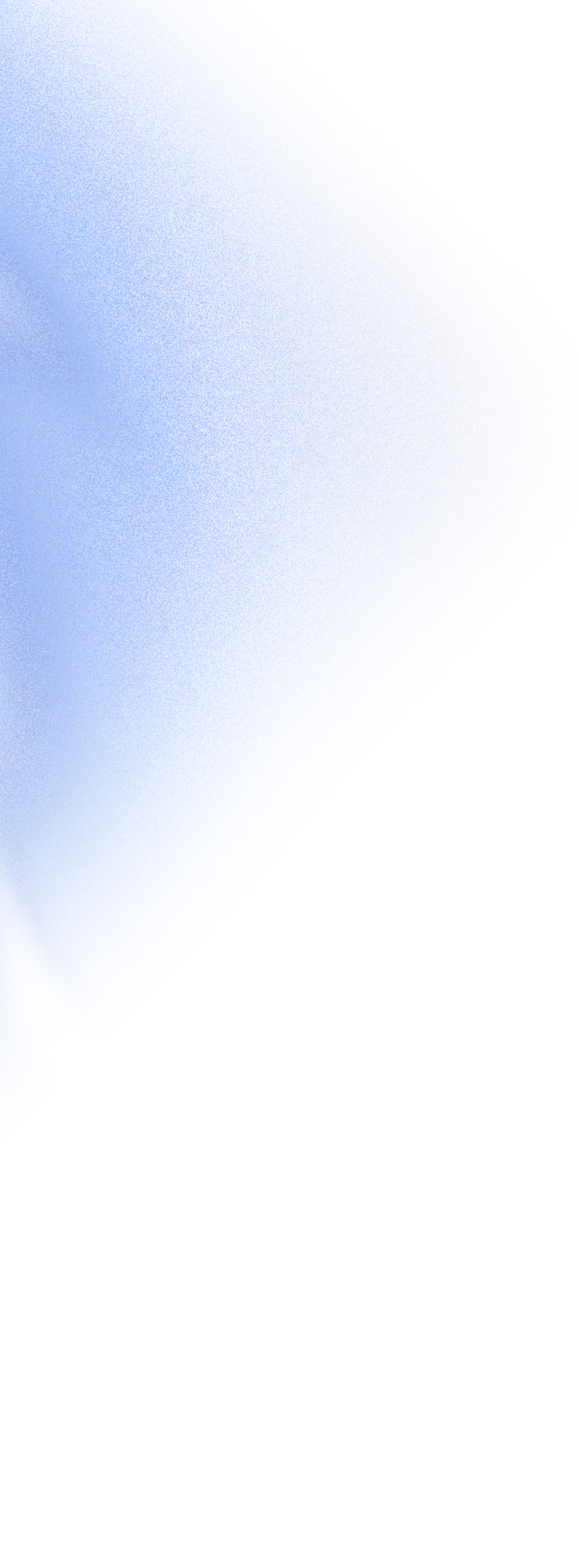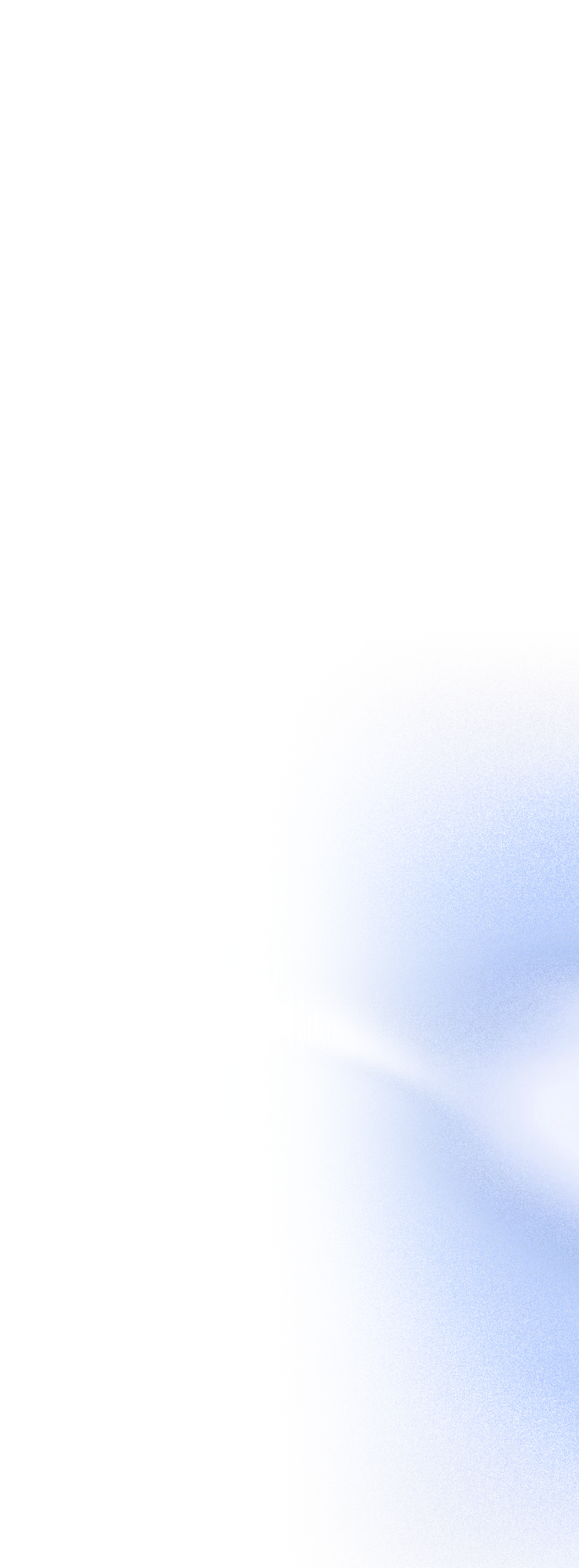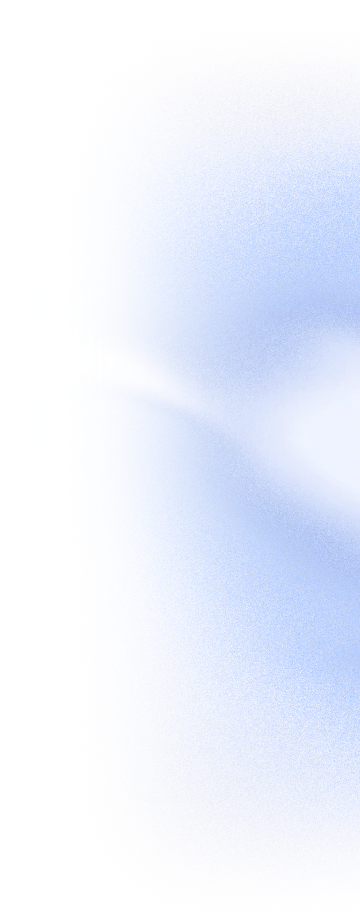自律型人材とは ~育成失敗を回避するポイントと成功の秘訣~
日経225企業
取引実績
集合研修
有益度
評価
導入
企業数
受講
者数
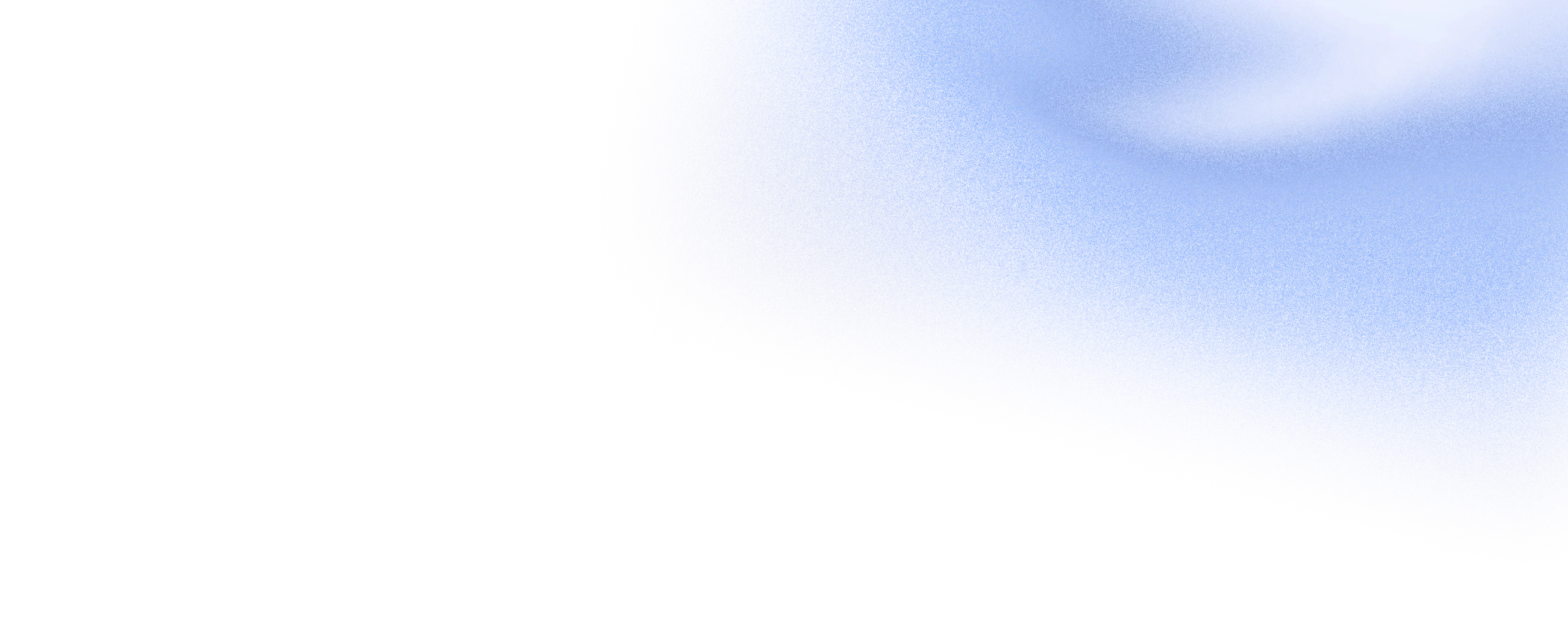
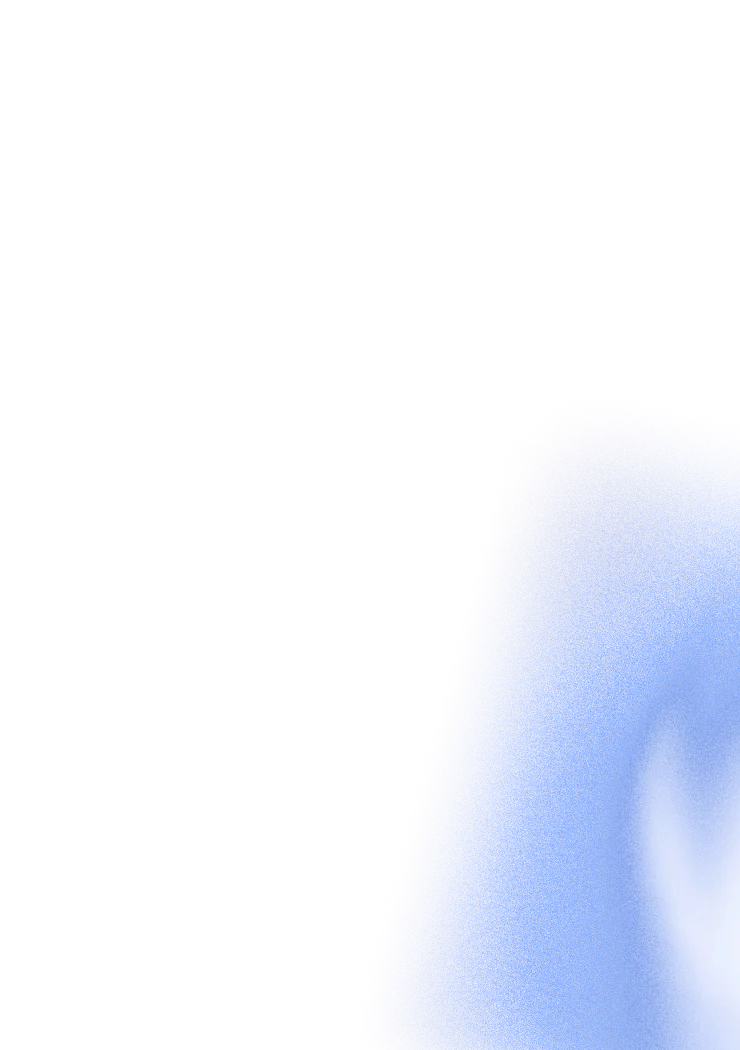
自律型人材とは、仕事の意義意味を理解して主体的に行動し、成果を生み出せる人材のことです。
年間3,400社以上の企業研修を実施しているグロービスでは、業界や業態を問わず「自律型人材を育成したい」というご相談とお悩みの声を頂戴します。

本コラムに興味を持たれた皆様も、同じような悩みをお持ちではありませんか?本コラムは、このようなお悩みを解決するために、執筆が決まりました。お心当たりのある方は、ぜひ最後までお読みください。
なぜ人材育成担当者はこのような悩みを抱えがちなのでしょうか。グロービスでは、「自律型人材を育成するための真の目的を抽出できていないから」と考えています。
そのため自律型人材育成の相談の際には、皆様の悩みにさらに深く踏み込み、具体的な育成課題を明確にします。議論を通じて、以下のような課題に焦点を当てていきます。

このように悩みにもう一歩踏み込んで、具体的な育成課題を明確にしていきます。すると貴社が自律型人材を育成するための、真の目的が見えてきます。真の目的とは、たとえば以下のような内容です。

真の目的を明確にせずに、表面上の悩みだけで育成施策を検討すると、本当に必要な自律型人材を育成するのは難しいでしょう。
本コラムでは、皆様が明日から一歩を踏み出せるよう、育成課題を深掘りし、具体的な育成施策を検討するためのエッセンスをわかりやすくお伝えしています。育成のポイントや失敗回避のコツさえ押さえていただければ、確実に成果を上げることができます。
本コラムの特徴は、自律型人材育成の具体事例を沢山用意していることです。グロービスは3,400社以上の人材育成に関する豊富な経験とノウハウを活かし、実際に、多くの社員の意識や行動変容を起こしています。詳しくは9章で紹介しますが、自律を促す育成施策によって、受講者の自律性向上はもちろん、組織全体の自律的な風土や文化の醸成に貢献した成功事例があります。
―成功事例―
- 【国分グループ様】優秀な若手が飛躍できる研修によって、主体的に働くモチベーションをつくれた事例
- 【SAP様】営業担当者が経営知識を得たことによって、提案力の向上と自律的学習につながった事例
- 【コロワイド様】管理職層が学び始めたことによって、自律的に学ぶ組織の風土醸成につながった事例
- 【雪印メグミルク様】管理職層がリーダーシップ研修によって、部下の自律を促すマネジメントができるようになった事例
また本コラムには、皆様が自律型人材の育成を成功させられるように、具体的な施策・解説を多く盛り込んでいます。5章では、成功する自律型人材育成には欠かせない3つの注意点についてご説明します。

6章では、具体的な自律型人材の育成方法をご紹介します。自律型人材の3つの特徴を育成するために、具体的にどのような働きかけをすればよいのかを説明します。

ぜひ参考にしてください。本コラムを読んで、本当の自律型人材の育成成功を目指しましょう。

自律型人材とは
1-1 自律型人材という言葉の定義はない
実は、学術的な「自律型人材」という言葉の確たる定義はありません。そのためグロービスでは、具体的な「自律型人材」の定義は、各組織によって定めることが最適だと考えています。
1-2自律型人材の特徴は3つある
そうは言ってもなかなか議論しづらいというお客様の声もあり、グロービスなりの自律型人材を特徴づける3つの特徴をお客様にご紹介しています。

1-2-1仕事の意義意味を理解し、自分の働く動機と重ねる力がある
仕事の意義意味と自分の働くモチベーションとなる動機が重ねられると、「この課題は自分がやるべき」と当事者意識が生まれてきます。自分の価値観や仕事への動機がよくわからないまま、組織から期待されたことを努力し続ける期間が長くなると、「何のために頑張っているのかわからなくなる」というメンタル不調が起きる場合があります。長期的に自律性を発揮して働き続けるには、仕事の意義意味と自分の価値観の重なりを見つけることが大切です。
1-2-2最低限の業務スキルをもって主体的に行動できる
主体的な行動をしてくださいと言われても、新人や異動してきたばかりの社員であれば、そもそも基本となる業務知識・スキルが足りないので、目の前の仕事をこなすことで手一杯です。例えば人事担当者のあなたが突然「スペインで看護師をやってください」と言われても、スペイン語がわからない、看護師として働いた経験もなければ、主体的には働くのは難しいと思います。最低限の業務知識やスキルを獲得することが主体的な行動の土台づくりに必要です。
1-2-3PDCAを回して、成果を生み出せる
主体的に問題解決ができるようになるには、課題の発見~実行~振り返り~次のアクションというPDCAサイクルを回していくことが必要です。この行動特性をもてていると、仕事に対して「なぜ?」という問いを立てながら働くので、他人に依存せず、自分の仮説をもとに業務を進めていくことができます。組織の成果指標をすり合わせながら、自分の責任で考え、工夫できるように仕事を任せていくと良いでしょう。
1-3自律的な素質があっても自律型人材とは呼ばない
注意することは、主体的に行動している・学んでいる“だけ”では、自律型人材とは呼びません。組織にとって自律型人材とは、「成果を生み出せる」という生産的な行動までを含んでいるからです。
例えば、こんな方はいないでしょうか。仕事はあまり熱心ではなく、指示がないと動かないのに、飲み会などは喜んで幹事になって企画するような人です。飲み会の幹事も大切な役割の一つではありますが、そこばかりに集中している方は、個人としては自律的な資質をもっていますが、組織にとっては自律型人材とは言いません。人として「自律的な資質を持っていること」と「実際に自律的に働いていること」とは、必ずしもイコールではないのです。つまり組織における自律型人材とは個人の自律的な資質・行動という視点だけではなく、それが働く場で発揮されているかが重要になります。

自律型人材育成がなぜ求められているのか
自律型人材が求められるようになった背景には、次の3つの大きな動きが関係しています。ビジネス環境や働き方改革といった複数の要因が同時発生しており、社員一人ひとりが自律的に行動することが企業の持続的成長には欠かせない条件になっています。

2-1 激しい市場変化には、社員一人ひとりの対応力が必要だから
VUCAの時代には、変化を前提とした試行錯誤が必要となります。既存の方法で解決できる課題であれば、組織のトップの判断で物事が解決できました。しかし、現在は前例のない課題が増えています。
- “VUCA”という言葉に代表されるように、過去の経験が活きにくい前例のない仕事をすることが当たり前になりつつある
- テクノロジーの発展に伴ってビジネススピードが早まり、業務の細部まで管理職に判断を仰いでいる余裕がない
- 業界を超えた企業合併や提携も盛んになり、様々なステークホルダーと仕事をする必要がある
したがって、新たな変化が次々に起こりうる時代には、組織の上層部だけではなく社員一人ひとりが市場の変化や課題に迅速に対応し、行動する必要があります。これが自律型人材が求められている一番の理由です。
2-2 働き方改革による労働時間の減少で、効率的な業務遂行が必要だから
自律型人材は、管理職や管理者の監督を必要とせず、自分で課題を解決し、プロジェクトを進める能力を持っています。働き方改革を実現するには、指示待ちや前例踏襲ではなく、社員一人ひとりが自ら考え行動する姿勢が必要となります。自律型人材が増えるほど、組織は時間とリソースを節約し、効率的に業務を遂行できます。
2-3 個の自律を前提とした、働き方の多様性、雇用システムへと変化しているから
働き手の価値観が多様になっていることも理由の一つです。終身雇用や年功序列制度の限界、人生100年時代による就労観の変化で「会社任せじゃなく、どうやったらキャリアを自律的にできるのか?」という問いが個人に生まれました。働き方の選択肢が増えているため、会社が用意するポストやキャリアイメージに頼るのではなく、自らありたい姿を描き、実現する自律型人材が求められています。
自律型人材を育成する企業のメリットとデメリット
では、自律型人材を育成すると企業にはどのようなメリット、デメリットがあるのでしょうか。
3-1 自律型人材を育成する企業のメリット
主に、「組織力向上」に対しての4つのメリットがあります。

キャリア自律を促進すると「離職が増えるのではないか」と心配の方は、こちらのコラムもおすすめです。
関連コラム 組織を強くする「キャリア自律」とは ~企業が支援する意義と、促進・定着に導く方法~
3-2 自律型人材を育成する企業のデメリット
デメリットは、時間がかかることです。これまでの日本の企業はしばしば「同質性」や「上意下達の風土」といった特徴を持つメンバーシップ型の組織文化を築いてきました。このような企業にとって、自律型人材を育てるためには、育成プロセスを根本的に変える必要があり、それには多大な労力が必要です。後で詳しく説明しますが、自律型人材を育てるには、人事制度などの組織のシステムと、管理職やチームとの関係性が相互に影響し合う必要があるため、変革プロセスは複合的で時間を要するものとなります。
自律型人材に求められる定義を決めるコツ
それでは自社における自律型人材は、どのように定義すればよいのでしょうか。「自律型人材」という言葉が抽象的であるがゆえに、どう定義に落とし込めば良いものかとお悩みの人事担当者の方も多いと思います。順を追ってご説明していきます。
4-1 行動・能力・資質の順に整理する
まずは氷山モデルを参考にして自社が求める「自律型人材」の「行動・能力・資質」をそれぞれ整理します。ポイントは、「行動⇒能力⇒資質」と順番に考えていくことです。
- STEP1「行動」:まず、どんな行動を発揮してほしいか?
- STEP2「能力」:次に、その行動を発揮するにはどんな能力が備わっている必要があるか?
- STEP3「資質」:最後に、スキル・知識といった能力以外の資質・マインドではどんなことが必要か?
下図では、自律型人材の定義としてお客様からよく言われる内容を例として示しました。参考にしながら、自社における自律型人材の定義を考えてみましょう。

4-2 迷ったら経営戦略かロールモデルから考える
そもそも自社が求めている「自律型人材」をどのように考えたらいいかわからない、もしくは整理しているうちに迷ってしまったという方には、2つのアプローチ方法をお伝えします。ご自身の中で自律型人材のイメージを具体的に固めてください。

①経営戦略から落とし込む方法
経営戦略から逆算的に人物像を考える手法です。経営戦略を理解し、今後必要になる自律型人材にはどのような行動発揮が期待されるかを定義に落とし込んでいきます。
たとえば、新規事業創出を大テーマに掲げている会社の求められる(あるべき)自律型人材を考えてみましょう。いくら積極的に考えて行動していても、既存業務の改善活動だけでは物足りなさそうです。既存の延長線上にない考えを積極的に管理職や経営層に提案していく、そんな人材が評価されるのではないでしょうか。
※注意点:経営戦略と現状に大きなかい離がある場合、求められる(あるべき)人材像の基準が高くなりすぎてしまい、施策が非現実的な計画になる恐れがあります。
②すでにいる自律型人材(ロールモデル)を分析して抽出する方法
すでに組織内にいる人材をロールモデルとして活用する手法です。現組織の中で自律型人材と言えそうな人物がいる場合、その人の行動を観察し、保有しているスキル・マインドを分析することで自律型人材像を設定します。実際の従業員を目標とするためゴールがイメージしやすく、自社・自部門で実際に必要な行動やマインドを抽出できるという点がメリットです。
※注意点:分析している人材が戦略実現のために必要な自律型人材なのか?実は間違っているという恐れがあります。
おすすめは、併用して使うことです。なぜなら経営戦略から考えるだけでは、現実とのギャップが大きすぎて施策が非現実的になってしまう可能性があり、ロールモデルから考えるだけでは経営戦略とはズレてしまう恐れがあるからです。
4-3 必ず関係者内で認識をそろえる
関係者内での認識合わせの時間を忘れずに持ちましょう。管理職・同僚・経営層など立場が異なれば、自律型人材に対するイメージも異なる恐れがあります。実際、弊社のお客様でも、抽象的な表現を具体化していく中で「そういう意味じゃなかった」と認識違いがありました。自社にとっての自律型人材の定義を関係者内でしっかりとすり合わせをし、定義した内容が自社の理念・事業戦略に沿う内容になっているかを必ずチェックしてから、具体的な育成方法の検討へ入っていきましょう。
自律型人材を育成する前に知っておきたい、3つの注意点
具体的な育成施策に入る前に、自律型人材の育成を成功させるための3つの注意点をお伝えします。

5-1 育成課題を議論する前に、施策を検討することはやめましょう
第3章でもお伝えした通り、メンバーシップ型に見られやすい組織文化を築いてきた企業の場合、育成設計から見直す必要もあります。自律型人材が育ちにくい現状に対して、どこに組織課題があるのか、どこが人材育成課題となっているのかをしっかりと議論して本質的な解決策を導きましょう。どんなサービスを導入するかなどの施策検討の前に、育成課題を関係者内で議論してください。経営課題から整理ができると尚良いです。
とはいえ育成課題を自分一人で考えるのはなかなか難しいものです。部内で確認しながら進められるワークシート付の無料ダウンロード資料がありますので、ぜひご参考になさってください。
【ワークシート・記載事例あり】 “グロービス式” 研修体系を最短で構築する7ステップ
5-2 社員個人への研修や啓蒙に偏った自律型人材の育成施策はやめましょう
社員を取り巻く環境にも目を向けてください。過去の例では、せっかくeラーニングを導入しても、管理職が社員の自律的な学びにストップをかけて、学ぶ意欲はあっても学び方に迷っていたということがありました。本当に解決しなくてはいけない課題は、社員個人以外にある場合も多いのです。人事の仕掛けや管理職からの働きかけが自律型人材の育成に影響することを考慮して、複合的な施策を考えましょう。
5-3 自律型人材の育成ゴールをeラーニングや公募施策の導入と混同しないように気を付けましょう
育成担当者の方との面談で「自律型人材を育成したいから公募施策をやりたい」「自律型人材を育成したいからeラーニングを導入したい」と、サービスと手法の話を混在してお話しされているケースがあります。しかし、公募施策もeラーニング導入も自律型人材育成の一つの手段でしかなく、育成ゴールではないはずです。成功する育成施策を実施するためには、現状の育成課題、育成する目的などを整理する必要があります。改めて関係者内で確認してください。
経営課題、育成課題の整理の仕方はこちらをご参照ください。
関連コラム はじめに知ってほしい「研修体系の考え方」
自律型人材の育成方法
自律型人材を育成する5つの方法についてご説明します。自律型人材の育成を計画する際、ぜひ参考にしてください。

育成担当者には、個人の自律を促すために働きかける役割が期待されます。本当に人材(側だけ)の問題だけなのか。自律的な働き方を促す組織になっているのか。あるいは、制度は整っていたとして、管理職が社員一人ひとりと、それぞれの自律性を促すような関係性を作れているかどうか。自律型人材の障壁になっていそうな課題は個人以外にもないのか、目を向けてください。
6-1 社員が仕事の意義・意味を理解する機会をつくる
社員が仕事の意義・意味を理解する機会をつくることは、自律的な人材を育てるために非常に大切です。経営層がビジョンや目標を伝え、それに基づいて自分の仕事の意義・意味を考える機会を与えることが欠かせません。
しかし、組織のビジョンや目標は社員にとっては距離感があり、「自分には直接関係がない」と思われがちです。その問題を解決するには人事だけではなく管理職も、組織のビジョンや目標にどう貢献しているのかを社員に伝えることが大切です。同時に、その組織のビジョンや目標が個々の社員のキャリアとどのように繋っているかを見せることも重要です。
組織のビジョンと社員本人の業務を結びつけることで、社員はビジョンや目標を自分自身のものとして受け入れ、権限移譲された環境で自律的に行動できるようになります。
具体的な施策例
- 経営層が社員に組織の目標やビジョンを伝え、理解してもらう機会がある(経営層からの講話、社内誌)
- 管理職は、社員に自分の仕事の期待役割を理解してもらう機会をつくる(管理職との1on1、MBOなど)
- 管理職は、日頃から組織のビジョンを社員に伝える機会をつくる(チーム内でのビジョンの読み合わせなど)
- 人事は、社員に自分のwill/can/mustを考える機会をつくる(キャリア研修、管理職との1on1など)
- 人事は、仕事を通じてどんな価値観・キャリアを実現したいか社員に考えさせる機会をつくる(階層別研修など)
つまり「社員が仕事の意義・意味を考える機会をもつこと」と、「管理職は社員が仕事に前向きな姿勢をつくること」が大切なので、下記のような研修がおすすめです。
グロービスの集合型研修サービス 自分のwill/can/mustを考える機会をもつなら「エンゲージメント向上プログラム」
自分自身の未来と会社の未来の重なりを見つけ、働くことの意義・意味をもつには、社員のエンゲージメント向上をさせる研修がおすすめです。
管理職のマネジメント力強化なら「社員の意欲・能力を引き出す職場マネジメントプログラム」
社員が仕事の意味意義を理解するために、管理職のサポートは重要です。研修プログラムで管理職のマネジメント力を鍛えて、社員の仕事のポジティブな姿勢をつくりましょう。
6-2 社員が仕事の変化やチャレンジに対して前向きになる環境を人事が整える
個人の自律的な行動を促すには、「自律的な行動が報われる組織である」と社員が認識していることが重要です。人事が仕組みを作ったとしても、社員が認識していなければ効果がないからです。自律的な行動を評価する仕組みやチャレンジを奨励する制度を人事が整備し、それを文化として根付かせる仕掛けが必要になります。新しい仕組みほど作っただけでは、形骸化してしまうので、組織文化とするためにどのような働きかけを行うのか仕掛けも合わせて考えましょう。
具体的な施策例
- 企業として、スキル保有者を優遇する報酬体系になっており、報酬体系が公開されている
- 企業として挑戦したことを評価する機会があり、評価基準は管理職と社員のすり合わせによって行われている(MBOなど)
- 人事や管理職は、新しいやり方をインプットするためのセミナーの参加や勉強会の開催を奨励する(業務時間内で勉強することができる文化)
- 企業として、誰でも使える自己啓発支援制度を設ける
関連コラム 越境学習とアンラーニング ~組織に変化を生み出す自律型人材を育成するには~ジョブ型雇用の導入に伴う、人事制度改革を進める際の効果的なプロセス
6-3 管理職は権限移譲し、社員が自分の責任で考え、主体的に行動するよう促す
管理職は社員へ権限移譲を最大限しましょう。権限移譲により、自分の責任で考え、主体的に行動する社員が増えていきます。管理職がすべての意思決定をしていたら、そのうち社員は自分で考えることを止め、管理職の判断を仰ぐという受け身なスタイルが出来上がっていきます。管理職は社員に権限移譲をし、自分の責任で考え、工夫できるように仕事を任せましょう。
具体的な施策例
- 管理職は、社員毎に適切な任せ方を考えさせるために、社員の特性を一覧化する
- 管理職は、進め方を細かく説明するのではなく、その先にある目的・背景を説明する時間を確保する
- 管理職は、社員の積極的な失敗を奨励し、必ずフィードバックを行う場を持つ
- 管理職は、社員が自分でPDCAを回せるように、考える時間を社員と共に持つ
- グロービスのサービス:管理職のマネジメント力強化なら「クリティカル・シンキング~部下育成の質問力~」
社員がアイデアを発言したときに、その発案を評価しながら、質問を通じてより考えさせられると良いです。動機付けを行い、モチベーションを高める質問力を身につけられるような研修がおすすめです。
関連コラム エンパワメント(権限移譲)とは?組織や個人にとって重要な理由と実行プロセス
6-4 社員が“こうすればうまくいく”という自信をつける
主体的な行動や発言には、「こうすればうまくいく」という根拠のある提案を自分の中にもてていることが望ましいです。自律性を発揮したいと思っていても、業務スキルや経験がなければ、自信をもった提案には至りません。社内で経験や知識を得たり、社外で学んだ内容が実務に活かせたりすると、改善提案や新たな事業への提案に繋がるはずです。学習計画を自分で立て、実行できた経験も成功体験の一つとなり、自信の礎になります。
具体的な施策例
- 人事は、社員の業務範囲や必要性に応じて幅広く学べる環境を用意する(経営知識インプット機会の提供)
- 人事は、主体的な行動を評価する機会や制度を作る(表彰制度の活性化など)
- 人事(や管理職)は、主体的な行動とはどのような行動なのかリーダーシップ論について学ぶ機会を作る
- 管理職は、社員の強み・弱みを理解できるようスキルマップを活用した1on1を行う
グロービスのサービス:社員個人のスキルアップをeラーニングで行うならeラーニング「GLOBIS 学び放題」
基礎〜最新知識・ビジネス周辺知識まで2200コース以上見放題の「GLOBIS 学び放題」(動画学習コンテンツ)がおすすめです。

関連コラム 自律学習を促す、学習設計のポイント
6-5 社員本人が、自律的な行動を組織の成果につなげられるようにする
単に主体的な行動や発言を行っていても、それが組織の成果に結びついていなければ、企業としては困ります。組織として評価される主体的な行動や発言とは何なのかを意識してもらえるように、社員と管理職が成果指標をすり合わせする機会、その成果に向けて考えるべきこと、取るべきアクションをすり合わせる機会が重要です。
具体的な施策例
- 会社の目指す方向と個人の目指すキャリアパスの方向性をすり合わせる(期待役割の明確化、職能要件やスキルマップを提示)
- 成果を明確に示す
- 社員が自ら振り返り、次に何をしていくべきかを考える機会を設ける(管理職との1on1、チームレビュー会、社員同士での対話など)
グロービスのサービス:管理職のマネジメント力強化なら社員のパフォーマンスを上げる対話力強化研修
組織で求められている成果とは何かを社員に理解してもらうために、目標管理における管理職のコミュニケーション力は重要です。管理職の評価面談における対話力を鍛える研修がおすすめです。
関連コラム 採用や昇格試験だけではない、アセスメント・テストや適性検査の幅広いデータ活用法とは~目標設定、評価、配置などの人事施策に活用する~
関連コラム 変化に即応する自律型組織の作り方 〜全員が主役となる「対話」の促進〜
自律型人材のよくある2つの課題と解決策
「自律型人材の育成に向けて施策を実施しているのに、なかなかうまくいかない」というお声も伺います。下記の課題はグロービスがよくご相談いただくケースです。課題と解決策を合わせてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
7-1 【課題】研修や評価制度は整ってきたが、社員が自律的に学習するというところになかなかつながらず活用できていない(例:公募制なのに手が上がらない、動画学習なのにログインしない)
【原因①】認識の壁:研修自体を認識できていないからやらない
実は、申請の仕方がわからない。そもそも申し込んだこと忘れているなど基本的な認識ができてないために、行動していない。申し込んだものの使い方がわからないためにログインができていないというケースもあります。
【原因②】行動の壁:実務に役に立つイメージが沸いていないからやらない
現業が忙しく、スキルの不足も感じていらっしゃらない場合、研修が実務に役立つイメージがわいておらず、「今はやる必要がない」と自分の判断基準だけで勝手に決めつけている可能性があります。
【解決策】認識の壁、行動の壁いずれの原因でも、人事が根気強く働きかけることが大切
受講者が強制感を感じず自分から学ぶためには、自転車の補助輪のように、最初のサポートが大切です。たとえば、自主学習ツールを導入したての半年間は受講者任せにしないでください。開講後すぐに未ログイン者へのメールでのリマインドする、職務要件・能力要件と研修内容をリンクさせた一覧を作るなど根気強い働きかけが重要です。
グロービスのワンポイントアドバイス
たとえば自主学習ツールを採用した場合の目標目安は、「導入1か月以内にログイン率100%、1コース視聴をすること」です。
そのためには開講前から、「必ず1か月以内にログインとコース視聴をしてください!」と事前のアナウンスをしてください。 開講後も下記のような働きかけを行ってください。
定期的に発信する際のコツ
- マインドメールを必ず週1回は送るように内容を整理して計画的に発信する(例:必須コンテンツの紹介、人気ランキングの紹介、テーマ別おすすめコンテンツの紹介、学習が続くコツなど)
- 発信内容は長々とした発信ではなく、スキマ時間にパッと目にして内容を理解できるくらいのカジュアルな文章にする(例: 「へぇ~」「後でこの動画見ようかな」とすぐに理解・判断できるような内容)
- “中の人”の温度感が伝わるような発信をする。発信者(事務局)の立場で興味を持ったコンテンツ紹介は、反応を得やすい。
事務局以外の発信から認知してもらうコツ
- 社内報に社長のメッセージと共に自主学習ツールの案内を掲載する
- 社員が毎朝必ず確認する「社内イントラ」に自主学習ツールのログインURLを掲載する
- 職場の上長から直接受講者に視聴する目的意義を伝えてもらう
視聴してもらうコツ
- おすすめコンテンツのURL(クリックしたらすぐにログインかつ視聴ができるURL)を送る
- 社員の職能要件に関連したコンテンツを周知する
諦めず根気強く働きかけて、全員がログインするのを見届けましょう。初動が肝心です。
担当者様向けお役立ちサイト 導入成功ガイドのおすすめコラム
【成功事例】株式会社ティーネットジャパン様「学びのコミュニティ」作りに成功した企業の受講活性とは?
7-2 【課題】管理職は社員の主体性や自律を促そうとしているが、つい指示を出してしまって相手のモチベーションを下げてしまう
【解決策】管理職の意識改革が必要です。
せっかく意欲ある若手が入社しても、管理職が仕事をかかえすぎて仕事を適切に任せなかったり、マイクロマネジメントになったりすると、自律型人材とは真逆の指示待ちの社員をつくりだすことになってしまいます。管理職は社員の原動力となる価値観や目指すキャリアを聴いて、意義意味を見出せるような仕事をアサインすることが必要です。そのために、傾聴力や質問力といった「対話のスキル」を向上させましょう。
グロービスのワンポイントアドバイス
対話のスキルに重要なのは「リクエストを話すのではなく、お互いのニーズを話すこと」です。
指示命令型や目標管理型のリーダーシップでは、「君にこうしてほしい」という目標を管理職が定め、できた・できていないを〇×で評価しますが、これでは社員は自分の頭で考える必要がないので、自律レベルが下がります。そうではなく、社員の意見を主軸にジョブを設計していくことで自律性は高められます。


(※参考)GLOBIS 学び放題「部下の自律を促す仕事のデザイン」
◆面談ではなく「対話」にするための4つのコツ
①自分の考えや判断を一旦保留し、相手が言っていることをまずはそのまま受け止める(聴き切る)
②相手が自分で考えさせるように問いを投げかける(引き出す)
③業務やコトではなく、その人の考えや感情・価値観にフォーカスを移す。たとえば、業務進捗確認は「例の件、どう進んでる?」と聞くが、対話なら「あの件について、何か気になることはある?」という聞き方になる
④部下と意見をすり合わせる際には、「自分にとってこれが大事だからこれを達成したいと思っている」と自分を主語にする
一方的に意見を伝えるのではなく、考えさせたり、フラットに同じ目線で一緒に考えたりすることの繰り返しが、社員の主体的な意思の表明・行動に結びつきます。
関連コラム 変化に即応する自律型組織の作り方〜全員が主役となる「対話」の促進〜
自律型人材の育成には 人事から管理職へのフォローも大事
とはいえ、ここまで読まれた方は「管理職のやることが多く、大変だな」と感じた方も多いのではないでしょうか。本人への動機づけにしても、主体的な行動を促す環境づくりにしても、職場の管理職の行動がカギです。しかし、管理職が重要だからといって人事は管理職に頼りすぎたり任せすぎたりしてはいけません。管理職も年々役割が広がり、負担が過重になってきているからです。

難しい役割に奮闘する管理職の実情を理解し、労い、敬意を持ったフォローが重要だとグロービスは考えます。 管理職自身、自らを客観的に振り返り自分をアップデートしたいと思っていても、日々の仕事が忙しいあまりわずかな時間しかとれないのが現実です。人事が主導して、仕事の意義意味や新しいマネジメントスタイルについて、見つめ直す内省の場や時間を意図的に設けましょう。
関連コラム セルフ・コンパッションを組織で実現する~誰もが燃え尽きず、組織で成果を出すマインドセット~
自律型人材育成の成功事例
続いて4つの事例をご紹介します。いずれも育成研修によって主体的な行動や自律的に学ぶ風土の醸成といった組織変容を促すことができた事例です。ぜひ自社の課題と施策の期待に合うものを参考にしてください。
- 9-1 【国分グループ】優秀な若手が飛躍できる研修によって、主体的に働くモチベーションをつくれた事例
- 9-2 【SAP】営業担当者が経営知識を得たことによって、提案力の向上と自律的学習につながった事例
- 9-3 【コロワイド】管理職層が学び始めたことによって、自律的に学ぶ組織の風土醸成につながった事例
- 9-4 【雪印メグミルク】管理職層がリーダーシップ研修によって、部下の自律を促すマネジメントができるようになった事例
9-1 【国分グループ】優秀な若手が飛躍できる研修によって、主体的に働くモチベーションをつくれた事例


課題
- 優秀な若手社員が目の前の仕事に忙殺され、視座視野が低く狭くなりつつあった
- 優秀な社員が自分自身を表現する場が無く、経営陣へアピール場が必要だと考えていた
- 以前に行っていた研修は実行まで移せていないジレンマがあった
研修内容
- 【公募型選抜研修】30代向け次世代リーダー研修。論理思考・経営知識の研修後、自社課題を提言・実行までを含めたプログラムを実施

研修後の効果・成果
- アウトプットの報告の質が中間報告と最終日で全くレベルが異なっていて、受講者の成長を感じられた
- 研修終了後も、提言された内容が自然と実行フェーズへ移っている
この事例のポイント
- 社長のビデオ講話で「研修で提言された案を推進する」と会社としての本気度を伝えた
- 各カンパニー/部門が一緒に練り上げて経営陣に提案する設計にすることで、研修で作成した提言が提言のまま終わらないようにした
グロービスの解説
- 優秀な若手社員が自分自身を経営陣にアピールする場、かつ自ら手を挙げて自身の成長にコミットする機会とコンセプトを明確にしたことで、狙い通り、意欲ある優秀な若手社員の視座を高めることに貢献しました。経営陣の皆様もテーマ設定から関わるという本気度が受講者に伝わって、モチベーションが高い研修となりました。
お客様の声
アウトプット中心かつ高レベルな講師がそろっていることが良いですね。グロービスの研修を見学した後に他社の研修を見ると、「あれ?」と思うこともあるぐらいです。受講者が挫折しやすい科目、たとえばアカウンティングは導入部分が工夫されていて、没入しやすい構成になっていました。学びやすさも大切なポイントですね。

人事総務部 人材開発課 グループ長 中島秀典様様(インタビュー当時)
【国分グループ】優秀な若手が飛躍できる研修によって、主体的に働くモチベーションをつくれた事例
9-2 【SAP】営業担当者が経営知識を得たことによって、提案力の向上と自律的学習につながった事例


課題
- お客様への提案内容が経営課題の解決に紐づけられていないシーンがあった
- 個人のマインドセットとスキルの両面について必要性と緊急性を感じていた
研修内容
【選抜型研修】営業マネージャー向け、営業研修プログラムを実施

研修後の効果・成果
- これまで経営の考え方から遠かった参加者ほど、学びのサイクルが回り始めた
- お客様に対する提案力や価値訴求力が格段に上がった
- 研修で学んだことに加えて、自分で理解を深めるべき分野を見つけてセルフラーニングし始めた
この事例のポイント
- マインドセット・経営スキルに加えて、世界や国の動き、日本企業の特徴的な経営スタイルや課題、企業固有の源流を理解するマクロ視点を養う内容などもカスタマイズした
グロービスの解説
- 長くタフな研修期間中、思い切り学んでもらえるように、事務局様が受講者全員と1on1をして状況を聞き、受講者の気持ちや環境を整えるサポートを行っていました。
- 担当した講師は、受講者へ「顧客の課題と未来について、顧客が言っていることや公開資料に書かれていることでなく、皆様はどう考えるのですか?」を繰り返し問わせていただき、研修コンセプトに合うようなスタイルにさせていただきました。その結果、自分で課題を見つけ、考えを深めていくというセルフラーニングの姿勢が生まれていきました。
お客様の声
講師陣の一言一言が、受講者に「このレベルではダメだ」と思わせ、ストレッチして学ぶためのサポートだったと感じます。プランには実現性があるのか、ステークホルダーを巻き込めるか、お客様に価値訴求できるものなのか、といった指摘を多くいただきました。単にグロービスのプログラムが提供されるのではなく、当社が真に実現したいことへ向けたサポートをしていただきました。
答えを与えるのではなく議論するきっかけを作り、問いを投げ、深めていく。ここがグロービスの価値のひとつですね。

SAP Customer Experience 事業本部 シニアディレクター パートナーセールス 高橋 佳希様(インタビュー当時)
【SAP】営業担当者が経営知識を得たことによって、提案力の向上と自律的学習につながった事例
9-3 【コロワイド】管理職層が学び始めたことによって、自律的に学ぶ組織の風土醸成につながった事例
課題
- 現場での店舗運営のスキル・経験と、管理職で求められるスキルにはギャップがある
- 過去の研修は参加必須のものが多く、受講者にモチベーションがないと学んだことが身に付きにくいケースもあった
研修内容
【管理職層向け公募型研修】ビジネススキルを習得するためにeラーニングと他流試合形式で研修を実施
研修後の効果・成果
- 自分の仕事とは異なる領域の知識・スキルが身に付いたことで、他部門の業務への理解が深まり、部門間の協力や会話の質も変わってきた
- 受講者のほとんどが、他社を含む全受講者の平均視聴時間を上回る視聴時間で学習していた
この事例のポイント
- 人事制度と紐づけたり、公募制度にしたりすることで、会社任せではなく自らの意思で学ぶ社員が増えるような設計にした
グロービスの解説
- 導入して間もない時期は、事務局様が動画を選定して、受講者へ頻繁にメール発信をし「まず学ぶべきことは、ここに揃っている」と示していました。社員の皆様の中には、自分への危機感がある一方で、何から学べば良いのかがわからなかったという方もいます。そうした受講者も学びやすい工夫をされていました。
お客様の声
今年からグロービス・エグゼクティブ・スクール(GES)への派遣とアクションラーニングを実施する次世代リーダープログラムをスタートさせたところです。初回のGES公募では、予想よりも多くの社員が「課題の負荷が大きくても、キャリアアップしていきたい」と意欲的に手を挙げてくれました。
以前の当社の風土であれば、自発的にスキルアップをしていくためのプログラムに手上げする社員は少なかったでしょう。GLOBIS 学び放題で学習したことで、学ぶ楽しさを感じたり、自分はもっとやれるかもしれないという自信が芽生えたりした結果、自律的に学ぶ風土づくりができたのだと思います。
【コロワイド】管理職層が学び始めたことによって、自律的に学ぶ組織の風土醸成につながった事例
9-4 【雪印メグミルク】管理職層がリーダーシップ研修によって、部下の自律を促すマネジメントができるようになった事例


課題
- 汎用的なビジネススキルと広い視野の獲得に向けた育成を十分に行えていなかった
- 変革を“創っていく“リーダーシップスタイルは、従来の業務の中では培えていない部分があり、意識的に強化していく必要があった
研修内容
【課長層向け選抜型研修】企業内集合研修で経営科目12講座を受けた後、最終講座では1日ケーススタディを実施

研修後の効果・成果
- 研修後、課長が変わったという部下からの声があった
- 『その仕事の目的はなんだったのか、そこを考えなさい』『ゼロベースで発想しなさい』と課長からのフォローがとても勉強になっているという声があった
この事例のポイント
- 経営の基礎科目を網羅的に受講したことで、学びによって自分の仕事の幅が広がることを実感していた
- 「自分はこんな考え方の癖を持っていたのか」と自覚したことで、受講者は自分の考え方を変えなければならないということに気が付いていった
グロービスの解説
- 基礎知識を幅広く学んでいただいたことで、得意な領域が自分の仕事に活きるだけではなく、苦手な領域も「もっと学んだ方が良い」と意欲的になり、さらなる学びにつながる研修になりました。
- また雪印メグミルク様では、プログラムの見直しを毎年行っています。環境変化の激しい時代において、会社の求めるリーダー像も変化しますし、受講者の思考や行動特性も異なっていくからです。その時にベストな研修とは何かを考え抜いたプログラム設計だからこそ受講者の行動変容を促せていると思います。
お客様の声
人材育成についてあまり詳しくなかったこともあり、佐々木さん(グロービス担当者)にいろいろと質問をしていました。いつもこちらの期待以上の回答・情報をいただけていたことが強く印象に残っています。佐々木さんから提示される資料は、過去に人材開発に携わってこなかった私にも、非常に分かりやすいものばかりでした。情報交換を通じて信頼関係が生まれていたので、その後の提案も違和感なく受け入れることができましたね。

人事部 担当部長 守屋彰様(インタビュー当時)
【雪印メグミルク】管理職層がリーダーシップ研修によって、部下の自律を促すマネジメントができるようになった事例
自律型人材育成を外部パートナーへ依頼するなら、 グロービスをお勧めする3つの理由
もし自律型人材の育成研修を外部へ依頼しようとしているなら、ぜひグロービスへお問い合わせください。本コラムでお伝えしてきた通り、自律型人材の育成には次のような難所があります。
- 【難所1】課題を特定しないまま流行りの施策に飛びついて、研修の効果は何だったのかわからなくなってしまう
- 【難所2】研修施策やeラーニングを導入しても、受講促進のノウハウがなく、結局活用できていない
- 【難所3】複合的な育成施策の検討が必要だが、研修プログラムが多すぎて、効果的な施策の組み合わせ事例がわからない
このような難所に対してグロービスの研修は様々な打ち手をご用意し、受講者の行動変容、組織の文化醸成をサポートしてきました。

これまで自律型人材の育成をサポートしてきたグロービスだからこそ、難所をカバーした育成施策をご提供できます。それぞれの研修の特徴について詳しく解説します。
10-1 貴社の立場で経営課題を考え、要件定義、研修の設計・実施まで一気通貫でサポートできる
論点がいくつも絡み合う自律型人材の育成には、育成課題を整理し、打ち手を明確にする必要があります。課題を特定しないまま流行りの施策に飛びついて、研修効果が不明瞭にならないために、貴社の経営課題から育成課題を考えるのがグロービス担当者です。なぜならグロービス担当者はほぼ全員、MBAを所有しているため、経営の上流から議論をし、貴社の問題意識と世の中のトレンドも加味したご提案が可能だからです。他の研修会社との大きな違いは、この点です。社内事情をふまえ、貴社にとって再現性の高いプログラムを提案いたします。
お客様の声
成果が見られているのは、グロービスに当社の社内事情をご理解いただき、外部の潮流も踏まえて本プロジェクトの企画と運営、ブラッシュアップの提案に至るまでご尽力いただいたからだと思っています。我々の課題感をざっくり伝えたところから具体的な企画に落とし込んでいただくだけでなく、改善のご提案もゴールを見据えたものになっており、本当に助けられています。

鈴与株式会社 人財開発部 チームリーダー 藤田佳秀様
【鈴与】激しい環境変化の中で、「ぶれない軸」を持ち自社の成長をけん引する次世代リーダーを育成する
10-2 施策の導入後も受講促進・活性に向けた設計ノウハウのご提供、研修内容のチューニングなどサポートがある
運営面でもグロービスがお力添えできます。例えば、動画学習サービスの「GLOBIS 学び放題」では、受講者フォローのための分析ツールをご用意したり、受講開始後の学習実績から今後の受講促進に有効な施策を提案したり、貴社の状況に合わせて自律型学習が持続できるようにサポートさせていただきます。
お客様の声
受講促進策のアドバイスを数多くいただけました。GLOBIS 学び放題の導入支援の経験が豊富で、様々なノウハウを持っているのですよね。結果として、申し込みは1,700人弱、開講後120日以上経った時点でのログイン率は98%です。かなり良い数字だと聞いています。

株式会社SUBARU 人財マネジメントグループ 稲森文華様
【SUBARU】 学びの場を提供し、個人の自律的成長を後押しする人財育成プログラム。”学び”、”変える”組織をデザインする
長期間にわたるテーラーメイド型の研修では、プログラムの企画前から研修終了まで同じ担当者が伴走します。必要であれば研修の途中でも、貴社の期待に応じて研修内容などを調整することがあります。
お客様の声
7か月間と長いプログラムなので、最初に全体像を描いてスタートしても、想定と違うことが起こります。なので、7ヶ月、全11回のプログラムで毎回PDCAを回し続けました。大変ありがたかったのは、尾花さんやファシリテーターの方と率直な議論ができた点です。要望を伝えると、文脈を理解しながら建設的な姿勢で、何度もカリキュラムのファインチューニングをしてくださいました。

武田薬品工業株式会社 グローバルHR 人材・組織開発(日本)ヘッド 赤津恵美子様
【武田薬品工業】グローバルリーダーとしての当事者意識が、自発性と社内の変化を生み出した
10-3 豊富なプログラムを揃えているので、相乗効果のある育成施策を提供できる
貴社の課題をしっかりヒアリングさせていただくので、本質的な問題意識に対して豊富なプログラムを柔軟に育成施策へ反映することが可能です。育成施策の営業担当者が設計から実施までサポートするため、育成課題のコンセプトがブレることなく施策を実行できます。プログラムとしては、下記のように集合型研修だけでなく、他流試合やアセスメント・テスト、eラーニングなど幅広くご用意しています。人事担当者ご自身で育成施策全体をコントロールするのが大変な時には、効果的な施策の組み合わせ事例をご紹介しますのでグロービスへご相談ください。
~次のような豊富な研修プログラムを、社内事情を加味しながら相乗効果が得られるようにご提案します~
- グロービスの集合研修はこちら
- グロービス・マネジメント・スクール(GMS)の詳細はこちら
- グロービス・エグゼクティブ・スクール(GES)の詳細はこちら
- アセスメント・テストGMAPの詳細はこちら
- GLOBIS 学び放題の詳細はこちら
お客様の声
グロービス・マネジメント・スクールへの通学やGLOBIS 学び放題など、グロービスのさまざまなコンテンツをA-CAPのプログラムに取り入れられる柔軟性も、決め手のひとつでした。

アサヒビール株式会社 経営創造本部 人事総務部 副課長 村瀬進様
【アサヒビール】経営課題に真正面から向き合う次世代リーダー育成を通して、事業変革の立役者を輩出する
まとめ
最後に、本コラムでお伝えしたポイントは以下のとおりです。
- 自律型人材に学術的な定義はなく、各社が自社なりの定義をつくるべきである
- 自律型人材の”あるべき人材像”を考える際は、定義した内容が自社の理念・事業戦略に沿う内容になっているか関係者内で確認する
- 研修テーマや手法といった方法論から検討するのではなく、「自社にとって何が必要なのか」という視点を大切にする
- 社員個人への研修や啓蒙に偏った自律型人材の育成手法ではなく、人事制度からの働きかけや管理職との関係性といった複合的な視野をもつ
- 自律型人材の育成方法は5つある
- 社員が仕事の意義・意味を理解する機会をつくる
- 社員が仕事の変化やチャレンジに対して前向きになる環境を人事が整える
- 管理職は権限移譲し、社員が自分の責任で考え、主体的に行動するよう促す
- 社員が“こうすればうまくいく”という自信をつける
- 社員本人が、自律的な行動を組織の成果につなげられるようにする
- 研修テーマや手法といった方法論から検討するのではなく、「自社にとって何が必要なのか」という視点を大切にする
自律型人材育成は、どの組織にとっても今後の事業成長を左右する重要なテーマです。
上記ポイントを押さえ、貴社に合う自律型人材を輩出していきましょう。
自律型人材の育成にお悩みの方は、ぜひグロービスへご相談ください。皆さまの悩みや課題に合わせ、最適な情報の提供・育成手法のご提案をさせていただきます。

※文中の所属・役職名は原稿作成当時のものです。