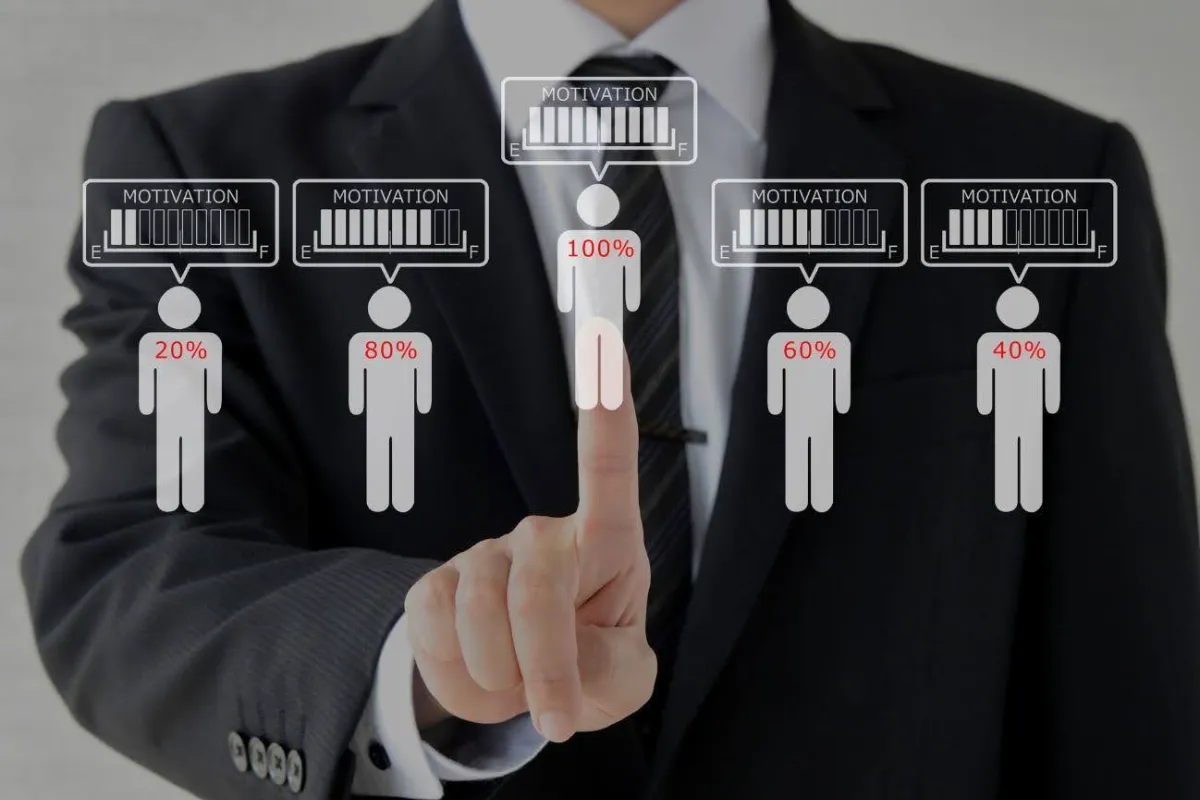
スキルマップの評価基準の設定方法|各段階の特徴とポイント
人材育成や人材配置などを行う際に役立つスキルマップは、適切に評価を行うために明確な評価基準を設けることが大切です。しかし「どのように評価基準を設定すればよいか分からない」とお悩みの方も多いでしょう。本記事では、スキルマップの評価基準の設定方法と各段階における特徴、設定の際のポイントについて解説します。
目次
スキルマップの評価基準を適切に設定する重要性
スキルマップとは従業員の業務遂行能力を点数化して一覧表にしたもので、スキルの習熟度や不足しているスキルの把握が可能になるため、人材育成や人材配置、人事評価などに活用できます。
社員のスキルを適切に評価するには、評価基準を設定することが大切です。しかし、「できる・できない」の2択だけでは「どのスキルを、どの程度習得しているか」を把握できないため、適切な評価を行うことはできません。スキルマップの評価基準や評価段階に一般的な正解はありませんが、評価内容に応じて適切に設定する必要があるのです。
よって、評価基準は単体で考えるのではなく、スキル項目や評価段階とセットで設定するようにしましょう。たとえば、以下のように設定します。
| スキル項目 | 評価段階 | 評価基準 |
|---|---|---|
| 電話対応 | レベル4 レベル3 レベル2 レベル1 | ・人に指導することができる ・一人でできる ・指導を受けながらできる ・できない |
このようにスキル項目や評価段階とセットで設定することで評価基準が明確化され、評価者は「どのスキルを、どの程度習得しているか」を判断しやすくなります。社員一人ひとりの保有スキルを正しく評価できるようになれば、効率的な人材育成や適切な人材配置、公平な人事評価につながるでしょう。
スキルマップの評価基準における各段階の特徴

スキルマップは段階をいくつか設けて評価基準を設定することで、適切な評価が可能になります。段階数の決まりは特にありませんが、3~5段階で評価することが一般的です。
そのため、各段階における評価のメリットやデメリットをしっかり理解したうえで、適切に評価段階を設けることが大切です。スキルマップの評価基準における各段階の特徴について詳しく見ていきましょう。
2段階評価
2段階評価とは、「できる・できない」「はい・いいえ」「ある・ない」というように二項対立で行う評価です。特定のスキルや資格、経験などの有無について確認する際は、2段階評価が効果的でしょう。有無について問う評価方法なので、判断に迷うことがなく明確な評価が可能になります。
ただし、「ある」か「ない」かの評価しかできないため、スキルや能力の程度を評価したい場合には不向きです。2段階評価は限られたスキル項目にしか設定できないことから、スキルマップに用いられることはほとんどありません。
3段階評価
3段階評価とは、「○・△・×」「高・中・低」「上・中・下」など3つの選択肢を設けて行う評価です。たとえば「○:1人でできる」「△:ほぼ1人でできる」「×:できない」というように、スキルや能力の程度について問うことが可能になります。
シンプルゆえに直感的に評価しやすく、評価者が判断に迷うことはほぼないでしょう。ただし、評価基準が曖昧な場合、中間の評価にあたる「△」「中」を選択しやすくなるというデメリットがあります。中間の評価への偏りを防ぐには、「○(高・上)」や「×(低・下)」の評価基準を明確に設定するといった工夫が求められます。
4段階評価
4段階評価とは、「A・B・C・D」「4・3・2・1」「よい・どちらかというとよい・どちらかというと悪い・悪い」など4つの選択肢を設けて行う評価です。たとえば「A:人に指導できる」「B:1人でできる」「C:指導を受けながらできる」「D:できない」というように、3段階評価よりも具体的にスキルや能力の程度について問うことができます。
中間の選択肢がないので良し悪しを明確に評価でき、評価される側の社員からも納得感を得られるでしょう。ただし、中間の選択肢がないことによって評価しにくくなるという人もいるため、評価者からの理解が得にくい場合があります。
5段階評価
5段階評価とは、「A・B・C・D・E」「5・4・3・2・1」「よい・どちらかというとよい・普通・どちらかというと悪い・悪い」など5つの選択肢を設けて行う評価です。たとえば「A:人に指導ができる」「B:イレギュラー対応もできる」「C:1人でできる」「D:指導を受けながらできる」「E:できない」というように、3段階評価や4段階評価よりもさらに細かくスキルや能力の程度を評価できるようになります。
具体的な評価によって評価される側の社員の納得感も高まるのがメリットです。最高評価を得られれば、社員のモチベーション向上も期待できるでしょう。ただし、中央値があることから中間の選択肢に評価が偏る可能性も否定できません。また、評価基準の細分化によって、かえって最高値や最低値をつけにくくなり、無難な評価を行ってしまうという人も多いのが特徴です。
スキルマップの評価基準を設定する際のポイント

スキルマップを作成する際は、評価者によってバラつきが出ないように評価基準をしっかり設定することが大切です。スキルマップの評価基準を設定する際のポイントは、以下の4つです。
スキル項目を具体的に設定する
評価者によるバラつきを防ぐには、スキル項目を具体的に設定する必要があります。たとえば、「顧客対応スキル」という抽象的なスキル項目では業務内容の範囲が広すぎるので何を基準に評価すればよいかが曖昧になり、評価者によってバラつきが出やすくなります。
そのため、「顧客対応スキル」を大項目とし、小項目として「丁寧な言葉遣い」「電話対応」「クレーム対応」というようにスキルを細分化して、スキル項目を具体的に設定しましょう。スキル項目を具体的に設定することで、そのスキルに対して適切な評価を行えるようになります。
公開前にテストを実施する
スキルマップを作成したからといって、いきなり全社展開するのは避けるべきです。不備がないかを確認するために、まずは試験的に導入して評価者数人に実際に評価してもらいましょう。
「作成者の意図する通りに評価ができるか」「分かりにくい点や評価しにくい点はないか」など、不備や評価者によってバラつき・認識のズレがないかをチェックします。フィードバックをもとに都度ブラッシュアップを行って、精度を高めてから公開することが望ましいです。
マニュアルやルールを設ける
スキルマップを活用する際、人事担当者や各部門・部署の上長などさまざまな人が評価者になる可能性があります。そのため、誰が評価しても同じ結果になるように、マニュアルや使い方のルールを設けることが大切です。
スキルマップ作成の目的や見方、評価基準、活用方法などを明記することで、認識のズレを防げるようになります。また、スキルマップを更新する際はあわせてマニュアルの見直しも行って、常に最新の情報を保つようにしましょう。
必要に応じて評価者研修を実施する
社内に評価者の適任となる人材がいない場合は、評価者研修を実施してスキルの底上げを行うのが効果的です。「なぜスキルマップを活用するのか」「スキルマップをどのように活用するのか」「評価基準の意図」「評価の実践練習」など、スキルマップを使って評価を行ううえで必要な知識やスキルを習得してもらいましょう。
まとめ:スキルマップは評価基準を明確化することが大切!
スキルマップを活用するには、評価基準を明確化して適切な評価を行うことが大切です。評価基準を設定する際はスキル項目や評価段階とセットで考えることで、評価者が基準に沿って評価を行いやすくなります。本記事でご紹介した内容を参考に評価基準を設定し、作成したスキルマップを人材育成や人材配置などに活用しましょう。
また、スキルマップに沿った研修を実施する際は、学習管理システム「GLOPLA LMS」を導入することで複数の研修を管理できるようになります。学びやすい受講画面も搭載しているため、社員の意欲的な学習にもお役立ていただけるでしょう。スキルマップの作成とあわせて研修の実施をご検討の際は、ぜひお気軽にご連絡ください。
