
eラーニングの受講は労働時間に含まれる?注意点と運用のポイント
社内研修にeラーニングを導入している企業は増えていますが、eラーニングによる学習は労働時間に含まれるのかどうか分からないという方も多いでしょう。eラーニングで研修を行う際は、あらゆるトラブルを防ぐためにも運用方法に注意する必要があります。本記事では、eラーニングの受講が労働時間に含まれるかどうかと運用時の注意点について解説します。
目次
eラーニングの受講は労働時間に含まれるのか
eラーニングの受講が労働時間に該当するかどうかの判断は、受講義務の有無によって異なります。eラーニングの受講と労働時間の関係性について、それぞれ詳しく見ていきましょう。
受講が任意の場合は含まれない
eラーニングの受講が義務ではなく任意の場合は、労働時間に含まれません。時間や場所の制約がなく、企業からの命令や指示がない場合は社員の自主性に委ねられているため、業務との関連性が薄いと考えられています。
自己啓発を目的としたeラーニング学習であっても、企業側で目標設定や場所・時間の拘束を行っていない場合は任意の受講となり、企業は社員の自己啓発を支援しているだけとみなされます。そのため、社員が自主的に就業時間外や休日に学習を行っても労働時間には該当しないのです。
業務上の命令や指示による受講の場合は含まれる
eラーニングの受講が業務上の命令や指示によるものである場合は、業務と直接関連性のない社内外研修であっても労働時間に含まれます。また、業務上の命令がなくても受講しないと罰則や評価・査定に影響するなど、社員にとって不利益が発生する場合や受講しないと業務に最低限必要とされる知識やスキルを習得できない場合も、実質的な強制とみなされ労働時間に該当すると考えられています。
そのため、業務上の命令や指示によって就業時間外や休日に社員がeラーニングで学習を行った場合は、残業代や休日出勤手当を支給しなければなりません。
eラーニングの労働時間に関する参考判例
eラーニングによる受講が労働時間に含まれるか否かについて、企業と社員とのトラブルが発生している例は少なくありません。以下の判例を参考に、自社のeラーニングの運用にお役立てください。
<労働時間に含まれない場合>
- 業務上の命令や指示がなく、受講が強制されていない
- 時間や場所の拘束や評価への影響などがなく、社員が自主的に自己啓発に取り組んでいる
<労働時間に含まれる場合>
- 業務上の命令や指示があり、受講義務がある
- 業務上の命令や指示はないものの、受講しないと罰則や評価などに影響するといった不利益が発生する
- 業務上の命令や指示はないものの、受講しないと業務に最低限必要とされる知識やスキルが習得できない
eラーニングを行う際の注意点
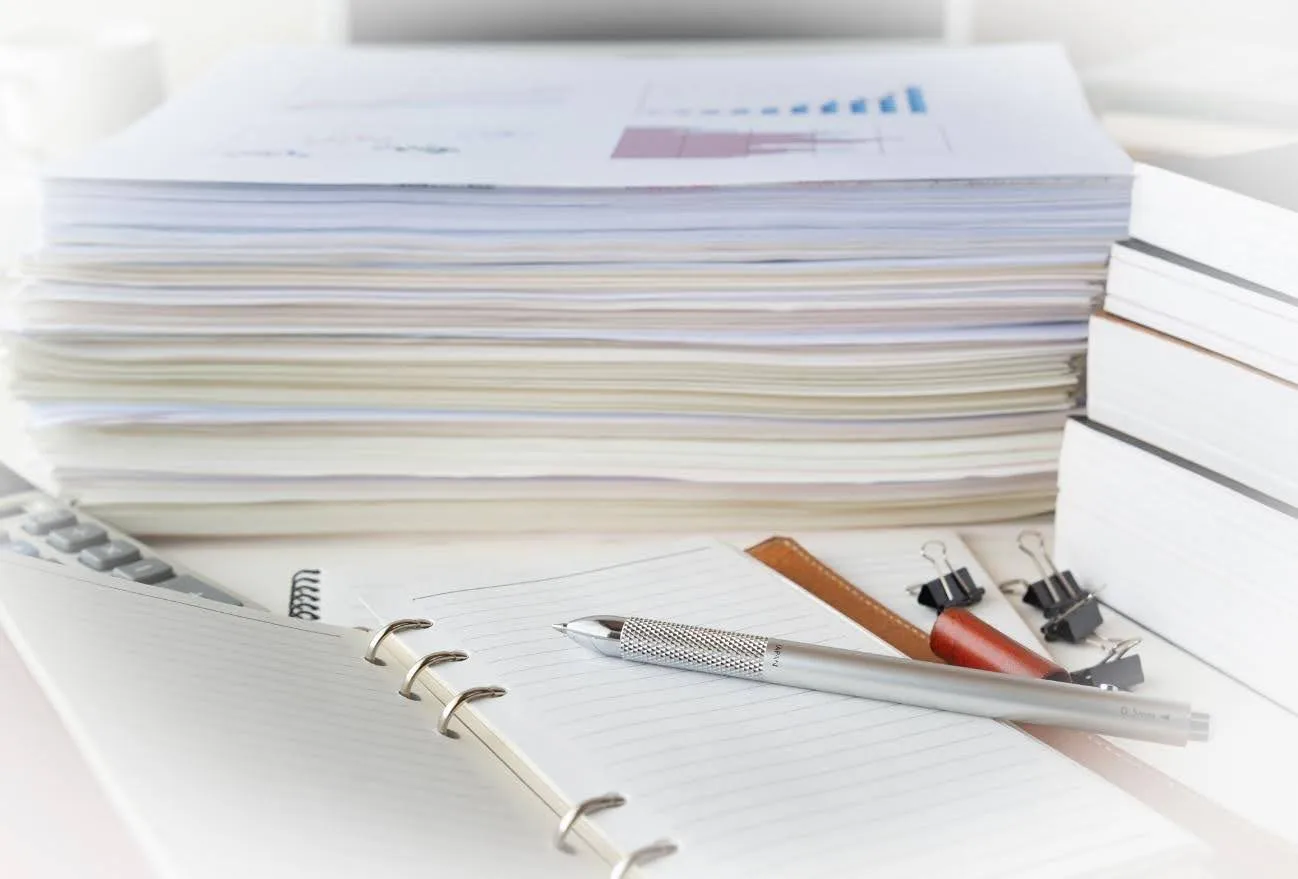
eラーニングの運用方針によって労働時間に該当するか否かが異なることが分かりました。そのため、eラーニングによって学習を行う際には注意しなければならない点があります。eラーニングを行う際の注意点は、以下の3つです。
eラーニング導入前にルールを策定・周知する
eラーニングを導入する前に、eラーニングに関して社内ルールを策定し、周知することが重要です。あらかじめ社内ルールを策定しておけば、トラブルを未然に防げるでしょう。
eラーニングに関する社内ルールとして、以下のようなものが挙げられます。
- 受講義務の有無(強制か任意か)
- 受講による罰則や人事評価への影響の有無
- 受講可能な時間や場所
- 受講可能なデバイス
- 労働時間に含める場合の賃金について
そのほか、社内におけるeラーニングの運用方針において判断が必要となる項目があれば、ルールとして明確に定めておくようにします。また、eラーニングの導入目的や研修目的・目標についても全社的に周知しておくことで、社員の学習意欲の向上につながるでしょう。
関連記事「eラーニング導入のメリットと成功率を高めるポイントを解説」
労働時間に含めない場合は社員の自由意思に任せる
eラーニングの受講を義務としない場合は、労働時間に含めず社員の自由意思に任せるようにします。受講を推奨することは可能ですが、任意であることをしっかり説明したうえで、あくまでも学習意欲が向上するようにサポートに徹するのみにしましょう。
受講を命令・指示しない場合であっても、時間や場所の拘束、受講しなかった場合の罰則や人事評価との結びつけは受講の強制に該当するので、ルールとして設けないように注意してください。
労働時間に含める場合は原則就業時間内に受講させる
eラーニングの受講を義務とする場合は、労働時間に含めなければなりません。受講を命令・指示しない場合でも、受講しないと罰則や人事評価に影響するといった不利益が発生するルールを設けるようであれば、労働時間に含める必要があります。
労働時間に含める場合は原則として就業時間内に受講させるのがベストです。就業時間外や休日の受講となると、社員の不満が募ったり残業代や休日出勤手当を支給しなければならなかったりするため、トラブルに発展するリスクもゼロではありません。
また、労働時間に含める際はeラーニングの受講時間を正確に管理できるように、管理機能が備わったシステムを導入するようにしましょう。社員研修としてeラーニングを活用する場合は、レポートを提出させることも効果的です。
eラーニングを効果的に運用するポイント

eラーニングで研修を行う際は、あらかじめ策定した社内ルールに則って運用することが大切であり、トラブル防止につながります。そのほか、eラーニングを効果的に運用するには、以下の3つのポイントを押さえておくと良いでしょう。
LMS(学習管理システム)を導入して受講時間を管理する
eラーニングの受講時間を管理するには、LMS(学習管理システム)の導入がおすすめです。LMSはeラーニングをはじめ社内のあらゆる研修を一元管理するシステムで、受講者の学習進捗状況をリアルタイムで確認できるのが特徴です。受講履歴やテストによる理解度の確認も可能になり、自動リマインド機能を活用すれば受講漏れの防止にも役立ちます。
また、eラーニングの受講時間を正確に把握するために、読み飛ばし防止機能が搭載されたLMSを導入すると良いでしょう。動画をスキップまたは途中で離脱した場合は「受講完了」と判別されない機能のため、不正防止につながります。ただし、受講者が高い集中力を維持したまま学習できるように、短時間で受講できるコンテンツを用意するといった配慮も必要です。
関連記事「LMS(学習管理システム)とeラーニングの違いとは?LMSを導入するメリットを解説」
マルチデバイス対応のものを選ぶ
社員の学習意欲を高めるには、マルチデバイス対応のeラーニングを選ぶことが重要です。社用パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットからも受講ができるようになれば、スキマ時間を使って効率的に学習を進められるようになります。
マルチデバイスに対応していれば時間や場所の制約がなく自由に学習できるようになるため、受講者も集中できる環境を選択してモチベーションを維持しながら学習に取り組めるでしょう。内定者に向けた入社前研修にも活用できます。
フィードバックをもとに改善を繰り返す
eラーニングによる学習効果を高めるには、実際に受講する社員からのフィードバックをもとに改善を繰り返すことが大切です。eラーニングで受講した研修に対してヒアリングを行い、「内容が分かりにくい」「受講時間が長く集中力が持たない」といったフィードバックがあれば、修正を行いブラッシュアップしていきましょう。
せっかくeラーニングを導入しても、効果を得られなければ意味がありません。受講者の声に耳を傾けて、必要に応じて改善を繰り返すことで、学習効果の向上が期待できます。
まとめ:eラーニングを導入する際は受講義務の有無と労働時間に注意しよう!
eラーニングの受講が動労時間に含まれるか否かは、受講義務の有無によって異なります。自社でeラーニングを導入する際は、あらかじめ強制受講または任意受講かをはじめ、社内ルールを策定したうえで運用することが大切です。また、受講時間を正確に管理するためにはLMSの導入がおすすめです。LMSは各ベンダーによって機能や操作性、サポート性などが異なるので、自社に適したものを選ぶようにしましょう。
「GLOPLA LMS」は、誰でも使いこなせる学習管理システムです。操作に迷わないシンプルなUI&UXと厳選された必要機能によって、受講者の学習意欲の向上につながります。また、カスタマーサポートが導入後の定着から運用までサポートするため、LMS上で質の高い研修を提供できるようになります。eラーニングの効果的な運用にLMSの導入をご検討の際は、ぜひお気軽にご連絡ください。
