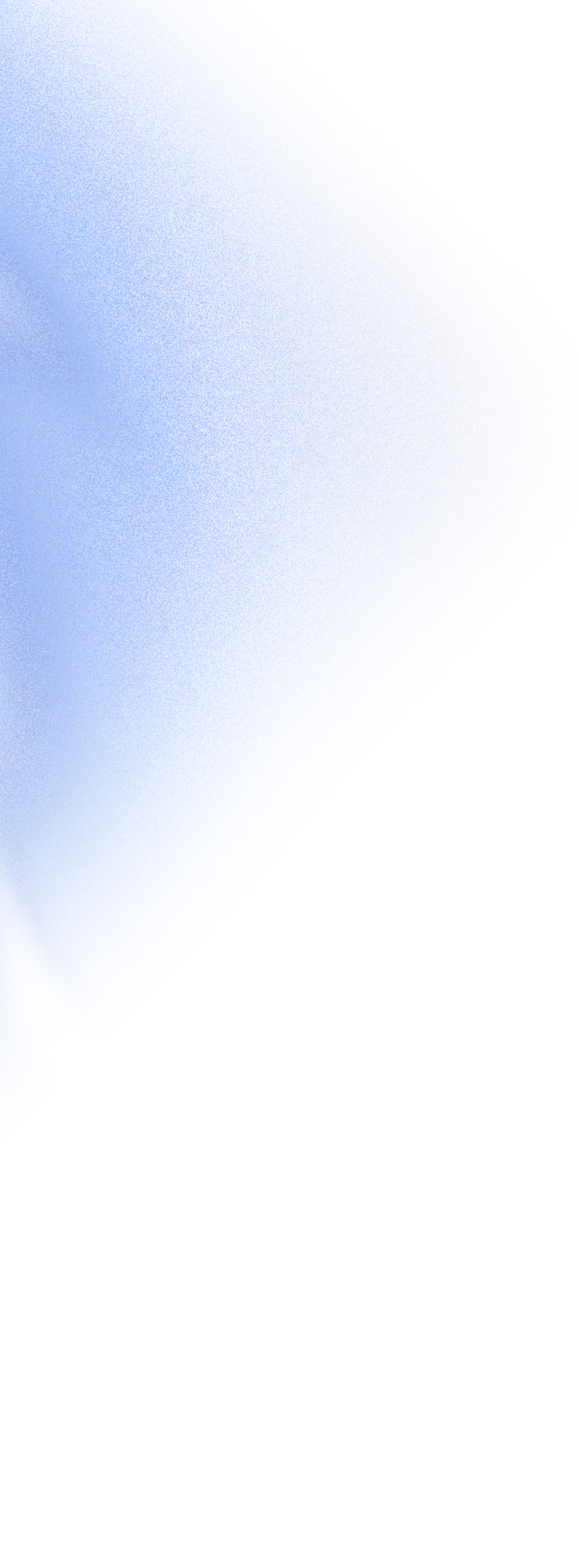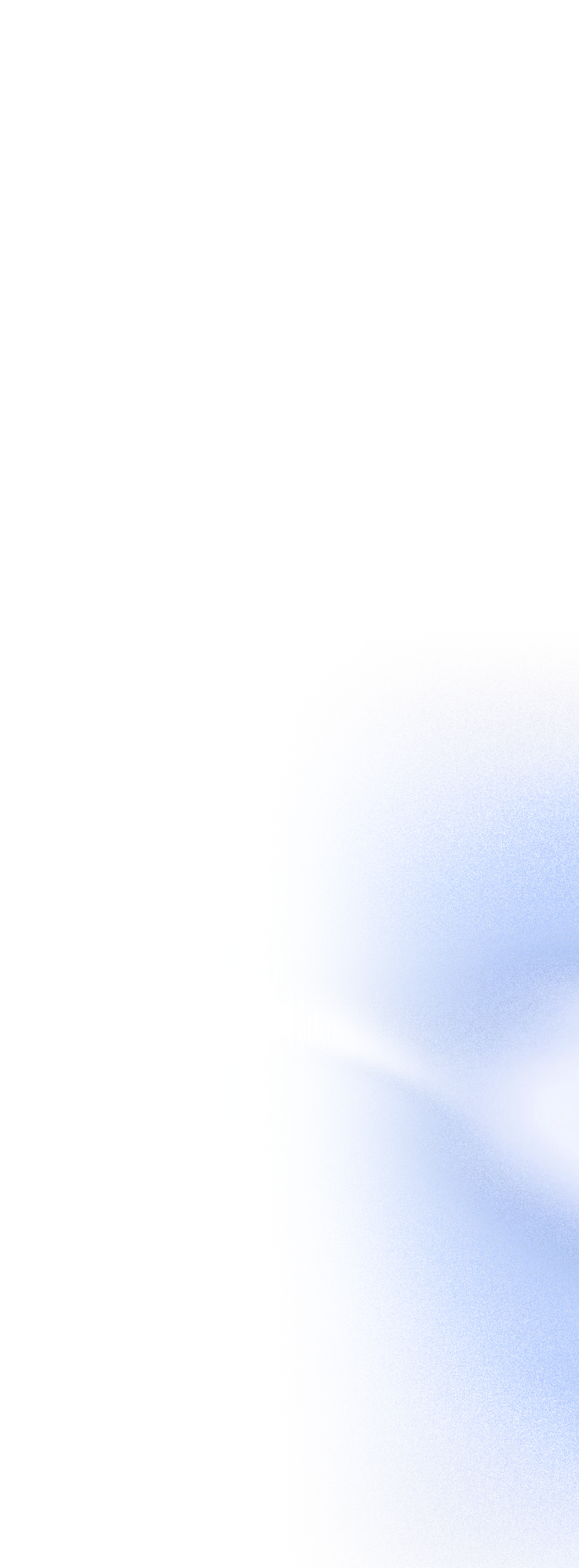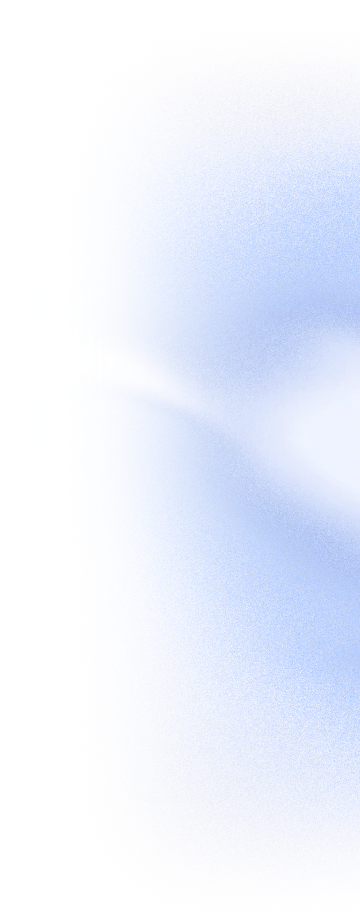次世代リーダーが抱える課題と求められる資質
日経225企業
取引実績
企業内研修
有益度
評価
導入
企業数
受講
者数
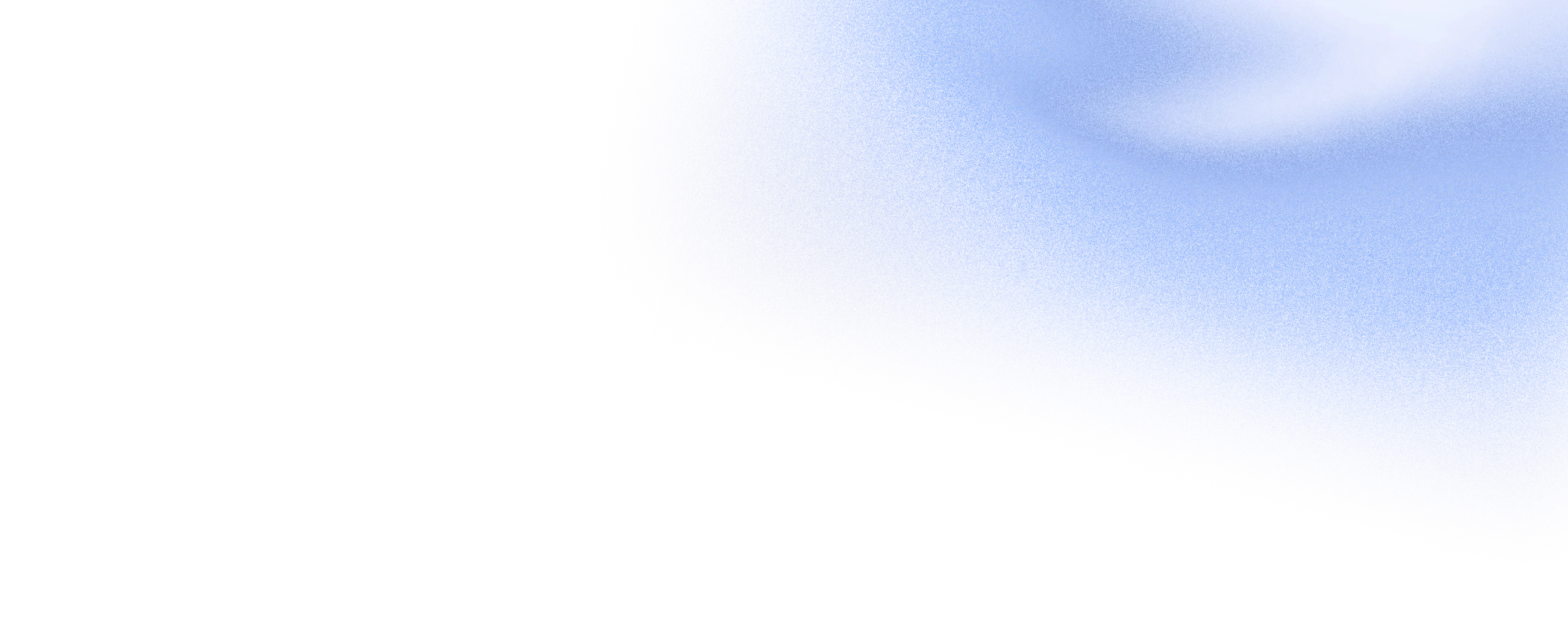
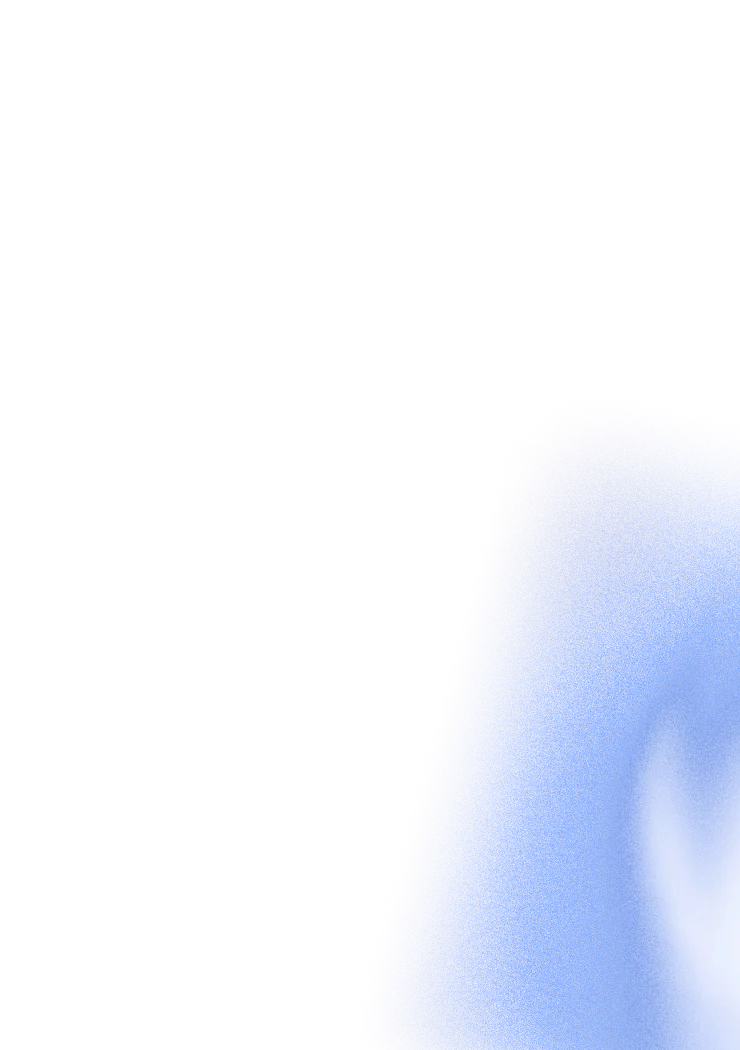
「自社の将来を担う次世代リーダーをいかに育成するか」は、多くの経営者が頭を抱える悩ましい課題です。現代ではテクノロジーの急速な進化や不確実性の高い要素によって、我々を取り巻くビジネス環境が刻一刻と変化しています。
そんな時代において企業に必要なのは、未来を見通し、迅速かつ正しい意思決定を下すリーダーの存在です。しかし現実では多くの企業で、候補者や指導する人材不足などの理由から、次世代リーダーの育成と継続的な輩出が課題となっています。
本コラムでは、グロービスの次世代リーダー研修で筆者が出会った事例をご紹介しながら、次世代リーダーが抱える課題と求められる資質について解説します。
次世代リーダーの役割
次世代リーダーとは、未来の会社をけん引し、周囲を巻き込みながら経営の意思決定をするリーダーです。現在の人材課題を解消するだけではなく、組織の存続や成長のために必要とされるため、「経営人材」と呼ばれることもあります。
次世代リーダーに求められる役割は様々ありますが、その1つに、周囲を巻き込みながら経営の意思決定をし、組織が未来に適応できるよう変革を推進することが挙げられます。市場の変化や技術の進化に柔軟に対応し、革新的なアイデアを実行に移す能力が、次世代リーダーには求められます。
次世代リーダー育成の検討にあたり重要なポイント
次世代リーダー育成は、未来の会社をけん引する有望な人材を早期に選抜し、中長期的に育成・支援する取り組みです。ある程度時間をかけて段階的に育成を行うことで、経験・スキル・マインドに長けた経営人材を輩出し、会社のより良い未来を目指します。
次世代リーダーを育成するには、まずマクロな環境の変化を踏まえ、未来の自社がどうあるべきかを考えることが求められます。次に、その実現のために「いつまでに・どのポジションで・何人のリーダーが必要か」を逆算しましょう。重要なのは自社の置かれた状況を正しく認識することです。その上で、企業の戦略実現のために組織で課題となることは何か、その課題を人材育成を通じてどのように解決するのか、を明確にすることが必要です。
次世代リーダーに求められる能力・要素とは
このような次世代リーダーの役割を担うにあたり必要となる、4つの能力・要素について紹介します。
- 経営の定石
- 考える力
- 人を巻き込む力
- 志
経営の定石
「経営の定石」とは、経営課題を解決するのに必要な知識・フレームワーク(理論)を指します。知識や理論に基づくことで、より効率的な課題の分析・解決策の立案が可能になります。また経験や勘に頼って、重要なポイントを見落としてしまうことを防ぎます。精度の高い経営判断ができるようになるには、土台となる思考力をはじめ、環境分析力や組織行動学といった経営の定石をしっかり理解・習得することが近道です。
考える力
「考える力」とは、複雑な問題の本質と原因を把握し、考えられる最善の解決策を導き出す思考力のことです。ビジネスを取り巻く環境が変化し、過去の成功パターンが通用しなくなりつつある今、企業の課題解決や新たな価値の創出には欠かせないスキルです。「考える力」を身につけるには、長い時間の中で染み付いた自分の「思考の癖」に気づき、軌道修正することが求められます。
人を巻き込む力
「人を巻き込む力」とは、周囲の人からの協力を引き出し、目標に向かって一緒に成し遂げていくために必要なコミュニケーション力の総称です。物事の前提や背景、課題などについてわかりやすく説明する力や、周囲を鼓舞し行動させる力などが含まれます。誰しも得意・不得意があるので、どんなに優秀な人でも一人でできることには限界があり、上手く他者の力を借りて協力しなければビジネスを完遂することはできません。成果を上げるには、社内外のさまざまなステークホルダーを巻き込むことが不可欠です。メンバーの力をうまく引き出すことができれば、想像以上のシナジーを生み出すことができるでしょう。
志
「志」とは、自身が何を大事にし、達成しようとしているかを明確にしたものです。経営リーダーの重要な役割のひとつは、「自らの使命感に従い、実現したい大きな絵姿を指し示すこと」です。先が見えない中でも組織全体が同じ方向に突き進むには、経営リーダー自らがスピード感を持って仮説を立て、実行・検証を繰り返しながら引っ張っていくことが不可欠です。
次世代リーダーはどのような課題を抱えているのか
企業の未来において重要な役割を果たす次世代リーダーですが、実際には先に挙げた4つの能力・要素を十分に発揮できず、課題を抱えてしまうケースが多いです。実際のグロービスの研修であった、具体的な事例を以下に示します。
10年ほど前から導入が広がった研修スタイルに、アクションラーニング(以下、AL)があります。現実の自社の課題を取り上げ、その解決策を考えることによって、人材と組織の開発を狙うことが目的です。グロービスでは、とくに次代を担うリーダー候補を対象としたALに数多く取り組んできました。
製造業X社は、「衆知を集め、世の中に独自の価値を提供し続ける」をモットーに躍進を続けてきました。グローバルに販路が拡大する一方、生産は国内拠点に大きく依存。顧客層は広がっているものの、新興国の台頭により価格の安い競合品の追い上げに苦しんでいました。
X社におけるALは、およそ6か月をかけて行われました。その前半戦のクライマックス、経営陣に提言をぶつけてアドバイスをもらう中間報告会のことです。発表者はB氏、営業を中心に20年近くのキャリアを持ちます。
「わが社のコスト構造を抜本的に改革することを提言します。国内の生産拠点を大幅に縮小し、海外に移します。同時に調達先も新しい海外生産拠点を中心にゼロベースで見直します。具体的には…」
B氏の発表が終わると、社長からいくつかの質問が投げられました。
「コストのうち、生産拠点に関連するコストは具体的に何で、いくらかかっている? それがなぜ問題といえるのか?」
「海外拠点はどこに作るつもりだ? 国内拠点より優れているという理由は?」
「結局海外への生産拠点シフトはうちのモットーである『独自の価値』に貢献するのか?」
「国内の生産拠点はいくつある? そこで働いている従業員の数は? 既存の調達先はいくつくらいある? 彼らに今回の改革をどうやって説明する? 」
「君は明日からこの生産拠点シフトプロジェクトのリーダーをやる気があるのか? 」
社長のそれらの質問を前に、B氏は言葉に詰まってしまいました。
経営課題を取り上げるALにおいて、上記の風景は珍しいものではありません。経営課題に対する着眼において、経営陣とミドルとの間に差があるのは当たり前のことです。逆にそのギャップに気付くことがこうした場の目的のひとつでもあります。上述のB氏自身も営業では歴戦のツワモノ、その実績を見込まれてこの場に集められています。そんなB氏でさえ、自分たちで調べたデータについて、社長に問われると明確に答え切れないときがあるのです。
経営陣からの質問の嵐が過ぎるのを待つかのように時が流れました。そして報告会を終え、経営陣が退出すると「ホッ」とした空気が場を支配します。私もまた「ホッ」としましたが、次の瞬間「ハッ」としました。これでいいのだろうか、と。
ALに伴走させていただく際に、参加者の皆さんに何度も聞く質問があります。
「●●さんは、どうしたいのですか? 」
この問いによって引き出したいのは、その方の持つ直感です。答える本人ですらどこから出てきたのかよくわからない問題意識や解決の方向性の表出が狙いです。
直感といっても、単なる思いつきではありません。上述のB氏にすれば、20年間の実務の積み重ねの結果であり、それらに裏打ちされた揺るぎない感覚のはずです。「実務の積み重ね」という言葉でも、軽すぎるかもしれません。次世代のリーダー候補として集められた方であれば、二度と経験したくない苦しい局面、人にはいえない痛い思い、そしてその結果として(誰にも言わないかもしれないが)誇りと矜持があるはずです。そうした経験から生まれるのは、いわばその人の仕事観といえるでしょう。
上述の直感は、こうした仕事観の中で醸成されて表出するものです。だからこそ、私はその直感に真実が宿っていると信じているのです。
経営陣に向けた提言は、この直感を言葉として紡ぎ、事実で裏付けたものだったはずです。とすれば、提言が終わっただけの段階で「ホッ」としてよいのでしょうか?
まず、経営陣からの主張に対して、面と向かって反論してほしい。退かないでほしい。さらにいうなら、退かないだけでなく、迫ってほしい。攻め側に回るのは、聞き手の経営側ではなく、主張する提言側のはずです。「これを自分達にやらせてほしい、今すぐ決めてほしい。なぜ決められない? なぜできない? これができなくてこの会社が存在する意義はあるのか?」そう、畳みかけてほしいのです。
これは、理想論ではありません。 実際の組織においては、しがらみがあってそんなこと言えるはずもないという意見もあるでしょう。ただでさえ日々の業務で忙しいのに、研修でここまで本気にやるのか? という疑問もあるでしょう。
しかしリーダー候補に期待されているのは、経営陣に本気で立ち向かう姿勢です。X社社長の「君は明日からこのプロジェクトリーダーをやる気があるのか?」と相手の覚悟を問う言葉に、その期待が端的に現れています。
正直に申し上げます。私たちの力不足もあり「次世代リーダーが経営陣に本気で立ち向かう」研修は、なかなか実現できません。では、なぜ実現できないのか? 次のパートでは、今日のリーダー候補が抱える課題とその要因について考察します。
次世代リーダーが克服すべき3つの要因
次世代リーダーの候補者となりうる多くの優秀なミドルが抱える課題、それは「反論や積極的な提案など経営陣に本気で立ち向かうことができず、意思決定の局面で立ち尽くしてしまうこと」です。数々の研修現場でそんな場面に対峙した経験から、要因を下記の3つと考えるに至りました。
- 思考の粗さ
- 当事者意識の低さ
- 可能性への信頼の弱さ
この3つの要因は、次世代リーダーに求められる資質として先に挙げた4つの能力・要素のうち「経営の定石」「考える力」「志」の欠如に由来します。(「人を巻き込む力」は実行フェーズで必要となるスキルのため、研修であるALにおいてはその不足が顕現することは多くありません。)
思考の粗さ
「思考の粗さ」とは、ビジネスや人間理解にあたって、ぼんやりと画素の粗い状態でしか考えられないことをいいます。リーダーに求められているのは、「一見ぼやっとした像を分解して具体的に考える力」、逆に「複雑な事象を統合して考える力」、そして「ある事象が何を引き起こすのか・どんな影響を与えるのかを、見えない先まで詰めて考え抜く力」です。
「思考の粗さ」の要因のひとつは、「経営の定石」「考える力」の欠如です。思考の解像度を上げるには、問題解決に必要な知識・フレームワーク(理論)を学び、問題の本質・原因を把握し、最善の解決策を考え抜くことが求められます。
経験のある領域においては、過去の蓄積で何とかなるでしょう。しかしそれを活かせない領域に足を踏み入れた途端、具体的に考えられず足踏みすることになってしまいます。たとえば前述のB氏は、コストのうち生産拠点に関わる知識が不足しており、具体的な内容まで把握しきれていませんでした。加えて、コスト削減ばかりに目が向いて、閉鎖対象となる拠点の従業員への配慮も考えきれていません。その結果、社長の問いに答えることも、納得を得ることも、巻き込むこともできませんでした。もし仮に彼の案が実行に移されていたとしたら、単なる無謀な計画として失敗していた可能性が高いでしょう。
当事者意識の低さ
「当事者意識」とは、「自分の後ろには誰もいないという自覚」です。より具体的には、「誰にも頼ることのできない環境において、自らの意思決定が組織全体に影響を与え、時には命運を分ける」と認識することです。
リーダーは、広く全体を俯瞰できる高みに自分を押し上げつづける必要があります。自らの影響範囲を見誤ると適切な判断ができず、結果として人を動かすことができなくなるためです。時間軸としては、過去から将来を踏まえ、空間軸としては、一個人や一部門の利害に留まるのではなく、組織全体や社会を見据えることが重要です。
さらに、「なぜ自分がしんがりを務めねばならないのか、務めたいと思うのか、その原点はどこにあるのか」を深く掘り下げる必要もあります。誰も頼ることのできない環境では、最後に頼れるのは自分の価値観だけです。またその価値観は、周囲の共感を得られる深みを持っていなければ人を動かすことはできません。
すなわち当事者意識の低さは、「人を巻き込む力」「志」の欠如に起因します。人を巻き込む力がなければ、自らの影響範囲を見誤り適切な判断ができなくなってしまいます。また「志」、つまり「明確な意志」を持ち「自分の使命」がなければ、しんがりを務める重圧に耐えきれません。
事例で挙げたB氏は、生産拠点の移転に伴う関係者へのコミュニケーションをどう行うかまで目配りがおよびませんでした。たとえそこに気づいたとしても、自分が責任者として閉鎖拠点の従業員に説明しなくてはならないという意識を持てなかったでしょう。自分が最後だという自覚が足りず、国内生産拠点閉鎖の困難さ・影響範囲までを見渡せる高い視座を持ってなかったといえます。
可能性への信頼の弱さ
「可能性への信頼の弱さ」とは、「諦め」です。動詞表現は「諦めない」。否定形ではなく、肯定形に言い換えると「やればできると(可能性を)信じる」となります。これまで多くの方と議論する中で、この言い方はなかなか理解されるのが難しいと感じています。否定形「諦めない」はまだ理解されやすい一方、肯定形「やればできる」は誤解を生みやすい表現です。具体的には「無謀と何が違うのか?」「精神論ではないか?」という声が寄せられます。もう一歩踏み込んで考えてみましょう。
「やれば」という言葉は一見軽く聞こえます。だからこそ上記のような問いが寄せられます。しかし、ここでいう「やれば」は軽く、そして重いのです。まず、何事もやってみないとわからないという意味で、踏み出すことのハードルを下げることが大事です。だから軽くもあります。しかし、同時に重いのです。ハッキリとビジネス上の可能性を考え抜く。厳しい現実を直視したうえで、考えられるありとあらゆる手を打つ。それは一回で済むものではありません。何度壁にぶち当たっても、現実を直視しながらその時点の最善の方法を考え抜き、「できる」までやり抜く。つまり、「やるべきことをやり抜けばできる」ということです。松下幸之助氏の次の言葉を信じているともいえるでしょう。
「失敗したところでやめてしまうから失敗になる。成功するところまで続ければ、それは成功になる」
しかし「言うは易し、行うは難し」です。研修現場でお会いするビジネスパーソン、とくに次代を担う方々は、僭越ながら”ハッキリと考えられる”方が多いようです。しかし先が見えてしまうがゆえに、まず一歩踏み出すこと、つまり「軽く」やってみることを躊躇してしまうのです。またせっかく一歩踏み出したとしても、立ちはだかる障害の「重さ」ゆえに途中で挫けてしまい、やり抜けません。やってみる「軽さ」とやり抜く「重さ」、この一見矛盾する両者を兼ね備えることは簡単ではありません。しかしこの矛盾を選び取ることこそ、「やればできる」という可能性を信頼することに他ならないと思います。
「可能性への信頼の弱さ」、つまり困難に直面したときにやり抜けずに諦めてしまうこともまた、「志」の低さから生じる問題です。志、すなわち「自分が成し遂げたいと強く願う目標や理念」がなければ、「できない」「やらない」と考えやすくなります。逆に志を持つことで、それに向かって進むべき道のりが明確になり、途中での困難や障害を乗り越えることができます。志は単なる夢や希望とは異なり、具体的な行動指針や信念を伴うため、自分自身を支える強力な柱となります。
先ほど挙げたB氏の提言は、自社のモットーである「独自の価値」を貫くために何をすべきかを十分に検討したものでしょうか。なぜ生産拠点の海外移転を決めたのでしょうか。仮に、「独自の価値」を貫くためには国内に生産拠点を持つことが大事だとしましょう。低価格の競合品への対処も同様に大事です。しかし、この「国内生産拠点」と「安価な競合品への対処」の両立は簡単ではありません。ただ、この困難に直面して安易に「できない」と思っていないか。社長は、そう問うているのです。
次世代リーダーの意思決定に必要なサイクル
「思考の粗さ」「当事者意識の低さ」「可能性への信頼の弱さ」の三者は、本来相互につながっています。
人間は本来、何かを成し遂げて成長したいという願いを持っています。その願望をベースに、まずやってみる。壁にぶつかったら、乗り越えるために考え抜き、試行錯誤する。なんとか成功すると、やればできるんだと自信がつく。そしてまた新たに自らチャレンジする。この繰り返しこそが、「緻密なハッキリとした思考」「高い当事者意識」「可能性への強い信頼」を形作り、互いを鍛え強化し、好循環を生み出していくのです。
しかし現在、企業組織の中で次代を担うリーダーたちが立ち尽くしています。なぜなら、彼らが本来持つべきグッドサイクルが途切れてしまっているからです。この環を途切れさせたものは何でしょうか。外部環境の変化や内部の施策群、それらの歴史的な経緯も要因として考えられそうです。思いつくだけでも次々と考えられる要因の多さと複雑さに混乱しかねません。少なくとも言えるのは、彼らだけの責任ではないということです。
このような現実を踏まえて、人材育成担当者であるみなさんは、何を考え、どのような行動を取りますか?ぜひ、考えてみてください。
まとめ
本コラムでは、グロービスの次世代リーダー研修で筆者が出会った事例をご紹介しながら、次世代リーダーに求められる4つの能力・要素と、3つの課題をご紹介しました。
次世代リーダーに求められる4つの能力・要素
- 経営の定石
- 考える力
- 人を巻き込む力
- 志
次世代リーダーが直面する課題
- 経営陣に本気で立ち向かうことができず、意思決定の局面で立ち尽くしてしまうこと
課題の要因
- 思考の粗さ
- 当事者意識の低さ
- 可能性への信頼の弱さ
課題を克服するため、次世代リーダーに求められる4つの能力・要素を身に着けてもらうことは、今日の企業にとって重要な課題のひとつです。次世代リーダー育成は継続的な取り組みが必要になるため、外部パートナーから適切な支援を受けることも有効な手段でしょう。
グロービスは数多くの企業に次世代リーダー育成の研修を提供しており、次世代リーダーに必要な4つの能力・要素「経営の定石」「考える力」「人を巻き込む力」「志」を育成するノウハウを持っています。次世代リーダー育成にお悩みの場合は、お気軽にお問い合わせください。
※文中の所属・役職名は原稿作成当時のものです。