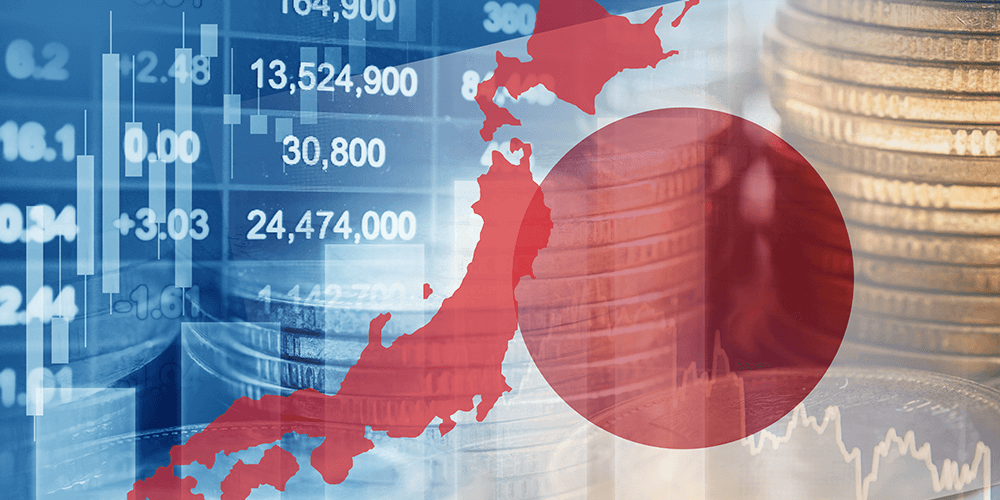- HRBP・FP&A
事業と人をつなぐ、HRBPの役割と活躍のポイント
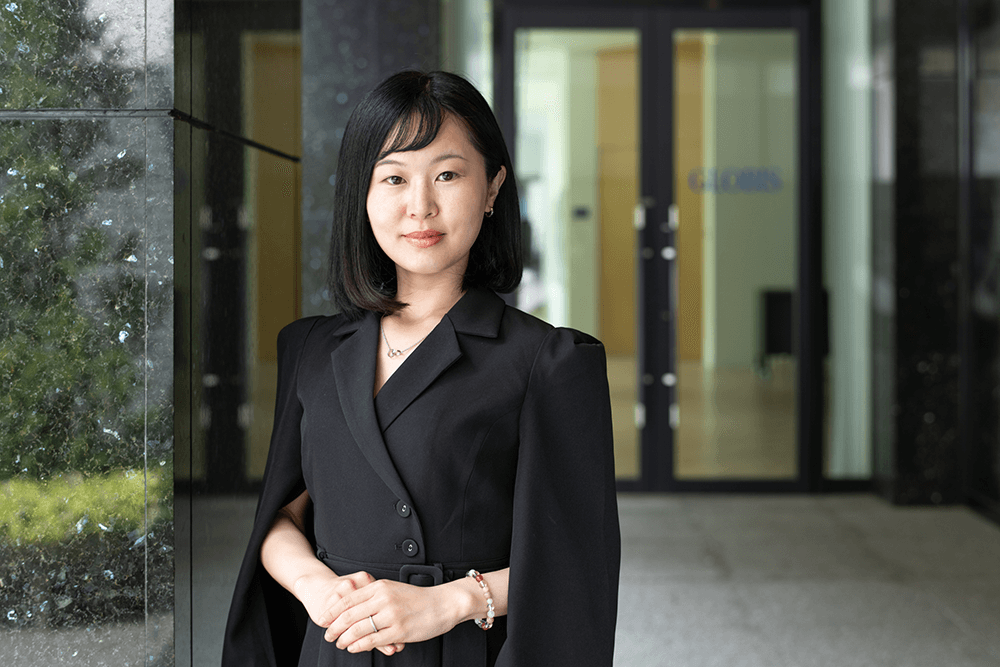
近年、多くの企業で「HRビジネスパートナー(HRBP)」の導入が進んでいます。
その背景にあるのは、経営環境の変化に伴う“人と組織”のあり方の再定義です。市場の変化が激しく、戦略のアップデートが常態化するなかで、企業が競争力を維持・強化していくには、事業戦略と組織戦略を連動させ、価値を創出していくことが不可欠です。そうした中で登場したのがHRBPです。HRBPは、事業と組織をつなぐ“橋渡し役”として、従来の人事機能とは一線を画し、ビジネスの成果に貢献する経営パートナーとして、注目を集めています。
本コラムでは、HRBPという役割の本質に立ち返りながら、その実践に求められる資質や、HRBPが力を発揮できる組織のあり方について紐解いていきます。
(本コラムは、「企業と人材」2025年6月号の連載記事を一部編集のうえ、掲載しています)
HRBPの役割
「あなたの人事としてのやりがいは何ですか?」。そう尋ねると、「社員の成長に関われること」、「組織をよりよくできること」多くの方がこんな言葉を口にします。“誰かや組織のために”という貢献意識を強く持っている方が、人事の方には多いのではないでしょうか。
そんな思いを持つ方に届けたいのが、人や組織への貢献をより大きなスケールで実現していく、「HRビジネスパートナー(HRBP)」という存在です。
HRBPとは企業が“勝てるチーム”として進んでいくために、人と組織の観点から事業戦略の実行を支える役割を担います。これから事業がどのように勝ちにいくのかを理解し、それに向けて最適な組織を設計する。さらに、そこに関わる一人ひとりが能力を最大限発揮できる環境をつくることが求められます。
また、”勝てるチーム”を創るには仕組みづくりだけでは不十分です。関わる一人ひとりが自律的に動き、力を存分に発揮できる状態をつくることも、HRBPの重要な役割の一つです。つまりHRBPは、組織として成果を出しながら、関わる全ての人が誇りと充実感を持って働ける、そうした未来を創っていく存在です。
一方で、HRBPがこれらの役割を果たすことは決して容易ではありません。関わるステークホルダーは多岐にわたり、必要なスキルも人事の専門性にとどまりません。時には、経営と現場の間に立ち、調整することが求められます。
それでもなお、HRBPが力を発揮し、成果を生み出している企業には、ある共通点があります。今回は、HRBPに必要な「個人の資質」と、HRBPが活躍できる「組織のあり方」の2つの視点から、HRBPが機能する条件を探っていきます。
HRBPに求められる資質
はじめに、私がこれまで人材育成や組織開発の現場に携わった経験をもとに、実際にHRBPとして活躍している人に共通する3つの資質について解説していきます。
1. 共創型のリーダーシップ
HRBPは、事業部や経営層の“パートナー”となることを期待される存在ですが、その関係性は肩書きだけで成立するものではありません。自らの行動によって信頼を築き、相手から「ともに考えたい」「ともに進みたい」と思ってもらうことが必要です。
そうした信頼を獲得するために欠かせないのが、“共創型のリーダーシップ”です。ここでいう“共創型のリーダーシップ”とは、不確実な状況でも「自分はこうありたい」「こう進めたい」という意志を持ち、関係者を巻き込んで未来を描く力のことを指します。
HRBPは戦略実行を担う“当事者”であり、単なる支援者ではありません。正解のない問いに向き合い、異なる立場をつなぎながら意思決定を進めていくには、自分の言葉で語り、周囲を巻き込み未来を描く姿勢が求められます。人や組織に誠実に向き合い続ける胆力こそ、HRBPのリーダーシップの本質です。
2. バウンダリースパナー力
HRBPが、異なる立場や背景を持つ人同士をつなぎ、共通の目的に向けて組織を前進させるには、「バウンダリースパナー力」が欠かせません。
HRBPに必要な資質としてよく挙げられるのが「コミュニケーション力」ですが、コミュニケーション力が「対話する力」だとすれば、バウンダリースパナー力とは、そこから更に一歩踏み込んだ「異なる立場の人の考え方や価値観の違いを汲み取り、共通のゴールへと導く力」です。
例えば、経営の言葉が現場には響かないとき、また現場のリアルが経営に伝わりきらないとき。経営と現場、事業と人事、それぞれが見ている風景や、使う言葉、重視するポイントは異なります。HRBPはその間に立ち、両者の意図や背景を丁寧にすくい上げながら、同じゴールに向かって動き出せるように橋渡しをします。このような異なる立場をつなぎ導く力が、HRBPに必要な資質のひとつです。
3. 事業や組織・人に対する熱意
HRBPにとって何より大切なのは、「この事業をもっと成長させたい」「組織や人の可能性を開花させたい」といった、自分自身の意思や思いです。
HRBPの仕事には、明確な答えがない場面が多くあります。組織の方向性が定まりきっていない中で部門長とともに未来を描く、立場の異なる関係者と議論を重ね意思決定をしていく。そこでは、「事業と組織のより良い未来をつくりたい」「向き合う人の力を引き出し、後押ししたい」というような個人としての強い意思や思いが、判断と行動の大きな支えになります。
“意思や思い”という言葉は少し抽象的に聞こえるかもしれませんが、実際には、そうした周囲を思う気持ちや信念こそが、人の共感や行動を引き出す原動力になるのではないでしょうか。
HRBPが活躍できる組織のあり方
HRBPがその力を最大限に発揮するには、個人の資質や努力だけでなく、それを支える組織の土台が必要です。ここからは、HRBPの活躍を支える組織のあり方について、3つのポイントをご紹介します。
1.HRBPが戦略実行に専念できる体制の整備
HRBPが、本来の役割である「事業戦略の実行パートナー」として力を発揮するには、組織としての体制整備が欠かせません。
まず必要なのは、人事部門全体における役割分担です。人事が担う日々のオペレーション業務(労務対応や給与計算等)と、戦略的な人材・組織課題に向き合うHRBPの機能を分離し、専念できる状態をつくる必要があります。
例えば、CoE(Center of Excellence)、HRSS(Human Resource Shared Service)など他の人事機能との関係性を整理し、「誰が誰にどんな価値を提供するのか」を明確にすることで、HRBPが担うべき役割に専念できる体制が整います。
加えて、HRBPがどの事業や組織に紐づくのかを明確にしておくことも重要です。事業戦略や目標の切り分けが明確な事業部ごとにHRBPを配置し、戦略実行の一翼を担うパートナーとして位置づけることが、HRBP活躍の鍵となります。
2. 適所適材を支える「人を見る力」と「データ基盤」
HRBPは、組織の一人ひとりに目を向け、最適な環境を考える存在でもあります。そこで欠かせないのは、従業員のスキルや志向性、活躍条件を把握し見極める「人を見る力」です。
何千人、何万人といる組織の中で、一人ひとりの能力や可能性に気づくためには、タレントマネジメントデータや人材アセスメントといった「可視化された情報」が有効な手がかりとなります。ただし、こうしたデータだけに依存するのではなく、現場との対話や観察から得られる定性的な情報も同様に重要です。このようなデータの整備と現場接点の機会が揃うことでHRBPは適所適材を実現する力を存分に発揮できます。
「人を見る力」と「可視化された情報」の両輪があることで、現場の信頼を得ながら、最適な人材戦略を描くことができるのです。
3. 人事部門全体の“自己定義”を変える
HRBPが経営や事業部とともに未来を描こうとしても、人事部門が「制度を運用する役割」にとどまっていては、HRBPの取り組みが孤立してしまいます。人事部門全体が「経営と未来をつくる存在である」という意識を持つことが、HRBPの活躍を支える土台となります。
そして、人事部門全体の意識が変わるだけでなく、それを体現する個々の人材を育てていくことも、組織としての実行力につながります。成果を生み出すHRBPを人事部門から輩出していくためには、Off-JT等による知識・スキルの強化はもちろん、事業戦略・組織課題・人事戦略をつなぐ思考力と構造理解を育てるための学習機会を設計することが効果的です。
HRBPは、事業と人と組織、その間に立ち、未来に向けた変革を推進する存在です。同時に、HRBPの働きかけは、組織だけでなく個々のキャリアや可能性の開花にも直結します。一人ひとりの力を引き出すことが、結果として組織の総合力を最大化し、文化を変えていくことにもつながっていきます。 葛藤や難しさに向き合い、試行錯誤を重ね、一歩ずつ前に進む。そのHRBPの挑戦こそが、事業と人を動かし、組織の未来を切り拓いていくと私は考えます。