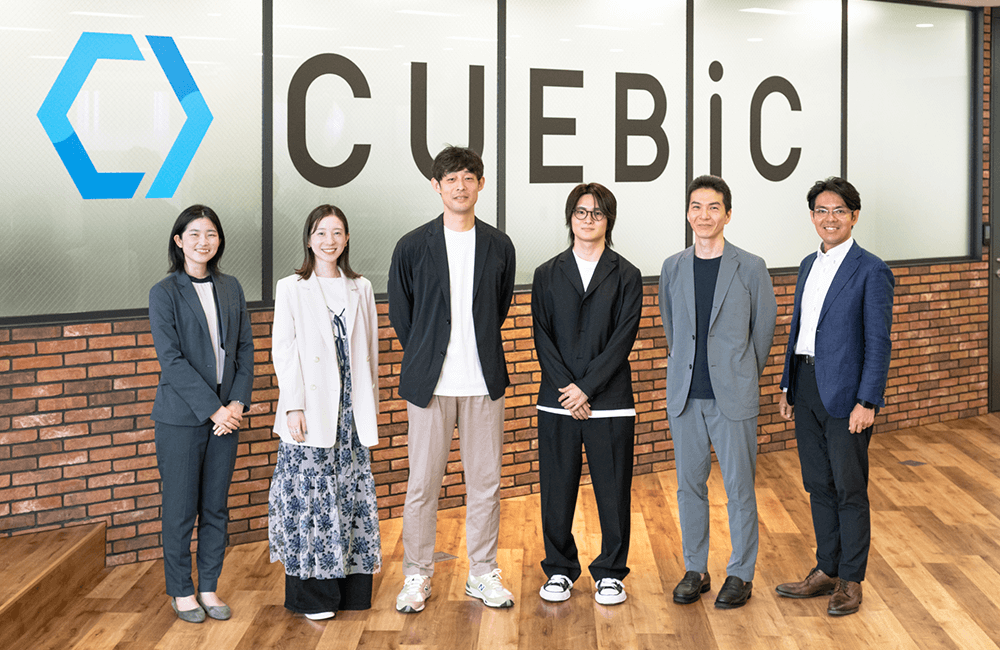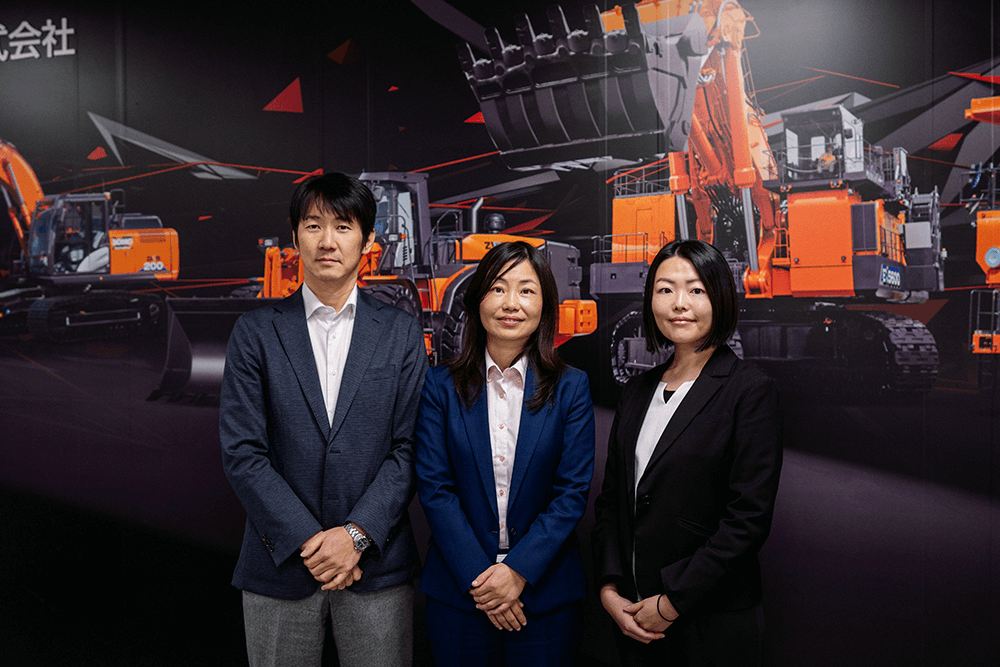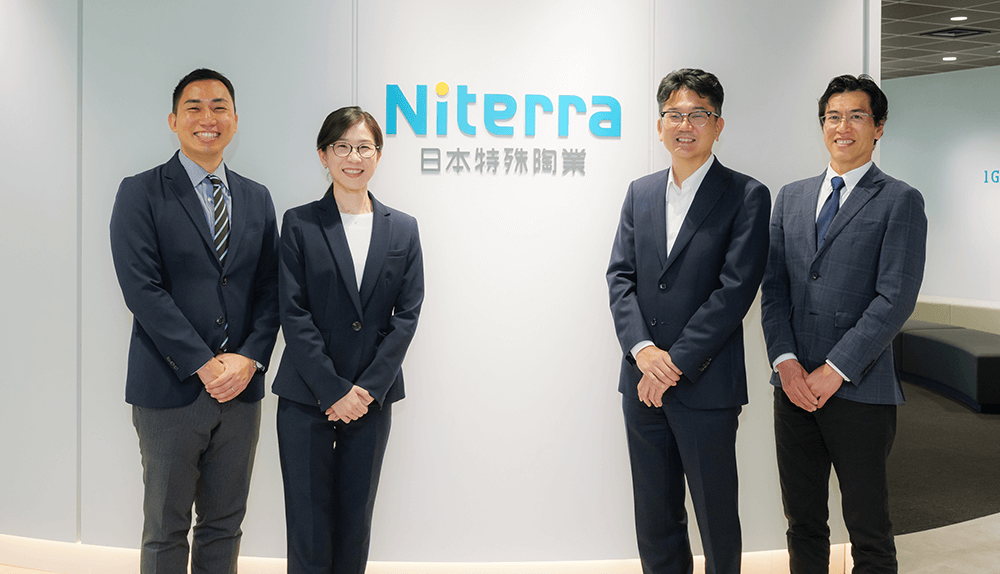- グローバル・D&I
- 経営チームの変革
「自分たちの手で未来を創る」―参加者の当事者意識に火をつけた日清製粉グループのGlobal Forumとは

日本企業が事業のグローバル化を進めるうえでは、本社と各地域、各国のグループ会社とが一丸となって経営に取り組んでいく必要があります。しかし、国や言語、事業の異なる多様な人材が共通認識を持ってグループ全体の経営課題解決に取り組むには、単なる方針共有や交流に留まらない、グローバル経営を支えるプラットフォームが欠かせません。
株式会社日清製粉グループ本社様は、グロービスと共同でグローバル経営幹部向け育成プログラム「Global Forum」(以下、グローバルフォーラム)を刷新。今回は、既存のプログラムをリニューアルするに至った経緯や、企画・運営における工夫、その後の組織における変化について、同社の企画本部 GS(国際)兼GS(海外事業開発)付参与の大内孝雄様、同主査の橋本康弘様、同主査の青山惇様、波多野真実様にお話を伺いました。(役職はインタビュー当時)
はじめに:本プロジェクトの概要
日清製粉グループは、120年以上にわたり日本の「食のインフラ」を担ってきた国内トップの製粉企業グループです。現在では、製粉事業を中核に、加工食品、酵母・バイオ、健康食品、中食・惣菜、産業用資材のメッシュクロスなど幅広く事業を展開。海外では、アジア、北米、オセアニアを中心とした11か国に22の海外子会社と35の製造拠点を有し、海外売上は約3割、外国人従業員は全体の約4割と、グローバルに事業を行っています。
同社では、グローバル事業のさらなる成長に欠かせないグローバル経営のためのプラットフォーム構築を目的として、シンガポールで4日間のグローバルフォーラムを開催。海外子会社経営層が一堂に会し、日清製粉グループの成長に向けた経営課題や今後のアクションについて議論しました。
インタビュー:プロジェクト実施の経緯
全参加者がコミットできる、共通のアジェンダとゴール設定が必要
大内さん:当社の海外事業はこの10年ほどで急拡大しています。2012年にアメリカ、2013年にはニュージーランドの製粉企業を買収。2019年には、オセアニア最大であるオーストラリアの製粉企業の買収を行いました。 今後さらなるグローバル成長を実現するためには、本社と海外子会社間の連携(タテの連携)に加え、海外子会社同士の横のつながり(ヨコの連携)も強化していくことが不可欠です。そこで、海外子会社経営リーダーを集めてグローバルフォーラムを再開するように、との指示が経営トップからありました。
以前のグローバルフォーラムは各国の経営リーダーを集めた会合で、2014年から2019年まで毎年開催していましたが、コロナ禍により2020年にオンライン開催した後はストップしていました。私自身も以前は海外子会社におりましたので、過去6回ほど参加しています。海外子会社のトップが集まり、それぞれの事業の話を聞いたり、ネットワーキングしたりする機会は当時としては画期的なものでした。ただ、回を重ねるうちに同じ場に集うこと自体が目的となっており、開催する意義が薄れてきているのではと感じていました。
当社にはいろいろなタイプの海外子会社があります。例えば、製造から販売まで行っている現地完結型の事業もあれば、日本市場向け製造拠点としての会社や販売オフィスのみの会社もある。そのような状況なので、海外子会社の経営リーダーが集まっているといっても、それぞれのバックグラウンドやビジネスモデル、マネジメントスタイルも異なり、経営課題も全く異なります。したがって、以前と同じコンセプトでグローバルフォーラムを再開しても意味が無い。グループ全体でグローバル成長を加速させていくためのプログラムにするために、全参加者がコミットできるような共通のアジェンダとゴール設定が必要だと考えていました。
「グローバル人事ガバナンスの基礎となるプラットフォーム」を目指す
大内さん:海外の経営リーダーの共通テーマとして考えられるものはいくつかありますが、海外事業が急拡大する中、喫緊の課題となっているのが、グローバル人事ガバナンスの強化です。例えば、海外子会社のトップ人事については本社がある程度関与しているものの、その下のマネジャー層や後継者の採用・育成については現地経営者に任せっきりとなっているなど、海外事業における仕組みづくりは十分ではありません。海外で経営者として活躍できる日本人人材も限られています。海外事業が急拡大する中で、今後は日本人だけでなく、海外人材も含めた後継者人材の育成や人材要件の定義、採用ガイドラインの設定など、グローバル人事の仕組みを早急に整えていく必要に迫られていました。
といっても、グローバル人事の仕組みはこうあるべき、という正解があるわけではなく、それぞれの会社の状況に合わせた仕組みを、海外事業を行っている当事者がつくっていくしかありません。そこで、グローバル経営トップが集まるこのグローバルフォーラムを活用しよう、と考えました。グローバルフォーラムを単なる研修やネットワーキングの場にするのではなく、今後のグローバル人事ガバナンスの検討基盤となるプラットフォームにする、というのが我々の狙いでした。
開催にあたっては、海外のグループ会社からできるだけ多くの方に参加してもらえるよう、事前から丁寧に働きかけました。忙しい中、シンガポールに4日間も滞在しなければならない、というのは、参加者にとっては相当負荷がかかります。そのうえ、以前のグローバルフォーラムと比べて事前課題も多かったため、当初は快い反応だけではありませんでした。そこで事務局から参加者一人ひとりに対して直接電話をしたり、メールを送ったりして、事務局として今回のグローバルフォーラムをどう位置付けているのか、目的や意義などについて丁寧に説明し、理解を求めました。
キーマンとなる海外子会社トップには企画段階から相談し、「どういう形だったら参加したいか」意見をもらうようにしました。加えて、日頃からすべての海外子会社を訪問していた経験も役立ちました。各社の状況や課題を地道にしっかりとヒアリングしていたからこそ、これだったらみんなが共通して取り組めるのではないかというテーマが見えてきたと感じています。
プロジェクトの主な内容
本音を引き出し、コミットメントを高めるファシリテーション
橋本さん:新しいグローバルフォーラムを企画するうえで、強くこだわっていたことがあります。それは、ただ一方的に講義を聴くだけのスタイルではなく、参加者同士がインタラクティブに議論し、そこで生まれた気づきを大切にしながら学びあえるような場にしてほしい、ということでした。グローバルフォーラムをグローバルマネジメントのプラットフォーム構築の場とするためには、多様なバックグラウンドを持つ参加者を巻き込み、主体的に関わってもらう必要があります。そのためには、英語力はもちろん、高いファシリテーション能力が必要です。グロービスには以前から国内の人材育成プログラムを組んでいただいており、ファシリテーションには定評があったので、参加者を議論に巻き込み、コミットメントを高めていくようなファシリテーションを期待してご依頼しました。
青山さん:海外子会社トップの方々が実際にどんなことを考えているのか、本音はなかなか見えづらいところがあります。ですが、今回のグローバルフォーラムでは、インタラクティブなやりとりの中で、参加者が普段考えていることがどんどん出てきているように感じました。ファシリテーターの堤さんは、語り口はとても情熱的なのですが、誰もおいて行かず、うまく参加者の意見を引き出すファシリテーションをなさっていたので、皆さんも話しやすい雰囲気になっていたように思います。
フォーラムで用いたケーススタディについても、何か学びを得るためだけではなく、参加者同士でより議論を深めるためにどのようなケースが相応しいのか、という基準で選定していただきました。本社と海外子会社間のコミュニケーションのあり方、販売の現地化の進め方など、今まさに参加者が直面している課題に近いケースをご用意いただいたので、それぞれがリアリティを共有しあい、白熱した議論になりました。単なる学びだけに留まらず、ディスカッションの呼び水になるようなケーススタディでした。
また、こういったディスカッションでは、発言する人としない人に分かれてしまいがちです。特に今回はすべて英語で行ったということもあり、普段あまり英語を使わない参加者が英語での議論に効果的に参加できるのか、少し心配でした。しかし、ファシリテーターの堤さんが上手くアイスブレークを行ってくださり、全員の発言を的確に引き出してくださいました。4日間の最後には、全員が自信を持って発言するようになっていたことが非常に印象に残っています。
日清製粉グループらしさを再確認した「社史セッション」
大内さん:今回のグローバルフォーラムでは、事前課題として、日清製粉グループとはどのような会社なのか、創業の理念とはどのようなものなのかを伝える動画を観てもらい、「日清製粉グループらしさとはなにか」について考えるセッションをメインテーマとしました。
当初はマーケティング講座など研修要素の強い内容を考えていたのですが、グロービスと「グローバルフォーラムをどのような場にするべきか」という議論を何度も重ねるうち、「グローバルフォーラムをグローバル経営のためのプラットフォーム構築の場と位置付けるのであれば、今一度、日清製粉グループの社是・企業理念などを見つめ直し、日清製粉グループの本質と組織的強みを再確認するところから始めるべきだ」という結論に至ったのです。
もともと、国内従業員向けには日清製粉グループの歴史を学ぶ「社史セッション」という教育プログラムがあるのですが、それは日本語版のみであったため、今回、グロービスと協力して、海外子会社向けに英語版の動画を作成しました。海外の従業員に対してはこれまでも、日清製粉グループの企業理念や歴史について機会を捉えて都度説明してはいたのですが、やはり断片的な説明だけではしっかりとしたイメージを持ちづらかったのではと思っています。今回、動画としてひとつにまとめたことで、日清製粉グループはどのような理念のもとに創業されどのように発展を遂げてきたのか、経営課題に直面したときにどのように意思決定し挑戦を乗り越えてきたのかなど、当社が創業以来大切にしている価値観と企業文化を伝えることができたように思います。
橋本さん:セッション中、多くの参加者が社是である「信を万事の本と為す」に言及し、「トラストを大切にしていきたい」と自分に引きつけて語っていました。やはりこの社是はグループとしての求心力になるものだと改めて感じます。それと同時に、私の立場としてはこのような会社として大切にしている価値観を、本社の立場からグループ全体に発信していきたいと考えています。
大内さん:この動画は非常に好評で、参加者の多くが「この動画をぜひ従業員たちに見せたい」と口にしていました。そこで、海外子会社の社内研修やタウンホールミーティングなどで多くの従業員に見てもらうことを想定し、内容をより充実させるべく、グローバルフォーラムの参加者とともに動画をブラッシュアップしているところです。事務局と参加者という関係性を超えて「一緒にブラッシュアップしていきましょう」という取り組みができていることは、非常に良い流れだと感じています。
プロジェクトの成果
「グローバル成長は自分たちの手で創る」というモメンタムを高めた
大内さん:今回のグローバルフォーラムでは、参加者が「日清製粉グループのグローバルビジネスは自分たちで考えて創り上げていくのだ」というモメンタムを自然に感じられるような場づくりを意識しました。一方通行の研修ではなく、全員参加型でそれぞれのリアリティを共有しあい、自身の経営のあり方やリーダーシップを振り返りつつ、組織としての強みや価値観、「日清製粉グループらしさ」を再確認させること。それだけでなく、議論を通じて見えてきた課題や問題意識を、日清製粉グループとしてどうしていくのか、自分たちでオーナーシップを持って次のアクションを起こしていくような機運を高めること。4日間が終わり、まさにそれができた、という達成感がありました。
波多野さん:驚いたのは、参加者のマインドセットの変化です。初日には「人は自分自身の責任で成長するべきだ。会社が人材育成にコストをかける意味がわからない」といった発言をなさっていた方が、最終日には「これからは人材育成に力を入れていくべきだ」とおっしゃっていました。これは最も顕著な例ではありますが、それぞれの参加者の意識が大きく変わり、新たな気づきを得ることができた4日間だったのではないかと思います。
青山さん:これまでどうしても組織上、事業会社間に壁があったのですが、今回のグローバルフォーラムを経て、事業会社の壁を越えて連携していこう、コミュニケーションをしていこう、という機運が高まったように思います。事業の壁を越えた取り組みによって、グループが一体になってビジネスができるようになっていってほしいと思っています。
大内さん:事務局として一番嬉しかったのは、フォーラム最終日に「次回のグローバルフォーラムでは、人材マネジメントの強化をテーマにやっていくべきだ」という話が、参加者の中から自発的に出てきたことです。我々としても「重要性から考えて、次回のテーマは人材マネジメントとするべきだろう」という考えはあったものの、それを押し付けるようなことはしたくないと思っていました。そのような誘導をしなかったにも関わらず、4日間を終えた時に、参加者の考えがその方向で一致したというのはとても印象的でした。
今回のグローバルフォーラムについては、準備が肝だったと感じています。グロービスには、準備段階から実施までしっかりサポートしていただきました。開催中の4日間も毎日一緒に振り返りをしながら、参加者の状態や進み具合に応じて「明日はこんなワークを追加しましょう」などと軌道修正してくださり、とても細やかに対応いただきました。今後も国内の人材育成プログラムと整合性をとって進めて行きたいと考えていますので、その部分でも引き続きお力添え願いたいと思います。
今後の展望
日清製粉グループのグローバル成長を促進するサイクルを創る
大内さん:今回のグローバルフォーラムを起点として、次世代グローバルリーダー向けの育成プログラムを立ち上げることを考えています。今年の秋には海外子会社の次世代リーダー層を集めた「Global Forum for Next Generations」を企画しています。この次世代グローバルリーダー育成のプログラムをグローバルフォーラムと連動させることで、日清製粉グループのグローバル成長を促進するサイクルを創っていきたいと考えています。
また、次回のグローバルフォーラムでは、参加者からの声も多かったグローバル人事のあり方をテーマに議論を進めていく予定です。海外事業を発展させていくにはグローバル経営体制の強化が鍵となりますが、人や組織を変えるということは一朝一夕にはできませんし、各社各様のやり方があります。日清製粉グループにとって何が正解なのかはまだ分かりませんが、グローバル事業の発展のためには、実際にグローバル経営を担っているリーダーの知見を結集し、力を合わせて地道に進めていくことが欠かせません。グローバルフォーラムが、今後の日清製粉グループのグローバル成長の布石となれば、と思っています。


事務局の皆さまからグローバルフォーラムの意義や、そこに込められた強い想いを伺う中で、「この場をいかにして真に意味あるものにできるのか」と、私自身も深く問い直す機会となりました。
本フォーラムが日清製粉グループ全体を結び、グローバル事業推進に向けた課題と方向性を共有する「プラットフォーム」として機能したこと、そしてその一端を担えたことを、非常に嬉しく思います。今後も、日清製粉グループのグローバル成長に寄与する場を創り出せるよう、全力で伴走してまいります。


グローバルフォーラムは、単なる研修の場ではありません。世界中のグループ企業のトップマネジメントが集い、各社の置かれた状況や課題について共有するとともに、解決策を議論します。さらに、日清製粉グループとはどういう会社なのか?どういう歴史を辿り、何を大切にする会社なのか?についての共通理解を醸成します。
参加者はリアリティあふれる議論から、日々のマネジメントに活かせる示唆を得るだけでなく、日清製粉グループのリーダーとしての意思決定や行動の拠り所とすべきものは何か、について改めて考えるきっかけになります。また、主催する本社サイドにとっては、海外の経営の実情や、各社のトップマネジメントの課題意識を掴む場となっています。
このようにグローバルフォーラムは、日清製粉グループ全体のグローバル経営を進化させていく、経営としての重要なプラットフォームといえます。多くの苦労もあると思いますが、このような場を企画・実行していく大内様・橋本様・青山様・波多野様の行動力には心から敬服します。そして我々自身、今後ともパートナーとして価値発揮できるよう成長し、この取り組みを支えていきたいと思います。
弊社の担当者がいつでもお待ちしております。