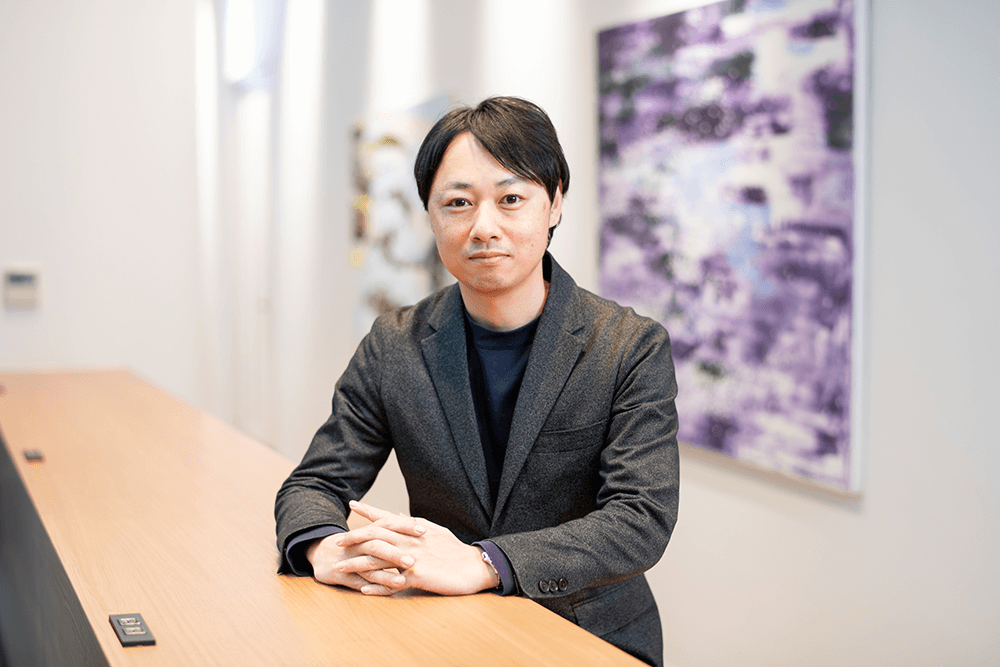- DXの実現
DX企業に向けたフルモデルチェンジ

1988年に日本のICT企業の雄である富士通に入社、金融システムSEとしてキャリアをスタートした時田隆仁さんは、金融システム事業本部長、グローバルデリバリーグループ長、執行役員副社長などを経て2019年6月、代表取締役社長に就任しました。就任直後から大規模な企業変革に着手し、従来のIT企業からDX企業への転換を目指し、パーパスの策定、ジョブ型人事制度の導入、グローバルな組織体制の再編などの施策を実施しています。今回は、変革への思いやその狙いを、2017年より様々なプロジェクトを通じて同社の人事関連戦略に伴走、支援してきたグロービスの西との対談で語っていただきました。(※本インタビュー記事の部署・役職、プロフィールは2021年5月取材時点のものです)
DX事業を支援するには自らがDX企業となる必要がある
企業変革への意識を醸成したロンドン赴任
西:時田さんは2019年6月に富士通の代表取締役社長に就任されて以来、パーパス(企業の存在意義)の策定、DX企業を目指すという方針の設定、組織改革など、まさにドラスティックに企業変革に取り組まれています。まず、どのような思いから、この変革に踏み切られたのか教えていただけますか。
時田:一つは入社以来、折に触れては改革の必要性を感じていたことがあります。富士通の事業の軸となるのは社会インフラとなるシステムです。私自身、金融システムのSEとしてそれを守り、安定稼働させることが社会的使命だと信じてきました。しかし一方で、この使命を理由にリスクやチャレンジを避け、オープン化などの新しい取り組みをしてこなかったのではないか、という矛盾した思いもありました。そしてこれはシステムの問題というより、根底で自社の組織や企業文化に関係していることも感じていました。
西:その思いが明確に「変えなければならない」という意識になったのはいつ頃ですか。
時田:2017年にロンドンに赴任したことが大きな契機になりました。それまでの私は金融機関のお客様しか知らない“井の中の蛙”でしたが、ロンドンではグローバルデリバリーを担当し、8か国の海外地域を統括したことで視野が広がり、日本が異質であることを実感しました。日本では気づかない当社の弱点も見えました。
西:どのようなことですか。
時田:一例を挙げると、私は執行役員として赴任したにも関わらず、ロンドンから執行役員のサイトにアクセスしようとしたらできなかったのです(笑)。同じ富士通なのに各国拠点でセキュリティ・ポリシーが異なるためでした。このように日本にいたらまったく不都合がないのに、海外拠点では困ることがたくさんありました。グローバルカンパニーとして恥ずかしいと思いましたね。
西:制度面だけでなく、コミュニケーション面でも転機になったとうかがいました。
時田:これは非常に大きかったですね。私はロンドンに赴任して世界8か国、1万4千人の部下を持つことになりました。そこで1年かけて8か国を回り、タウンホールミーティング(現場社員との対話集会)を積極的に実施しました。大変な歓迎を受け、皆が本音で話してくれました。社員と互いに顔の見える場で対話することは、トップとして最低限必要なことだと確信し、コミュニケーションの重要性を痛感しました。ですから今回、社長に就任した後も、タウンホールミーティングをほぼ全世界で実施しました。新型コロナ禍の影響が出てからは出張に行けなかったので、オンラインで国境をまたいで一度に千人単位の社員に会うことができました。
自ら開発した技術を利用し、経営に活かす企業へ
西:今回の変革では、従来のIT 企業を脱し、「DX 企業を目指す」方針を掲げられました。ご自身も社長就任後すぐにCDXO(Chief Digital Transformation Officer)に就任されました。目指しているのはどのような企業なのでしょうか。
時田:パーパス・ドリブン、データ・ドリブンで当社をDX企業へ変えることを決意しましたが、通り一遍の表現ではインパクトがないと思っていたので、言葉を決めるまでには相当試行錯誤しました。DX企業といってもさまざまな姿があり、一律に定義できるものではありません。DX企業については、一体どのような企業だろう、と一人ひとりが考えざるを得ない言葉であるところに魅力を感じました。
西:問題意識を喚起する効果ですね。
時田:そうです。あるべき姿を追求している段階ですから、明確な定義はできませんが、手本はあります。それがSAPとマイクロソフトです。
西:そのことは役員に福田譲氏をSAPジャパンから、山本多絵子氏を日本マイクロソフトから招かれたことにも表れていますね。二社のどのような点を評価されていますか。
時田:まずはオープンな風土です。個々人が自由に意見をぶつけあい、強みを出し合える、市場や社会と対話しながら行くべき方向を定めているなどの点です。
そしてテクノロジーカンパニーであること。経営をデータ・ドリブンで動かす、いわゆるダッシュボード経営が当たり前になっています。
何よりも私が憧れを感じるのは、自ら開発した技術を自社で利用し、事業を推進し、経営していることです。私はSEをしていた頃、お客様から何度も「ウチを実験台に使うのか」と言われたことを覚えています。富士通では、顧客に提供している技術を自社では使っていないことが珍しくなかったからです。これでは説得力がありません。運よく受注してもその後、お客様から問題を相談されたとき答えることはできても、起こりうる問題を先取りして手を打つといったことはできません。そうした反省から、今後、お客様のDX施策を支援・推進する企業になるなら、まず自らがDX企業となることが不可欠だと考えたのです。
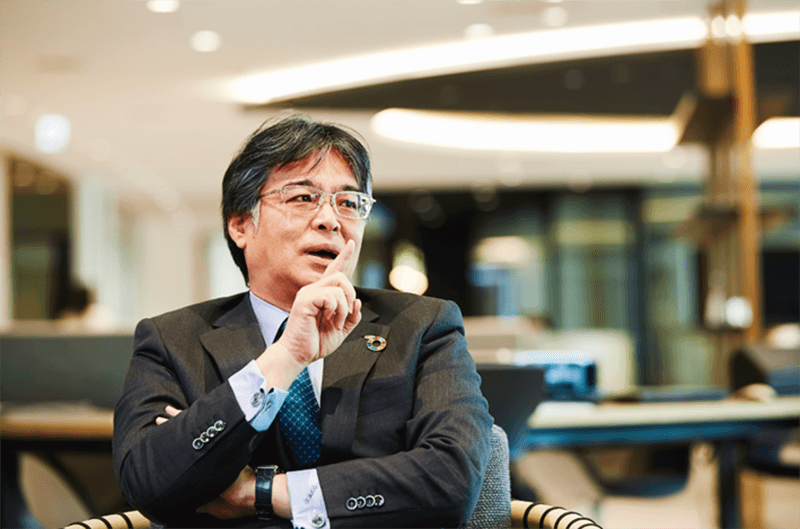
パーパスは富士通全体が向かう方向を定める
不可欠だったのは富士通全体をまとめるメッセージ
西:今回の企業変革では、パーパス・ドリブンも欠かせない柱になっています。パーパスについてはどうお考えでしょうか。
時田:パーパスを策定したのは富士通全体のベクトルをそろえるワン・メッセージを創りたかったからです。それがないと、富士通が目指す方向が定まらない、似たようなソリューションが重複する、グローバルな組織最適化ができないなど多くの問題が解決できません。
しかし富士通は全世界で従業員数約13万人、グループ企業も数多く、グループや本部の数だけミッションもありますから、どこかのミッションを使うことはできません。それでパーパスを策定しました。
パーパスを中核に、その実現を目指す行動規範、大切にする価値観を定めました。これが社員の意思決定や行動のよりどころとなる原理原則「Fujitsu Way」です。多言語で使用されるので文言は慎重に配慮しながら決めました。
西:パーパスを策定した真意は社員の方々に伝わっていると思いますか。
時田:正直、そこはわかりません。しかし経営者としてはパーパスを言い続け、社員それぞれが実際に取り組み、その意味を実感してもらうしかないと思っています。
多数派を理解し置き去りにしない変革を
西:どのような組織でも、新しい方向性に対して積極的に牽引する人が2割、中立層が6割、反対する人や動かない人が2割という2:6:2の法則があると言われますが、時田さんはどうお考えですか。
時田:積極的な2割は良しとして、反対する2割に関しては無理強いする気はありません。どれほど議論を尽くしても見解が異なる人はいるし、組織の全員が心地よく受け入れられる施策など存在しません。私は金融SE時代からそういう考え方でしたから、富士通を辞めて転職していく人を引き止めませんでした。むしろ他の場所で大きく花を咲かせて、自分が富士通出身であること、富士通で何を学んだかを語ってほしい、と言って送り出してきたのです。人事には叱られましたが、富士通が人材を輩出できる企業であってほしかったからです。
西:多数派である6割の層はどうご覧になっていますか。
時田:この層は素直についていく層と見られがちですが、私はそうは思いません。彼らは言わば様子見の層です。だからこの層が当事者意識のない、冷笑的な気持にならないようにしたいと思っています。実はかつての私自身がこの6割層の一人でしたからなおさらそう感じるのかもしれません。富士通は全社変革運動や改善運動を実施したことがありますが、私はそういった運動を冷ややかに見ていた社員でした。
西:そういう時田さんだからこそ、6割の人の心情を理解し、動かしていかれるのでしょうね。
時田:DX企業になるための具体的な施策についても、担当部署や経営層だけが先走るようなことがないように気を配っています。
強い組織力の源泉は人にある
人事を大幅に変革、テクノロジー企業としての力を高める
西:改革の中で特に人事改革に力を入れておられますね。
時田:組織を強化、変革する鍵は人事だと確信していたからです。SEとして長く金融機関を見ていて、その組織力の源泉が人事にあると感じました。ロンドンに行ったときは、グローバルではなおさら人事が重要だとわかりました。年功序列はなく、契約があり、一人ひとりの志向や得意分野が違う。ですから人事によるコミュニケーションがなくては組織が成立しません。日本の組織でもあらゆる施策は人事がそれに追いついていないと機能しないと思います。
西:ジョブ型人事制度、大規模なジョブポスティングによる幹部層の最適配置の導入は私から見ても衝撃的でした。本部長以上の幹部社員を含めて600ものポジションを社内外からポスティングするというのですから。勇気を要する決断だったのではありませんか。
時田:グローバルなテクノロジーカンパニーとして世界一を目指すには他に方法はないと覚悟を決めました。今は変革の端緒についたばかりで、反発や不満を持つ人もいるでしょう。しかしいずれ人材活用においても市場原理を機能させ、流動化をはかるのが当然という世界になるはずです。富士通一社だけでは日本全体が変わらないなどの課題は残りますが、このモメンタムの先鞭をつけたという自負は持っています。
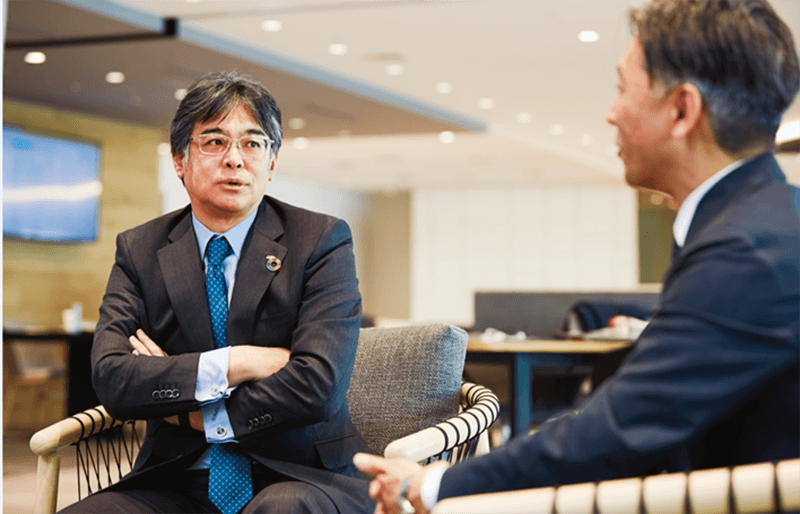
これからのものづくりに欠かせない市場や社会との対話
マーケティングは社会との対話のサイクル
西:DX企業への道を切り開くうえで、最も変わらなければならない分野はどこだとお考えですか。
時田:広い意味でのマーケティングです。これはずっと当社の課題でした。富士通にはお客様に寄り添い、その要望から絶対に逃げないという日本の製造業によくあるマインドが見られます。これは優れた点ですが、ともすれば、お客様に求められたことに応えるだけで満足してしまうという弊害も出てきます。しかしマーケティングとは社会との対話のサイクルです。DX企業を目指すなら、目先にとらわれず、市場、社会、世界と対話しながらこれから必要となるもの、新しいものを創り出す力が求められると思います。
西:受託型から共創型への変革が必要ということですね。
時田:その意味で理化学研究所と共同開発したスパコンの「富岳」の事業は一つの良いモデルだと思います。富岳の前の「京」まではソフトやアプリはアカデミア(学術界)に頼っていました。しかし富岳ではそうした領域まで手がけ、民間にまで利用範囲を広げたと思います。
西:「富岳」がスパコン世界ランキング1位になったことは、あらためて富士通の名を世間に知らしめましたね。
時田:私は富士通のテクノロジーは世界を支えるレベルであることを社員はもっと語ってよいと思います。将来、データ駆動の社会になったとき、高速、大量処理できるインフラが必要になります。富士通はそこに貢献できる世界でも数少ない企業の一つなのですから。
西:世の中へアジェンダ・セッティングをする企業になり、その結果、技術や製品が出てくる流れができれば理想的ですね。
時田:マーケティングも含めて、極めて重要なのは市場や社会との対話です。それを当社の卓越したものづくりに反映させ、「富岳」、5Gネットワークといった成果を生み出していく。これをパーパスの具現化と呼んでもよいでしょう。
西:毎年、富士通がパーパスに向けどのようなアジェンダをセットし、実行してきたかを発表し、社会がそれを注視しているという状態になるとよいと思います。
時田:そうですね。パーパスに向け、当社が何を実行しているかを社内外に知ってもらいたいし、進捗状況についてもKPIを定めて把握し、的確に伝えていきたいと思っています。
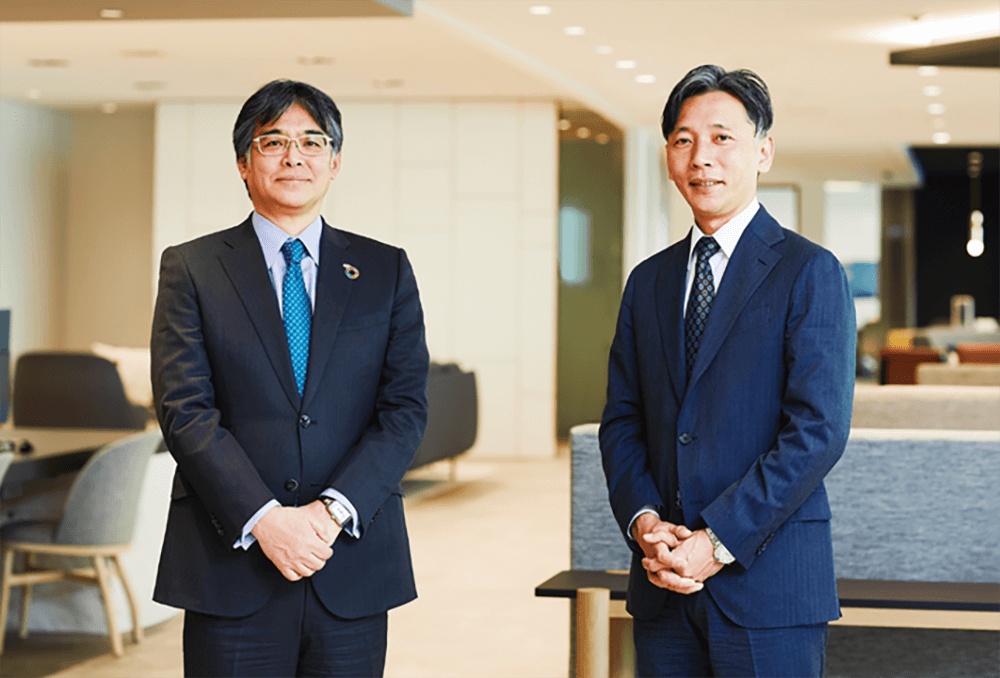
社員13万人の大企業を大きくシフトしていくために、価値提供の在り方だけではなく、会社の存在意義そのものから大きく見直してきた根本は、時田社長の原体験に基づくものだったというストーリーが印象的でした。高い山を登っていくために自社のケイパビリティを冷静に見つめ、自ら社員と何度も対話し、組織に働きかけていること等、大きな組織の方向性を変えていく悩みと苦労が赤裸々に語られています。(西)