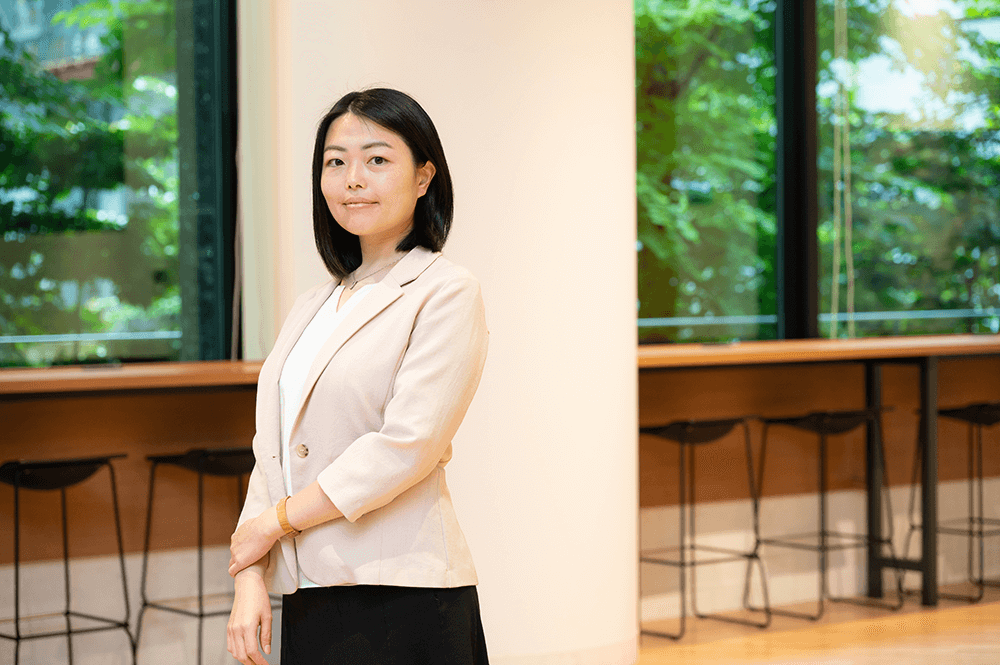- 経営人材
「人の可能性を拓く」人材アセスメント活用とは

テストや研修などを通じて個人の能力やスキルを客観的に評価する「人材アセスメント」。環境変化が激しく実績や経験だけでは将来の活躍を見極めにくい、自律的な成長を支援するための自己理解の重要性が高まっている、といった背景から、そのニーズは年々増しています。一方で、「結果を受け止めきれず自信喪失の原因になってしまう」「やりっぱなしで成長に繋がっているかわからない」といった活用上の悩みもつきものです。
そこで今回は、企業における「人材育成」の場面で、アセスメントを正しく活用するためのポイントを考えていきます。
(本コラムは、「企業と人材」2025年9月号の連載記事を一部編集のうえ、掲載しています)
「測定・評価」を超えた活用が肝
人材育成の現場でアセスメントを活用する際、どのような状態が実現すれば、その目的が果たされたといえるのでしょうか。人材育成プログラムの設計や講師を担当するなかで、「能力を客観的に測定したい」「将来有望な人材を、共通の指標で評価したい」といったご要望を多くうかがいます。
これらは確かにアセスメントの重要な役割の一つですが、育成における本来の目的は「人の可能性を切り拓くこと」です。例えば、本人が「成長の方向性がみえ、努力のモチベーションが高まった」と感じたり、人事・経営陣が「隠れた強みを見出し、適材適所の配置が進んだ」と実感する――。このように、単なる「測定」や「評価」を超え、隠れた可能性を引き出す活用ができてこそ、アセスメントの本来の意義を果たしているといえるでしょう。
アセスメント活用の落とし穴と対処法
一方で、残念ながらアセスメントが十分に活かされなかったり、場合によっては逆効果になってしまう場面があります。ここでは、アセスメント活用における2つの代表的な「落とし穴」を確認するとともに、アセスメントを「成長の羅針盤」にするための対処法をご紹介します。
落とし穴:結果を絶対視してしまう
アセスメントは「数字で結果がみえる」というインパクトが大きいため、結果を「評価ラベル」として過剰にとらえてしまうことがあります。しかし、アセスメントはあくまでも「ある時点」における「ある条件下」での結果です。一つのアセスメント結果を唯一の判断材料のように扱うと、「異なる環境や役割で発揮される力を見落とす」「潜在的な成長可能性を過小評価してしまう」といったリスクが生じます。育成対象者にとっても、アセスメントによる自己理解がレッテル化されてしまい、自律的な成長を妨げる要因になることもあります。
こうしたリスクを乗り越えるためには、以下のような取り組みが求められます。
アセスメント結果はあくまでも「成長のヒント」「傾向の一側面」として活用するよう、周囲や本人に伝えましょう。「評価」ではなく「成長に向けた対話のきっかけ」として位置付けることが大切です。
現場での観察・本人の自己申告など、「多角的な評価視点」を組み合わせて総合判断を行いましょう。必要であれば、2種類以上のアセスメントを活用し、バランスをとることも有効です。
結果を伝えて終わりにせず、「その後、どのように成長しているか」を確認する機会や、育成支援を組み込んだフォローアップ施策を準備しておきましょう。こうした継続的なサポートがあることで、アセスメントをスタート地点として活用できます。
落とし穴:ネガティブな評価に囚われすぎる
360度行動調査など、複数の視点から自身の行動や姿勢についてフィードバックを受けるアセスメントでは、他者からの「評価」に戸惑い、ネガティブな評価やコメントにばかり注目してしまうことがあります。「なぜこのような結果になったのか」と思い悩みすぎて、思考が止まってしまうケースも少なくありません。予期しない評価や厳しい言葉に心が揺さぶられるのは、誰にとっても自然な反応です。
だからこそ、その「揺れ」を自己理解のきっかけへと転換できるかどうかが、育成効果を大きく左右します。アセスメントを実施する際は、「結果を受け止めやすい場づくり」と、「行動への橋渡し」を意識した設計が、成功のカギを握ります。
調査の目的は「成長支援」であることを、本人および周囲に明確に伝えておきましょう。あわせて、ネガティブな反応も「悪いこと」と捉えるのではなく、「気づきの入口」として捉え直すようガイドすることが肝要です。
ネガティブな点数やコメントだけに注目せず、ポジティブなフィードバックとのバランスを意識して結果を整理することで、未来に目を向けやすくなるよう支援しましょう。
フィードバックはあくまで「現時点でのもの」、行動次第で印象が変わることを伝えましょう。そのうえで、具体的にどのように行動変化を目指すか、上司や周囲との対話をプロセスに組み込んでいくことが求められます。
人材アセスメントを「人の可能性を切り拓く」活用につなげるためには、「やって終わり」にせず、「成長ストーリーのプロセスの一部」としてとらえることが重要です。“Before–During–After”で一貫した設計を描き、事前に目的を共有し、結果の活用方法まで具体的に落とし込んでいくこと。成長プランとの紐づけや現場での対話活用を制度から支援し、経営・人事・現場マネジャー間での共通認識を醸成すること。こうした取り組みを粘り強く進めていくことが大切です。