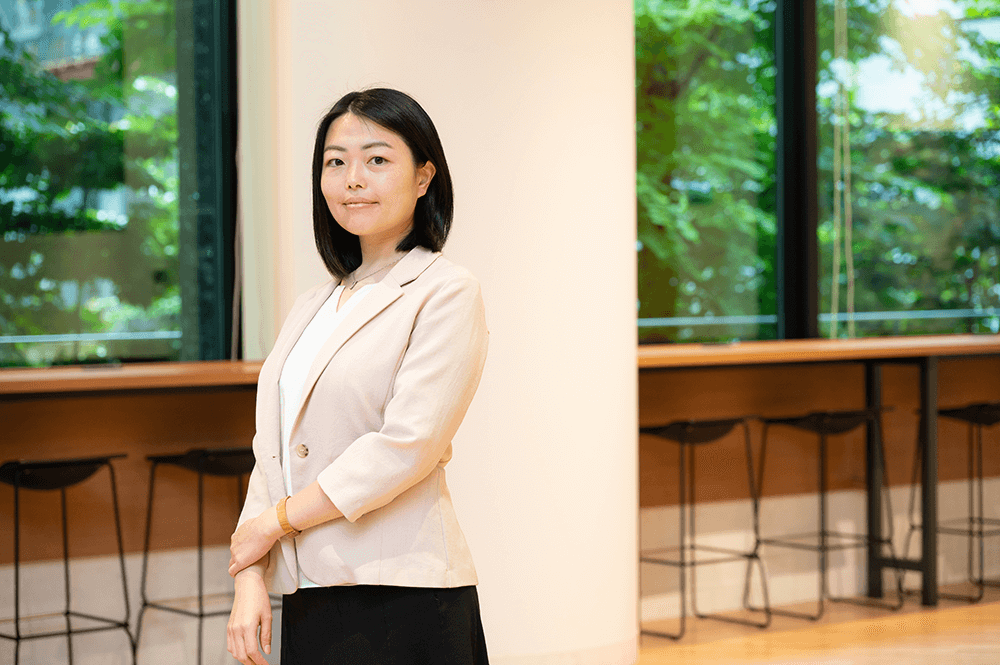- 経営人材
人事が導くリーダーシップ

人事・人材開発分野は多岐にわたります。この連載では「企業価値を高める人事戦略・施策のポイント」をテーマとして、全体観をもった人事戦略構築に向けて、多忙な読者の皆さんが一歩前に踏み出してみようと思える人事施策のヒントをお伝えしていきたいと思います。初回は、「人事が導くリーダーシップ」です。(本コラムは、「企業と人材」2025年4月号の連載記事を一部編集のうえ、掲載しています)
そもそも、リーダーとは誰か?
「リーダー」と聞いて、皆さんは誰を思い浮かべるでしょうか?社長でしょうか?目の前のマネージャーでしょうか?
一つの答えとして、『一流たちの金言』(藤尾秀昭監修、致知出版社)より、ソニー創業者の井深大さんのエピソードを紹介します。
井深さんがソニーの社長時代、最新鋭の設備を備えた厚木工場ができ、世界中から大勢の見学者が来ました。一番の問題だったのが便所の落書きです。工場長も徹底して通知を出したにもかかわらず、いっこうになくなりません。しばらくして工場長から井深さんのもとに電話がありました。パートで来てもらっている便所掃除のおばさんが、蒲鉾の板に、“落書きをしないでください ここは私の神聖な職場です”と書いて便所に貼ったところ、ピタッとなくなったというのです。井深さんは、「この落書きの件では、私も工場長もリーダーシップをとれなかった。パートのおばさんこそがリーダーだった」「自分が望む方向へ、相手の態度なり行動なりが変容することによってはじめてリーダーシップが成り立つ」と言っていたそうです。
リーダーに特別な役職や権限は必要なく、「目の前のやるせない現状を変えたい」「こんな未来を実現したい」という意志と、「私がやるのだ」という当事者意識があれば、誰でもリーダーになれるのです。
リーダーの自覚を育てるには?
では、そんなリーダーを育てるために、私たちは何を考え、何をする必要があるのでしょうか。
リーダー育成の定説は他でも多く紹介されていますので、ここでは、実践において抜けがちだけれど重要だと思うリーダー育成のポイントについて、研修実施前・中・後の観点でご紹介します。
研修実施前:育成対象者は自身にかけられている期待を認識しているか?
私は「人」に関わる仕事に10年以上携わってきましたが、育成対象である本人が、自分にかけられている期待に気づいていないことが非常に多いと感じます。「普段から大事な仕事を任せているんだから、言わなくてもわかっているはず」「あらためて期待を伝えるなんて、ちょっと照れくさいし、自分も言われたことはない」という上司の気持ちもわかりますが、「研修に行ってね」とだけ言われた本人は、「年功序列的に順番が回ってきたのかな?」程度にしか思っていないわけです。期待をかけて会社や上司がお金と時間を投資しているのに、当の本人は気づかぬまま。こんなにもったいないことはありません。
なぜ、他の人ではなくあなたが研修に指名されたのか、組織が何を目指しており、どのような成長を遂げてほしいと考えているのか。こうしたことを、上司から本人に、膝を突き合わせて伝えることが肝要であり、これこそが「私がやるのだ」という火種になるのです。
人事部門の皆さんは、今の上司に対する働きかけでそこを十分伝えられているか、現場で徹底されているか、ぜひ確認してみてください。
研修期間中:育成を人事だけで背負い込まない
人材育成は組織全体をあげて行うものですから、研修にもそのための仕掛けを織り込み、上位層にも育成にコミットしてもらいましょう。上位層の巻き込みは、参加者本人の育成を促進するのみならず、関与する上位層自身の育成にもつながること、そして、本人の成長と上位層の成長が統合され、組織変革にもつながっていくという、2つの効果が期待できます。
上位層の関わり方のイメージとして、いくつか具体例を紹介したいと思います(自社の課題設定と解決をテーマとした数カ月間の研修プログラムを想定)。
①研修内での講話(組織のビジョン、危機感など)
②中間報告会や最終報告会で、質問やアドバイスを行うオブザーバー
③研修参加者の伴走役・指導員
上位層といっても、社長や役員、部門長などさまざまな立場の方が考えられますが、研修の目的や対象層などに合わせて決定します。また、②③はフィードバック力が問われるため、事前に、研修の趣旨やフィードバックしてほしい観点などについてのガイドを出したり、指導員向けの研修を用意することも検討しましょう。
研修後:「やりっぱなし」にしないためには?
参加者自身が研修を通してリーダーとしての当事者意識や未来に向けてのビジョンをもつことができたとしても、その状態をいかに維持・醸成していくかが、最も重要かつ難しいポイントではないでしょうか。研修をやりっぱなしにしないためには、そこで得られたものを参加者自身が反芻する機会をつくることが肝となります。
例えば、少し期間を置いたうえで、フォローアップの場を設け、これまでを振り返って、自分にどんな変化・成長があったのか、あるいは、現場でどんな難しさ・新しい課題にぶつかっているのかを共有し、ディスカッションする機会をつくることが考えられます。さらには、OB/OG指導員として、翌回の研修に招待してもよいでしょう。
ここまで、リーダー育成についてお伝えしてきましたが、私たち自身もリーダーを育てるリーダーです。巻き込むメンバーが増えるほどチャレンジのハードルは上がりますが、「この組織を変えていくのは私だ」「活き活きと活躍するリーダーを輩出したい」という思いをもって、共に歩んでいきましょう。