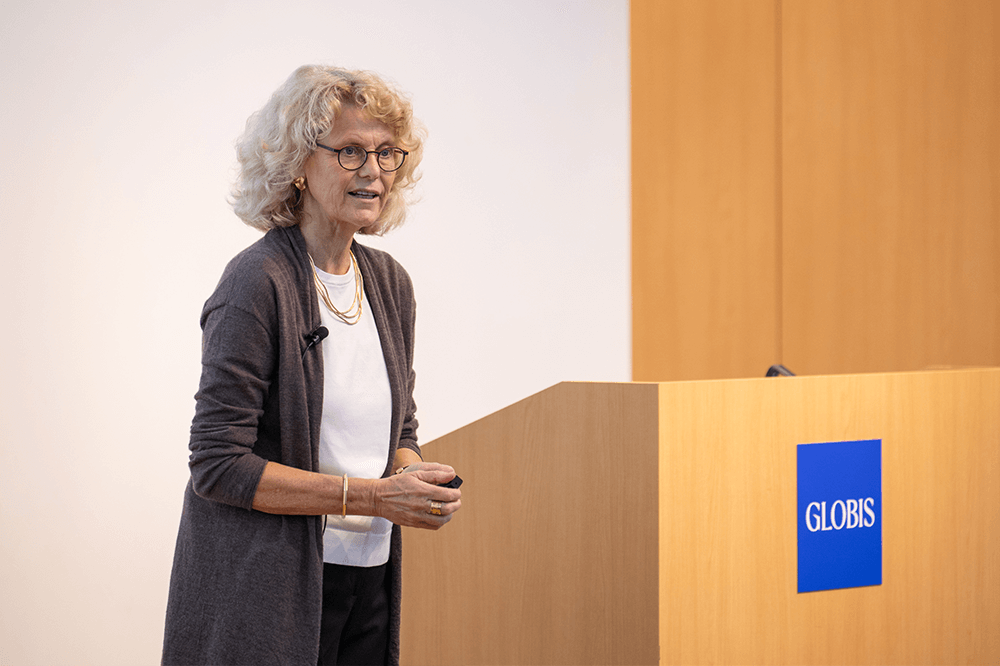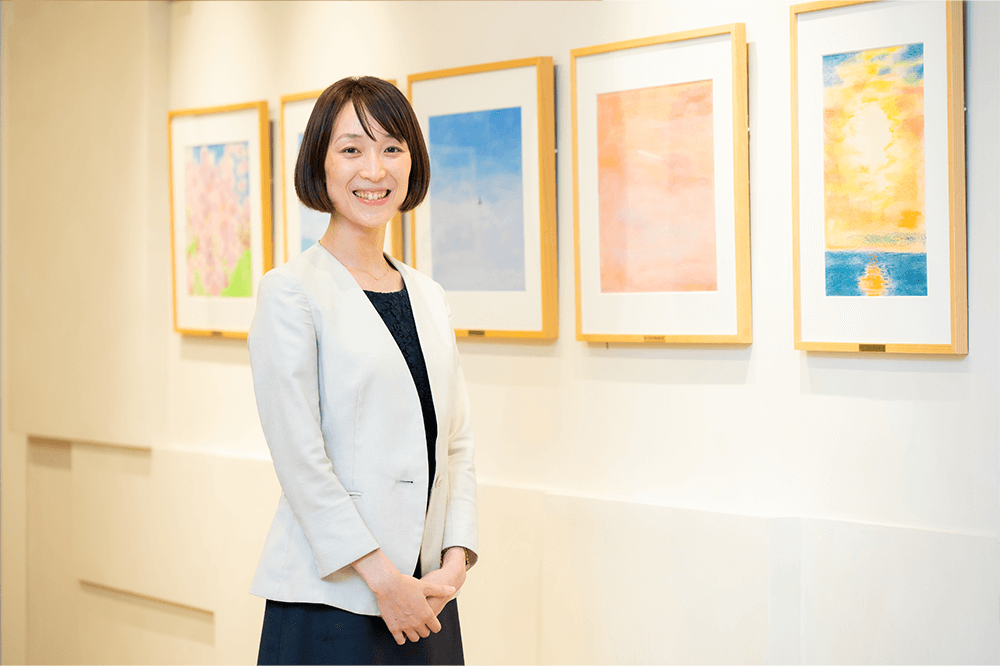- グローバル・D&I
グローバル人材育成担当者が押さえるべき3つの要件
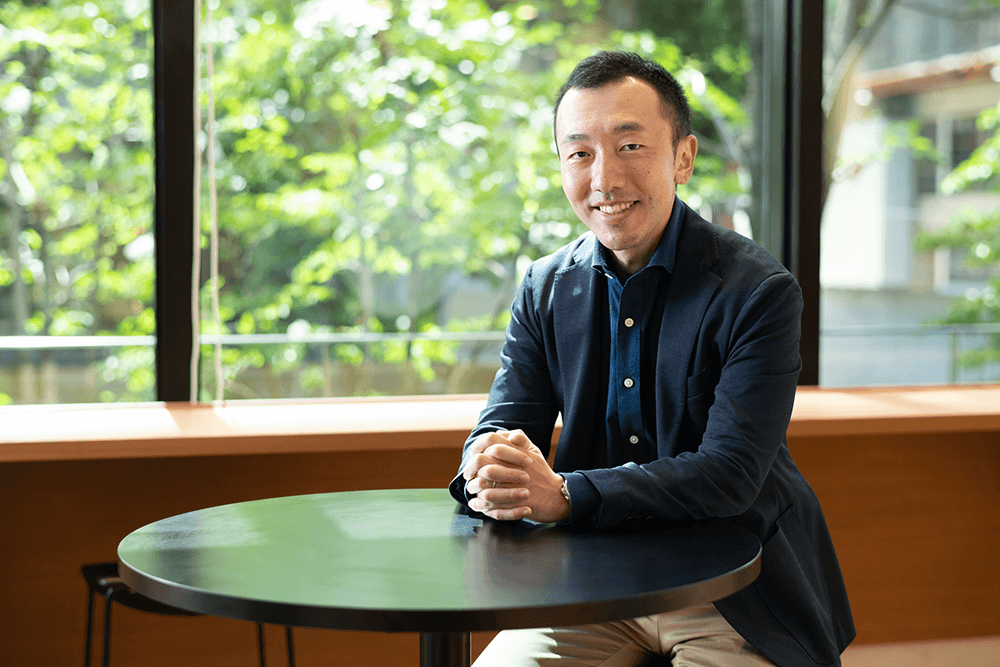
グローバル事業の加速に伴い、人事の役割はこれまで以上に高度かつ複雑になっています。南知宏氏 の『グローバル企業のための新日本型人材マネジメントのすすめ』※でも説明されているとおり、世界的な潮流として、人事部門は「採用」「育成」などの機能別組織から、経営層や事業部門への企画・支援など、役割や目的をベースとした目的別人事組織への移行が進んでいます。こうした変化のなか、グローバル人材育成を担う人事担当者には、これまで以上に幅広い視点と柔軟なスキルセットが求められます。
今回は、多数のグローバル人材育成プロジェクトに携わるなかで得た知見から、育成担当者が成果を上げるために欠かせない3つの要件をご紹介します。
(本コラムは、「企業と人材」2025年10月号の連載記事を一部編集のうえ、掲載しています)
1. あるべきグローバル人材像を明確化し、関係者と合意する
まず重要なのは、自社にとっての「あるべきグローバル人材像」を明確にし、経営陣や各リージョン・拠点のHRと合意することです。その基盤となるのが「人材マネジメントのフレームワーク」です。人材育成は経営理念や経営戦略の実現手段の一つであり、人材像は企業戦略によって異なります。経営戦略や採用・評価・配置などのHRMシステムとの整合性を明示することで、社内外のステークホルダーから納得を得やすくなります。
自社のグローバル人材像を描く際には、例えば以下の問いに答えることが有効です。
・グローバル戦略の現状と将来の方向性は?
・その実現に向け、どのような組織を目指すべきか?
・グローバルで特に重要となるポジションは?
・そのポジションに求められる人材像は?
・彼/彼女らの育成課題は何か?
これらの答えは相互に矛盾せず、整合性を保つ必要があります。また、これらの合意形成の対象は本社の経営陣や人事、事業部のキーパーソンに加え、海外拠点の人事や現地事業部のキーパーソンなど多岐にわたります。そのため、議論を効果的・効率的に進めるための高いファシリテーションスキルが不可欠です。さらに、エリン・メイヤーの『異文化理解力』※でも指摘されているように、文化的背景によって意思決定や議論の進め方は異なります。こうした違いを理解し、状況に応じて柔軟にコミュニケーションスタイルを使い分ける力も求められます。
2. 「自社」と「日本」の視点を育成に活かす
グローバル人材は、自社の価値や文化を体現し、社外・社内のステークホルダーに伝える「伝道師」の役割を担います。そのため、創業者の理念やこれまでの経営上の意思決定の背景などを理解し、「グローバルでも大切にすべき自社らしさ」を自分なりに理解・言語化できるようになることが求められます。
多くの場合、自社らしさの根底には日本文化や哲学が色濃く影響しています。グローバル人材は、日本的価値観を理解することで、自社理解を深めるだけでなく、グローバルで説得力を持って語るための土台を築くことができます。
近年、世界のビジネスリーダーの間で日本文化の思想や実践への注目が高まっています。この潮流を踏まえると、日本文化について社外から問われる機会も今後は増えるでしょう。その場で自信を持って語れることが、グローバル人材としての信頼や影響力を高める事にもつながります。
人材育成担当者は、こうした力をグローバル人材が身につけられるよう、研修や育成施策の中で「自社らしさ」と「日本文化の背景」を学び、言語化する機会を意図的に組み込むことが重要です。
ここで、「自社」と「日本」の視点を結び付けた事例として、阿部修平氏著書の『トヨタ「家元組織」革命』※に紹介されている取り組みを一つ挙げます。トヨタ自動車では、TPS(Toyota Production System)を理解するため、豊田佐吉記念館やトヨタ鞍ヶ池記念館などで創業の歴史や生産方式の成り立ちを学び、さらに、京都の寺院で空間設計や流れの本質を学ぶプログラムを実施しているとのことです。このような学びを通じて、トヨタ自動車の経営システムであるTPSと、その背景にある思想や価値観を結び付けて理解し、自社の本質をより深く捉えられるようになります。
3. 人材育成の理論を理解し、自らの“持論”を持つ
海外、特に欧米のステークホルダーと議論する際には、提案の根拠となる理論を求められることが少なくありません。日本では現場経験が重視される傾向がありますが、海外ではHRに関する学術的知見を持つ人材も多く、研修設計の背景にある理論や論拠について問われる場面がしばしばあります。そのため、社内で海外拠点の経営陣や人事と議論する際には、人材育成に関する理論的知識を持っていることが不可欠です。代表的な理論の一例としては、コルブの経験学習モデル、成人発達理論、U理論などが挙げられます。
さらに重要なのは、単なる理論を理解するだけでなく、次のような問いに対して自分なりの哲学や信念に基づく持論をもつことです。
・人は何をきっかけに変わるのか?
・リーダーはどのようにして育つのか?
持論をもつことで、プロフェッショナルとしての専門性に深みが増し、関係者からの信頼も得やすくなります。特にグローバル環境では、自らの考えを積極的に主張しなければ、その付加価値を理解してもらえない傾向があります。理論を土台とした持論は、異文化環境での説得力を高める大きな武器となります。
最後に、グローバル人材育成の手法や進め方において、どの組織にも通用する唯一の正解は存在しません。大切なのは、正解を探し求めることではなく、本稿で示した3つの要件も参考にしながら、自社にとっての最適解を描き、関係者と合意し、実行し、そして問い直す――このサイクルを繰り返すことです。この継続こそが、組織の未来を支えるグローバル人材を育てる原動力になります。
<参考文献>
1. 南知宏『グローバル企業のための新日本型人材マネジメントのすすめ』BOW&PARTNERS(発行)、中央経済グループパブリッシング(発売), 2024年
2. エリン・メイヤー『異文化理解力 ― 相手と自分の真意がわかる ビジネスパーソン必須の教養』英治出版, 2015年
3. 阿部修平『トヨタ「家元組織」革命――世界が学ぶ永続企業の「思想・技・所作」』リンクタイズ, 2022年