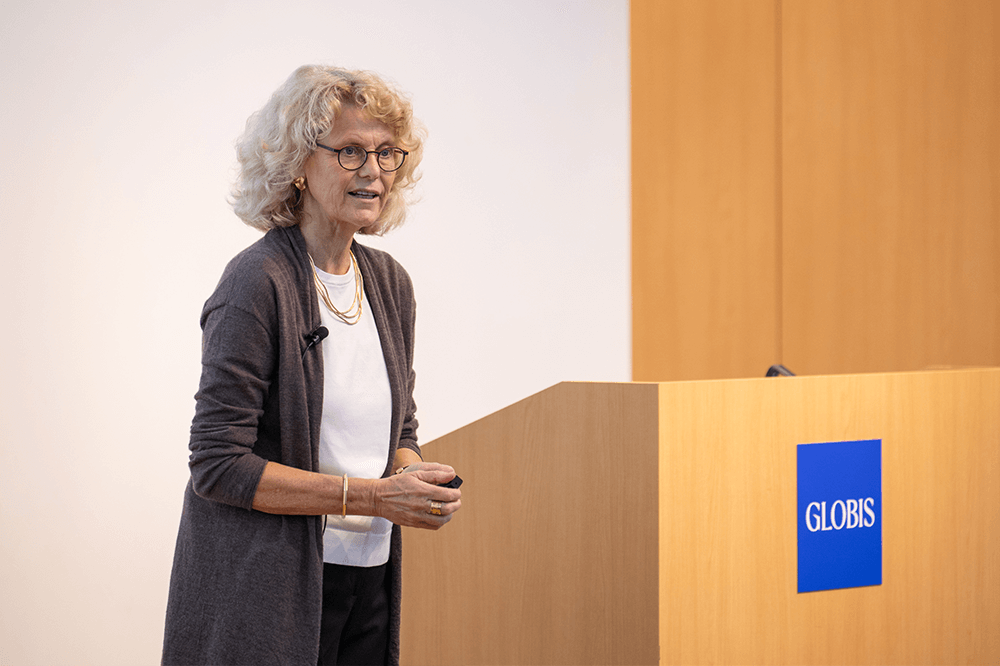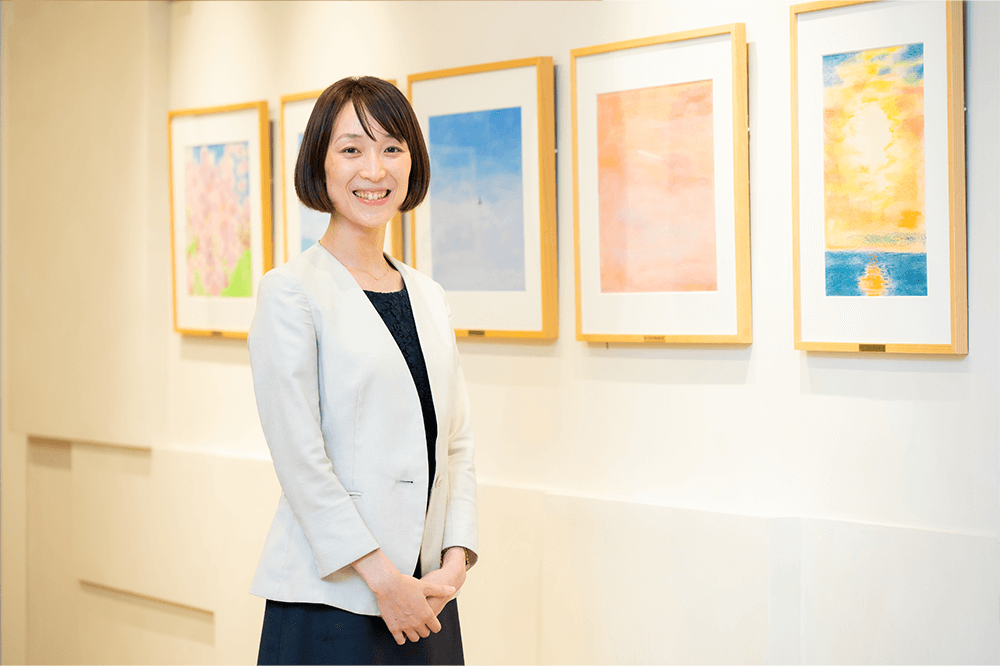- グローバル・D&I
- 経営人材
トヨタに学ぶグローバル人材育成術:グローバル拠点の未来を担うリーダーをいかに育むか

各地域(region)を統括していくグローバルリーダーを育成するにあたり、どのようなことを育成に取り入れるべきなのか。グローバル企業・トヨタでは、配置~育成を分けず、連動を意識し、さまざまな施策を行っています。そこで、今回は育成施策の一つである「グローバルトヨタのリーダー育成プログラム」について、トヨタ自動車株式会社 人材開発部 組織開発・育成室 室長 森谷 彩子氏に語っていただきました。モデレーターを務めたグロービス 福田 亮が、トヨタの人材育成において何を大切にし、どのように取り組んでいるのか、詳しいお話を伺っています。
本レポートは、2025年1月30日に「第1回グローバルCLO会議」で行われた講演内容を一部まとめたものです。なおこの会議は、日本企業のグローバルCLO(Chief Learning Officer人材育成責任者)が業種や業界の垣根を越えて集い、グローバルに活躍できるリーダーの育成や組織づくりを議論する場として創設されました。
変わりゆく自動車業界に対応するために
自動運転技術の進化やIoT化による多様なサービスの提供、EV車の普及といった環境負荷対策など、自動車業界は大きな転換点を迎えています。トヨタ自動車(以下、トヨタ)もその潮流の中で、クルマの概念そのものを変え、モビリティーカンパニーへのフルモデルチェンジを目指し、大きく変革を遂げようとしています。
「テクノロジーの進化によって、クルマはネットや街とつながり、AIが搭載されることで、移動の道具を越えて街の一部となってきています」と、森谷氏は語ります。その代表的な取り組みが、静岡県の東富士工場跡地に開設された「Toyota Woven City」です。ここはクルマだけでなく、ドローンやロボットなどを含めた未来のモビリティを検証できる「街の形をした実験都市」です。ここでは、実際の都市環境を再現し、新たな技術の実証実験を進めています。
自動車業界全体が「100年に一度の大変革期」と言われる中、もはや従来の常識が通用しない時代に突入しています。「これまでの延長線上に正解があるとは限りません。そのため、内向きにならずに外部環境の変化を素早くつかみ、お客様の声に真摯に向き合い、柔軟に対応していかなければ、生き残っていけないと日々感じています」と、森谷氏は危機感をにじませます。
「配置〜育成」の連動を意識して行うグローバルリーダー育成
このような大きな変革を迎える中、トヨタは、単なる研修プログラムではなく、「配置から育成」の連動を意識した育成プロセスの構築を目指して、グローバルリーダー育成に向けた取り組みを始めました。将来の各地域のトップが自発的に成長できる「育成サイクル」を確立したいと考え、こうした育成方法を導入しています。
プログラム(Leadership Development Program、以下LDP)は2段階で構成されていますが、本稿でご紹介するLDP1では、将来のリーダー候補者が毎年世界中から集まり、3回のインターバル期間を含めた半年間、グローバルトヨタに求められる価値観や組織変革をリードするために必要なことを学びながら、志と情熱をこめた自分らしいリーダー像を考え抜きます。加えて、研修で終わりではなく、その後のOJT経験をとても大切にしています。このような背景から、一人ひとりの成長や志向に合わせた配置・アサインメントを行い、他エリアへの異動、本社への派遣、営業から製造への配置転換、さらには社外留学で異業種への挑戦など、さまざまな機会を設ける努力をしています。こうした多様な経験を通じて、その人の能力発揮を促していく。それが「配置~育成」を連動させて行う、トヨタのグローバルリーダー育成施策です。

グローバルリーダーに求められる「3つの重点テーマ」を根づかせるプログラム設計
LDP1研修プログラムで修得してもらう重点テーマは大きく3つあると言います。それは、「トヨタの価値観の継承と進化」「組織変革のリーダーシップ」「地域や機能を超えた視点」です。
LDP1は、4回(4月、7月、9月、11月)のModuleで構成され、そのうち3回がオンライン、1回が対面で実施。約1年間をかけて行う包括的なプログラムになっています。(2024年度時点)
プログラムの大枠の構成としては、参加者はまず、自分自身を見つめ直し、他地域の状況や文化を理解するとともに、創業から大事にしてきている考えや理念に立ち返ることから始めます。続いて「トヨタの原点や価値観への理解」を深め、未来構想に取り組み、ロールモデルとの対話、そして今後のチャレンジ・具体的な行動宣言「My Toyota Story」へと進みます。
「My Toyota Story」は、未来のモビリティ社会の実現に向けた“トヨタでのビジョン、自身の志、実現までの道筋”をまとめた一人ひとりの行動宣言です。これまでの経験をもとに培った視点で、まず自身の考えを整理し、Moduleを通じて他の受講者からのフィードバックやセッションで得た知見を反映しながら、段階的に磨き上げ完成させていきます。Module2では、日本に場を移し、対面で参加者相互のフィードバックに加え、現地現物で感じたトヨタらしさについて、グローバルリーダーとの対話を通じて、自身のStoryを深めます。続くModule3では、書籍やトヨタの過去・現在の学びを取り入れ、さらなるバージョンアップを図ります。
そしてModule4では全参加者の前で「My Toyota Story」を発表します。一人10分間のスピーチでは、参加者ごとに異なる内容を語ります。共通するのは「自分自身を振り返り、未来に向けた志を言語化すること」です。
参加者は「自分がどのような人間で、どのような環境で育ち、どのような生き方をしてきたのか」を出発点に話し、そこからこれまでの経験を通じて何を感じ、どのような学びを得たのかを整理し、言葉にしていきます。例えば、北米でしか生活したことのない人が新興国での経験を通じて価値観を揺さぶられたような出来事を体験した場合、その気づきを自身の視点で語り、他の受講者に共有していきます。
また、Module2にあるジャパンセッションは、全プログラムの中で唯一、日本において対面形式(5日間)で行います。このセッションは、トヨタの価値観を五感で感じ、理解を深め、浸透させることを目的としています。期間中は、トヨタの歴史やカーボンニュートラル戦略、水素技術、BEVなど、普段は聞くことができない決して綺麗ごとではない、リーダーの悩みや苦労、直面している壁について直接触れたり、実際に現場を訪れたりして、リアルに学ぶ機会が提供されます。
例えば「TPS in京都」と呼ばれるセッションでは、トヨタ生産方式(TPS※)の考え方と日本の伝統文化(禅や枯山水、茶道)との関連性を体験的に学びます。「無駄のない美しい動作」や「人や物の流れ」といった概念が、日本文化とトヨタの価値観にどのように結びついているのかを実感できるプログラムです。
※TPS(Toyota Production System)とは、「誰かのために」という思いを原点に、「問題が発生した際にすぐに対応できる仕組み」である「自働化」と「必要なものを、必要なときに、必要なだけ作る」といった「ジャスト・イン・タイム」を2本柱とする創業期以来のトヨタの経営哲学であり、お客様にとって良いものを安くタイムリーに届けることを追求したもの。
そして、参加者は創業者である豊田喜一郎氏の邸宅を訪れ、トヨタの原点を感じます。これは参加者が創業当時の姿をリアルに感じ取り、学ぶことのできる貴重な機会だと言います。さらに現在グローバルトヨタのリーダーとして活躍する人物との対話セッションでは、考え方や視点に触れることで、自分自身を見つめ直して、新たな視点を得るきっかけとなります。これらのプログラムは、Module2の目的である「トヨタの価値観への理解を深める、未来を考える」に最も適しており、参加者からも高い評価を得ていると言います。
実際に参加者からは「大切なのは”People People People” すべては人中心だということを学んだ」というコメントが届いています。森谷氏は、「この言葉に象徴されるように、彼らにはトヨタの考える『人が財産』という価値観がより身近なものとして捉えられるようになっていきます。そしてトヨタの価値観を実感し、『頭だけでなく、経験・体感しながら学ぶ』というトヨタの学習スタイルを修得していくのです」と語りました。
加えて、このプログラムでは参加者同士の「仲間づくり」も重視しており、将来のリーダー同士がつながるさまざまなコミュニケーション機会を意図的に設けています。こうした取り組みによって、地域や部門を超えたグローバルなネットワークが形成され、将来のトヨタを担うリーダーシップ人材を育てているのです。

研修では綺麗事ではなく、あえて、リアルで生々しい課題を参加者に共有する
このように、LDP1では「すべては人が中心である」という気づきを、参加者自身が得ているということが特徴的です。「誰かのために」「この人のために自分たちは生かされている」という考え方を、すべてのコンテンツにおいて多角的かつ繰り返し伝える設計により、これがトヨタの考え方だと体感できる仕掛けとなっています。決められたコンテンツを理解してもらうのではなく、参加者自身がテーマに向き合い、対話を通じて自身の考えを深めていくアプローチです。
森谷氏は次のように語ります。
「特に登壇者や講師の方には『綺麗事ではなく、何が大変で、何に汗をかいているのか』といったリアルで生々しい課題を話していただくようお願いしています。そういった話が、参加者の共感を生み、気づきにつながるのです。グロービスさんにも協力してもらいながら、講師からの問いかけ、参加者同士や人事担当者との対話といった機会を多く設けることで、その中から参加者自身が気づきを言語化していくプロセスを大切にしています。」
本社とグローバル拠点をつなぐ鍵は「対話の量」にある
トヨタ全体(連結)では従業員が約38万人(2024年3月末時点)。そのうち国内が2割弱の約7万人。次に多いのが全体の1割強を占める北米で約5万3000人、そしてその他の子会社で構成されています。森谷氏の説明によると、「トヨタはグローバルにおいて『研究・生産・販売』を主要な機能として展開しておりますが、大切にしているのは“町いちばん“の考え方。各地域主体の経営を行っており、『地域統括』がその地域、現場を支える役割を担っています」。
「地域統括」は8つの拠点に配置し、HQ(ヘッドクォーター)のある日本のトヨタ本社(TMC)のHRと連携しながら、グローバルトヨタの人材開発を行っています。日本以外の7つの拠点は北米、欧州、中国、アジア、インド/中東/東アジア/オセアニア、南アフリカ、中南米のことを指します。
このように世界中に拠点を持ち、それぞれが独自の文化や課題を抱える中で、全体に共通する育成プログラムを構築するには、多様な関係者の理解と協力を得る必要があります。
従来は育成方針を整えた後に、教育プログラムを策定する流れでしたが、森谷氏は「育成方針の正解は分からないし、決めるのは時間がかかる。であれば、トライ&エラーの精神でまずやってみる」という考えのもと、育成方針が固まる前から、グローバルリーダーの育成プログラムの立案・実施に踏み切りました。上位層と方向性をすり合わせ、受講者が在籍する地域とも密に連携し、現場の課題を配属先に適宜フィードバックしながら進めることで、柔軟な仕組みを構築しています。
「当時は『先走りすぎでは』との声もありましたが、各地域のHRや現場社員の共感を得られるよう、チームメンバーが現地へ出向き、一人ひとりと対話を重ね、お互いの理解を深めており、今もその努力は続けてくれています。そして地域HRやCEOの意見を反映し、グローバルHR会議でも現場の声を共有しながら全体の方向性を統一。結果として、形式だけでなく、血の通った育成施策へと進化していきました。こうした大規模な取り組みでは、制度設計だけでなく、何よりも『対話の量』が成功の鍵だと実感しています」と、森谷氏は語りました。

働く人たちが何を考え、どうすれば幸せになれるのかを考え続ける
最後は、森谷氏が参加者へのメッセージを送り、セッションを締めくくりました。
「今お話しした通り、私たちがすでに取り組めていることもあれば、まだ道半ばのことも多くあります。人事の役割はあくまでも従業員の活躍を支援することであり、主役にはなりえません。私たちがやるべきは、『現場で働く人たちが何を考え、何に悩んでいるのかを想像し、その先にいるお客様やステークホルダーの皆さまの幸せのために私たちは何ができるのか』を考え続けることです。
企業文化の違いなどはありますが、同じ立場で取り組んでいる皆さんとこうして意見を交わせたことは嬉しく思います。ともにがんばりましょう!」
【第1回グローバルCLO会議 開催概要】
■開催日:2025年1月30日
■会場:グロービス経営大学院 東京校
■対象者:企業におけるグローバル人材育成責任者及び担当者
■統一テーマ:グローバルで躍進する人・組織を創る ~人事の役割と実践~
■登壇者:
▪森谷彩子氏(トヨタ自動車株式会社 人材開発部 組織開発・育成室 室長)
▪モデレーター:福田 亮(株式会社グロービス グロービス・コーポレート・ソリューション ディレクター)