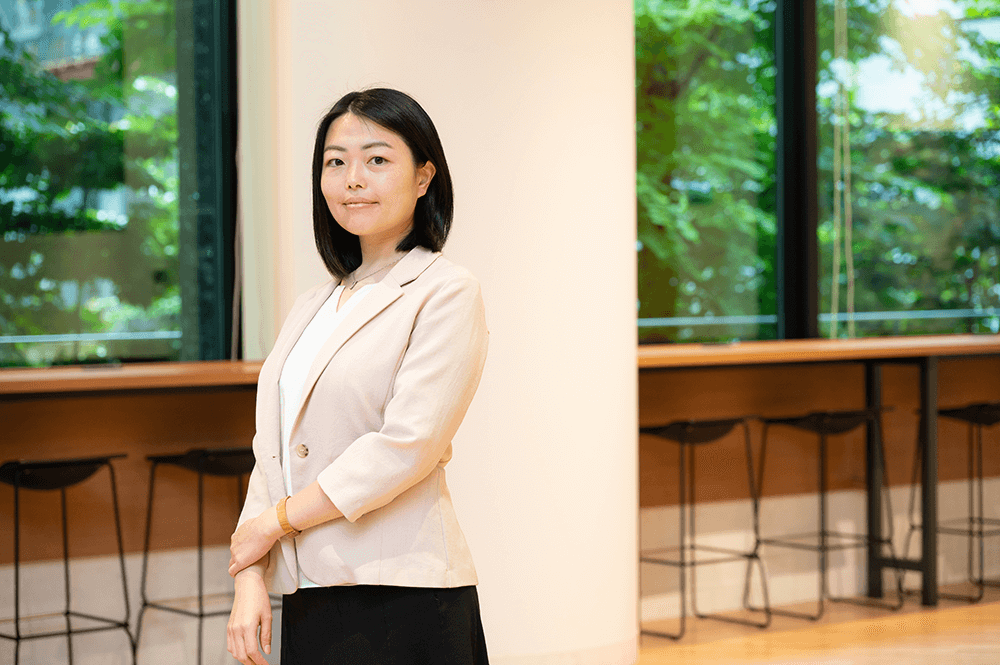- 経営チームの変革
- 経営人材
統合と再構築 日本的経営を変えたCxO体制による大転換

レゾナックは2023年、昭和電工と日立化成の統合によって誕生しました。この統合において、昭和電工の髙橋秀仁氏(現・レゾナックCEO)を支え、共に新体制の発足に携わったのが、日立化成の今井のり氏(現CHRO)です。統合に際してレゾナックは、グローバル・プラクティスに学びつつ、経営体制をCxO体制に変革しました。その経緯、企業カルチャーの重要性、経営幹部サクセッションのあり方などについて、今井のり氏に、グロービスの板倉義彦がお尋ねしました。
強い経営に欠かせない企業カルチャーを醸成する
2社統合を機に日本の経営をアップグレードしたい
板倉:まず、昭和電工と日立化成を統合し、レゾナックを設立するに当たって、なぜ経営体制をCxO 体制にしたのかを教えてください。
今井:旧昭和電工は事業軸が非常に強い会社でした。その長所はありますが、事業部を超えて管理機能が横串を通すことはできません。統合後はポートフォリオ経営として、事業最適ではなく全体最適で一体化した会社を目指したかった。それにはCxO体制にする必要があると考えました。
板倉:そのためにまず取り組んだことは?
今井:グローバル企業のベンチマークを参考に、CxOそれぞれの役割や仕事を明確にしていきました。例えばCFOのあるべき姿、役割は何か、実際にどういう人がなっているのか、といった部分について、日本企業とのギャップを分析しました。
板倉:そこから何が見えてきましたか。
今井:日本企業とベンチマーク企業と比べたとき、最もギャップが大きかった部分はCHRO でした。日本企業のCHRO が重視するのは人事制度、給与、労務などのオペレーショナルな業務ですが、グローバル企業ではリーダーシップや企業カルチャーを指向し、特にカルチャーへのコミットは非常に強いということです。
板倉:髙橋さんはしばしばJTC(日本の伝統的企業)から脱却したいということを口にされますね。
今井:髙橋は昭和電工、私は日立化成にいて、どちらも経営企画部門の長として統合事業に携わっていました。統合の目的は事業のシナジーですが、二人とも、統合を機に日本の経営をアップグレードし、グローバルに戦える企業を作りたいと考えていました。
板倉:それで、統合に際してグローバル・プラクティスを導入しようとしたのですね。
今井:そうです。これからの経営体制のあるべき姿をベンチマークし、現状との差分を理解したうえで、実現しようとしました。特にCHRO のあり方を変えることが非常に重要だと考えました。

HRの真の目的は企業や事業の成長
板倉:グローバル・プラクティスを取り入れたくてもうまくいかず、苦労している会社は少なくありません。これは、そもそも日本企業となじまないからなのか、それとも取り入れ方の問題なのか、今井さんのお考えはいかがですか。
今井:HR について言えば、取り入れ方が最も難しい要素であることは確かです。HR の役割は、HRそのものではなく企業や事業の成長です。事業戦略には段階があり、それによって人と組織の課題は変化します。また、組織の成熟度によっても必要な人材は変わります。フェーズによってHRがすべきことは変わります。打ち手も様々あるので、何をどの順番で実行するか、複雑な要素を紐解きながら考えなくてはなりません。
板倉:非常に複雑な分野ですね。会社の現状を深く理解していなくては判断もできません。
今井:当社も3年間やってきて課題がさらに見えてきたので、次の3年に向け、HR 組織、機能を見直しました。1年間にわたってHR の部課長30名くらいでありたい姿と現在の課題について議論を重ね、今年から変更しました。また、次に目指したい人事制度については、経営メンバーとオフサイトミーティングで議論を重ねています。
板倉:経営メンバーでHR 方針の議論を行っているのですね。レゾナックでは経営チームでの対話が非常に活発に行われている印象があります。経営メンバーが一枚岩となり、チームでの対話を効果的に行うためにどのような工夫をしているのでしょうか。
今井:対話でどれだけ自分をさらけ出し、経営メンバー同士の距離感を縮められるかが鍵だと思います。関係性の質を高めるためです。統合してまもなく、カルチャー・サーベイをしてみたら前に所属していた会社によって文化の差異が出ることがわかりました。しかし1年くらい対話を続けていると、気心が知れ、経営会議でも話がしやすくなるものです。

事業の発展や変化によってHRのすべきことは変わる
経営の機能として客観的視点で役員を選ぶ
板倉:少し話が変わりますが、新しい経営チームの体制は誰がどのように決められたのですか。
今井:髙橋も私も、経営のあるべき姿を実現するために、とにかく上から変えていこうと考えました。まず決めたのは執行役員の定義です。従来の日本企業でよくある論功行賞的な要素は一切抜きで決めました。
板倉:どのようなプロセスを経て経営チームの体制を設計したのでしょうか。
今井:必要な機能を一つの箱だとすると、まず、その箱を決め、それに合う人を選んでいく。箱の数が役員の人数ですね。髙橋と私、昭和電工と日立化成の当時の両社長、それぞれの社の実務者(PMO)を加えた6人で検討しました。公平を期すために候補者全員と私たちが外部アセスメントを受け、スコアを付けました。その結果も踏まえて決めた人選を取締役会に提出し、ベンチマークを見せ、グローバルでの経営統合のあり方も紹介しながら、経営体制はこうしたいと説明しました。
板倉:定量化し、客観的な視点で伝えたわけですね。
今井:そうです。アセスメントの概要なども見せながら、経営チームの体制を固めていきました。
板倉:CxOの要件はどの程度具体的に決められているのですか。
今井:統合時は厳密な表記はしていませんでした。先ほど申し上げた箱と役割だけ決めて、必要な人選や採用を進めました。現在は、CxOとBU長(事業トップ)については、執行役員としての要件を記述してあります。これはコンピテンシーレベルの要件で、従業員のマネージャー向けコンピテンシーの拡張版といったものです。統合後、経営会議メンバーによるオフサイトミーティングで議論した案を、指名諮問委員会での確認を経て、取締役会に提出して決めたものです。
板倉:統合前は現実路線で決め、形ができてから厳密にしていったということですね。
今井:ただ、今後も会社のフェーズは変わっていきます。その変革の局面に応じて、どういう人が必要かも変わります。ですから、役員として基本的に必要な要件は維持しつつ、それに加えて、「こういう資質や経験のある人がほしい」という要請も出てくる可能性があります。
板倉:しっかり固めている部分と柔軟に対応する部分をうまく融合させている印象です。ただ、これは難しいところで、状況に流されてもいけないし、硬直的になってもいけない。運用のコツのようなものはありますか。
今井:CEOとCHROが「あるべき論」をしっかりと議論しておくことだと思います。
板倉:指名諮問委員会との関係はどのようになっているのでしょうか。
今井:指名諮問委員会の委員長である常石哲男さん(レゾナック・ホールディングス社外取締役、元・東京エレクトロン取締役会長)の意向も反映し、指名諮問委員会がすべきことは、CEOと取締役の選解任のみとし、執行体制はCEOに任せると決めています。ただし、その選定のプロセスの確認は指名諮問委員会がしています。
板倉:経営チームが動きやすい体制としているということでしょうか。
今井:私たち経営チームは、全社的視野でサクセッションプランニングを行っています。執行役員の要件のほか、タレントレビューの結果から、各CxOのポジションのカバー率、外国人や女性の比率などを、社員個人の名は一切出さずに全体概要として、指名諮問委員会にお伝えしています。
板倉:委員会はモニタリングに徹している感じですね。
今井:現実問題として、こうした非常に詳細な部分まで指名諮問委員会が一から見ることは不可能です。このやり方は経営チームと、常石さんが主導する社外取締役の方々が、綿密に話し合ったうえで決定し、定着してきました。

リーダーの役割は後継者を育てること
10年以上を見越した後継者の発掘にも取り組む
板倉:次の体制に向けた準備(経営幹部サクセッション)についてもお聞かせください。
今井:リーダーの役割の一つは後継者を育てることです。各CxOに後継者計画を策定してもらい、年に1回レビューをしています。候補になる人材には、全社的観点での選抜育成プログラムや、それぞれの個性に合った社外のトレーニング・プログラムを受けてもらっています。
板倉:どのくらい先までの後継者を見ていますか。選考基準はあるのでしょうか。
今井:大きくは2種類あり、2年くらいで交代可能な人とそれ以降の長期視点で選抜している人ですね。選考はそれぞれのCxOに任せていますが、基準としては役員としての基本的な要件を満たすことと、次のCxO に必要となるであろう要件や役割を理解してもらっています。また、外部アセスメントによる客観的な基準も持ち込んで評価します。さらに言えば、もっと先、10年以上を見越した後継者の発掘にも取り組んでいます。
予想できない時代だからこそ組織には尖った人材も必要
“尖った人材”が思考の多様性に寄与する
板倉:現在、後継者育成の候補者は何歳くらいの年齢層ですか。
今井:下が35歳くらいです。でも私としては、もっと早く、20代後半から30代前半までの層から候補を見出しておきたいと思っています。
板倉:それはなぜですか。
今井:早い段階から手をつけないと、組織的スクリーニングによって“ 尖った人材”がどんどん減ってしまうからです。一般に日本の組織は「素直で従順な良い子」が昇進し、そういう人ばかりの集団になりやすい。きちんとした上司の下では尖った人材が淘汰されてしまう恐れがあります。しかし、尖った人材、弾けた人材がいなくては変革はできません。
板倉:なるほど。そうした人材の何を見られているのでしょうか。
今井:ポテンシャルを発見することですね。また、FFS(Five Factors &Stress)という人の思考行動特性を5因子とストレス値で定量化する外部アセスメントも参考になります。組織が管理しにくいところもあるが、どこか突出している、といった人はいるものです。そうした人材を確保しておく必要があります。
板倉:所属長に任せていては見つからないでしょうね。
今井:ですから、いろいろな機会をとらえて見つけ、プールしておいて、外部アセスメントを受けてもらい、ポテンシャルの大きさを判断したい。その人のポテンシャルや個人特性に合わせた育成の機会を提供する。これを今後パターン化していきたいと考えています。
板倉:それが10年後に影響してきますね。
今井:その通りです。これからはますます予想のつかない時代になるでしょう。そのためには思考の多様性は極めて重要です。なるべく早くから人材を発掘し、画一化しない、アジリティの高い組織を作りたいと考えています。
板倉:尖った人材が育ち、思考の多様性を担保する。そのことが、事業が移り変わっても適応できる組織を作ることになるのですね。ポートフォリオ経営も、企業カルチャーや人材への考え方も、すべて非常に長期的な視点から出てくることに感銘しました。本日はどうもありがとうございました。

人的資本経営が経営のキーワードとなっている昨今、戦略を実現するためにHRが機能することの重要性を否定する人はいないでしょう。一方で、既存の仕組みがあったり、様々な要因が関連してくるが故に、それを実践することは容易ではありません。一見すると派手に見えるレゾナックの変革ですが、その実態は、「監督と執行の役割分担」、「箱を作って人を充てる」、「人材の早期発掘」など、やるべきことを的確に設定し、着実に実行していく地道な営みといえます。あるべき姿の実現に向けて、グローバル・プラクティスを参考にしながら、経営の仕組み、人事の仕組みを変革し続けるレゾナックの取り組みには、具体的な事例のみならず、そのアプローチや、基本思想など日本企業にとって示唆に富む要素が数多くあります。本対談が、皆様の会社における経営をアップデートするきっかけとなれば幸いです。(板倉)