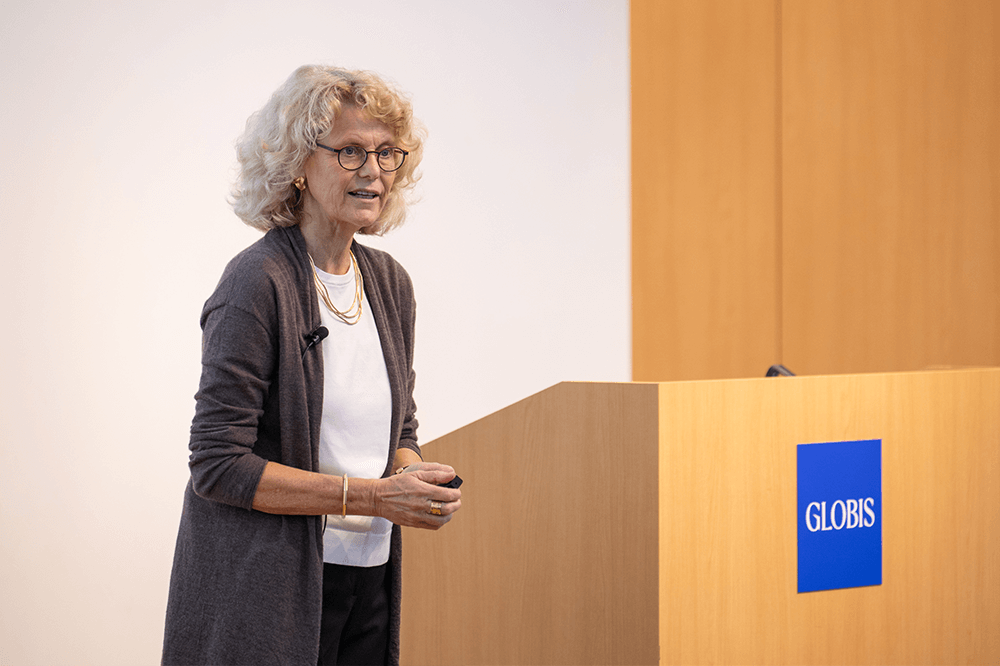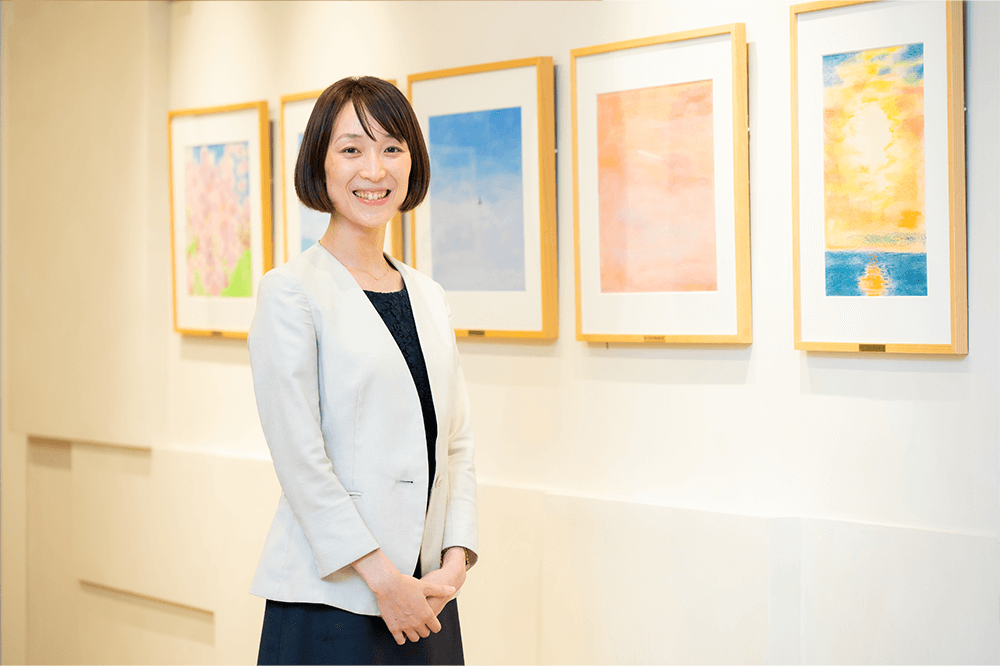- グローバル・D&I
- 組織風土改革
多様性と一体感『楽天主義』を世界へ

日本発のIT企業の代表格ともいえる楽天グループは、Eコマースの楽天市場を皮切りに、カード、トラベル、証券、モバイルなど70を超えるサービスを提供し、着実にその事業を広げてきました。2010年頃からはグローバル展開を強化し、現在、世界30の国・地域にサービス拠点を有しています。同グループが早くから注力してきたのが企業カルチャーの醸成であり、企業の哲学や価値観の浸透でした。グローバル化の過程でそれをどのように実践したのでしょうか。創業メンバーの一人で、現在Group CCuO(Chief Culture Officer)を務める小林正忠さんに、グロービスの内田圭亮がお尋ねしました。
多様性と統一感を掛け合わせる
『楽天主義』を軸に多様な力を束ねる
内田:楽天は、現在世界30の国と地域で70以上のサービスを展開されていらっしゃいますが、どのような企業カルチャーを目指して、世界中の拠点に広めているのでしょうか。
小林:
当社のカルチャーは大きく二つ考えられます。一つは周りの全てが無理だと言っても、あらゆる手段を探して挑戦し、やり切ること、そしてそれを醍醐味だと感じること。当社は1997年に会社を立ち上げ、これまでに難易度の高い様々な挑戦をしましたが、常に「信じていればその道は切り拓ける」と考えてきました。GET THINGS DONE(信念不抜)というブランドコンセプトのフレーズもそれを象徴するものです。
もう一つは、多様性を一つの方向に向けること。新しいビジネスにはイノベーションが欠かせませんが、これは同質性でなく多様性から生まれます。出身国、人種、教育、宗教など、多種多様なバックグラウンドを持つ人々が共に働く中でイノベーションは生まれます。しかし、多様性をそのままにしておくと組織はバラバラになりかねません。だからこそ、多様性を尊重しながらも、組織を一つの方向に促す必要があります。それを可能にするのが、従業員全員が当社の価値観・行動指針である『楽天主義』を理解し、共有することです。
『楽天主義』の特徴は何ですか。
小林:大きな特徴の一つとして、事業の社会的意義を志向していることがあります。当社では、エンパワーメントと表現しています。これは起業家精神の表れでもあって、1ミリでも社会を我々の信じる良い方向へ向けていこうとする姿勢です。例えば2020年に本格開始した携帯キャリアサービス『楽天モバイル』の背景には、「携帯市場の民主化」という大義名分がありました。実際、楽天モバイルの参入で、携帯市場の月額料金が劇的に下がったことはご存知の通りです。
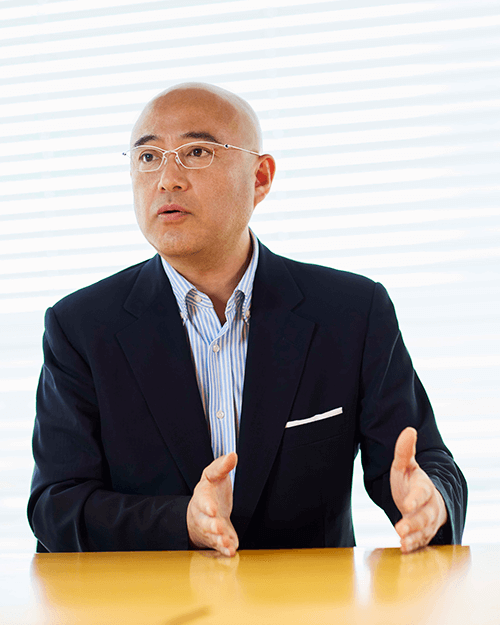
小林 正忠 氏
言葉だけでなく、体現することで企業カルチャーは浸透する
『楽天主義』を世界に浸透させるために
内田:多様な国籍や価値観を持った人材が様々な働き方をしている中で、『楽天主義』をグローバルな組織全体に浸透させ、目指す姿へと変えていくのは容易ではないと思います。これまでどのような施策、工夫を重ねてこられたのでしょうか。
小林:いくつかの段階がありました。まず、明文化です。楽天グループが上場したのは2000年ですが、その9カ月ほど前には現在の「成功のコンセプト」5項目(『常に改善、常に前進』、『Professionalism の徹底』、『仮説→実行→検証→仕組化』、『顧客満足の最大化』『スピード!! スピード!! スピード!!』)を明文化しました。それまでは従業員数20数名の規模でしたから、あるべき姿を文章にしなくてもわかりあえる距離感でしたが、企業規模が拡大すればこれまでとは違ってくるという思いがありました。他社をM&Aすれば、資本関係ができて結果的に楽天グループの従業員が増えるわけです。また、中途入社の従業員も毎月何十人も入ってきます。一人ひとりに楽天の考え方を理解してもらうには、企業の理念や行動指針の明文化は欠かせませんでした。研修方法なども工夫しながら、伝えていきました。
内田:業務研修だけでなく、企業理念についても研修を行ったということですね。
小林:そうです。入社してすぐ、『楽天主義』とは何かをみっちり研修で伝えました。
内田:理念をグローバルに浸透させるには、さらに工夫が必要になりそうですね。
小林:当社は2010年頃から急速に事業のグローバル展開を加速しましたが、『楽天主義』を理解してもらうには、明文化したものを翻訳して配付するだけでは不十分であることがわかってきました。母国語でなければ真意まで伝わり切らないからです。そこで、例えば台湾で『楽天主義』を伝える際には、まず英訳した文言を英語が堪能な台湾出身者に読んでもらい、さらに母国語で従業員に説明してもらうというプロセスを取り入れました。各言語の性質も踏まえながら、世界中の従業員に伝わるように心がけています。
内田:小林さんは米国にも赴任されましたね。その経験の中で感じることも多かったのではないでしょうか。
小林:2012年から米州本社の社長として米国に駐在しました。楽天では毎週「朝会」と呼ばれる全社ミーティングを行い、そこで三木谷浩史(会長兼社長)が会社の全体的な視野から、ビジョンや方針を語ります。当然米国でも実施していたのですが、彼らには朝会をする理由、その目的や意味といったスピリットの部分は伝わっていなかったんです。私が率先垂範して実行し、伝えることで徐々に理解されていきました。
内田:企業カルチャーや価値観を浸透させるためには、体感して納得することが重要なのでしょうね。
小林:細かい話をすると、当社では朝会が終わった後、デスクの掃除をするのが習慣になっていて、椅子の足まで拭いてきれいにします。こうした小さなことを徹底して実現できなくては、営業や事業の目標を達成することもできないという考え方なのです。こうした姿勢も最初は理解されませんでしたが、自ら体現して見せ続けることで、少しずつ組織全体に浸透していくのを実感しました。
内田:大切にしている価値観を言語化するだけでは、頭だけの表面的な理解になってしまう。そこでトップや上司が体現して見せるということですね。
小林:組織によっても温度差があります。インドの拠点では、『楽天主義』の徹底に非常に熱心なリーダーがいて、朝会後の掃除がきちんとできているかどうかを綿密にチェックしていました。このように自律的に動けるようになった拠点では、我々はクオリティのチェックだけすればよく、運用自体は任せておけると思います。
自律性を高めるための制度や工夫はありますか。
小林:『楽天主義』を掲げるのは、一人ひとりの従業員がトップと同じような当事者意識を持ち、自分事として考えられるようになってほしいからです。そこで毎月、単なる業績評価にとどまらず、『楽天主義』を体現している人を表彰する「楽天賞」という制度を設けています。これにより、グループ全体に共通概念がじわじわ浸透していきます。また「楽天主義ファシリテーター」と呼ばれるアンバサダー的人材が『楽天主義』を体現し、指導するワークショップを行なっています。例えば、インドの拠点ならインドの楽天主義ファシリテーターがワークショップを担当します。
内田:楽天主義ファシリテーターは今、何人くらいいらっしゃいますか。
小林:現在、全世界で140人以上います。本来はマネジメント層が自ら説明できることが理想なので、その体制づくりに向けた準備も進めているところです。
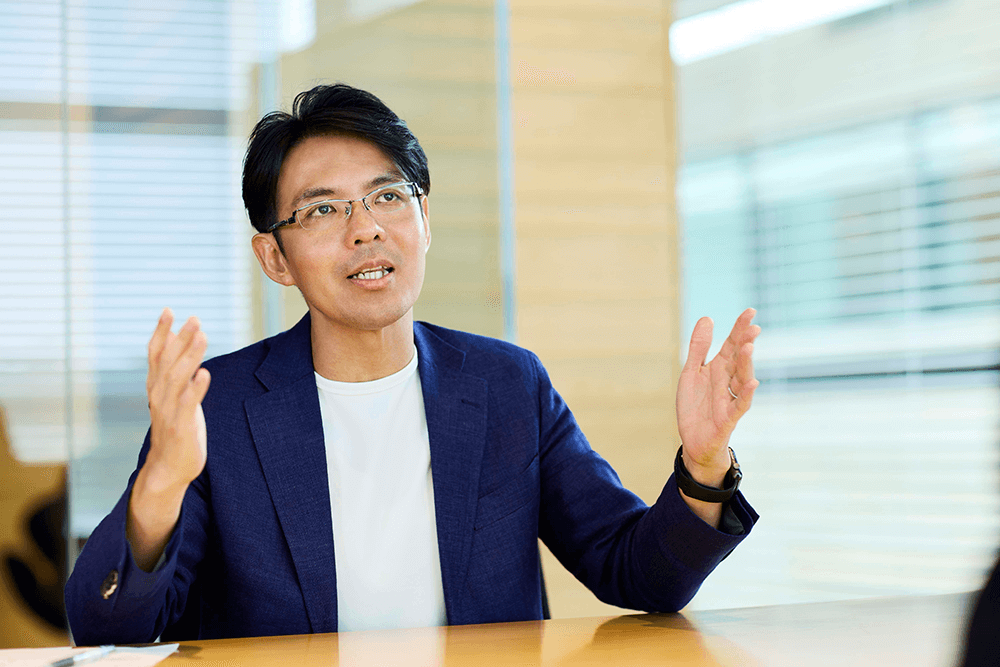
個と組織の価値観をつなぎ、一体感を生み出す
内田:一人ひとりの従業員の価値観と、企業の価値観をつなげることが大切だということですね。企業規模が大きくなっても、組織の一体感や団結力を保ち続けるために、具体的にはどのような施策を講じていますか。
小林:『楽天主義』の中に「一致団結」という考え方があります。その一環として、「一致団結」をテーマに掲げて、従業員が楽天モバイルの営業活動を行うプロジェクトを実施しています。営業、人事、総務、エンジニアなど、職務の制限なしに楽天モバイルの契約者数を増やしていこうという意図で始めました。このような全社を挙げて市場開拓に挑む取り組みは、これまでも何度か実施しています。
内田:実際にあった他の例を教えていただけますか。
小林:まだインターネット通販すらよく知られていない時代に楽天市場は開業し、当時の従業員数は百数十人くらいでした。この時は、全従業員が楽天市場の営業活動に取り組みました。また、クレジットカード事業を開始した時には、新規入会の獲得を目指す活動を実施しました。
内田:それは見方によっては、ノルマがあって大変だと見られてしまう可能性もありますね。
小林:従業員が当事者意識を持つことは、起業家精神の第一歩だと思います。しかし、成長して大企業になると、組織が縦割りになり、そうした精神は失われてしまいがち。それでも、全員を巻きこんで前進すれば、起業家精神を維持できます。また当事者意識を持つことで、例えば楽天モバイルであれば、部署や職位に関係なく従業員全員がサービスの強みや提供価値を理解し、説明できるようになります。そうでないと契約が取れないからです。これはサービス企業にとって極めて重要なことだと思います。
内田:ここまでの内容を少し整理すると、イノベーションのために多様性は不可欠、それと同時に多様性を力に変えるには組織が同じ方向を向く必要がある。そのために『楽天主義』を徹底しているということですね。
小林:そうです。私たちは大きな方針は明確に示しますが、具体的なやり方は各人に委ねています。例えば、楽天グループは現在「AI-nization」と名付けて生成AIの活用を進めていますが、これも全員が活用するという方向性は示しつつ、実際にどう使うかは、部署や個人によって異なる。そうすることで、多様性と統一性のバランスを取っているのです。
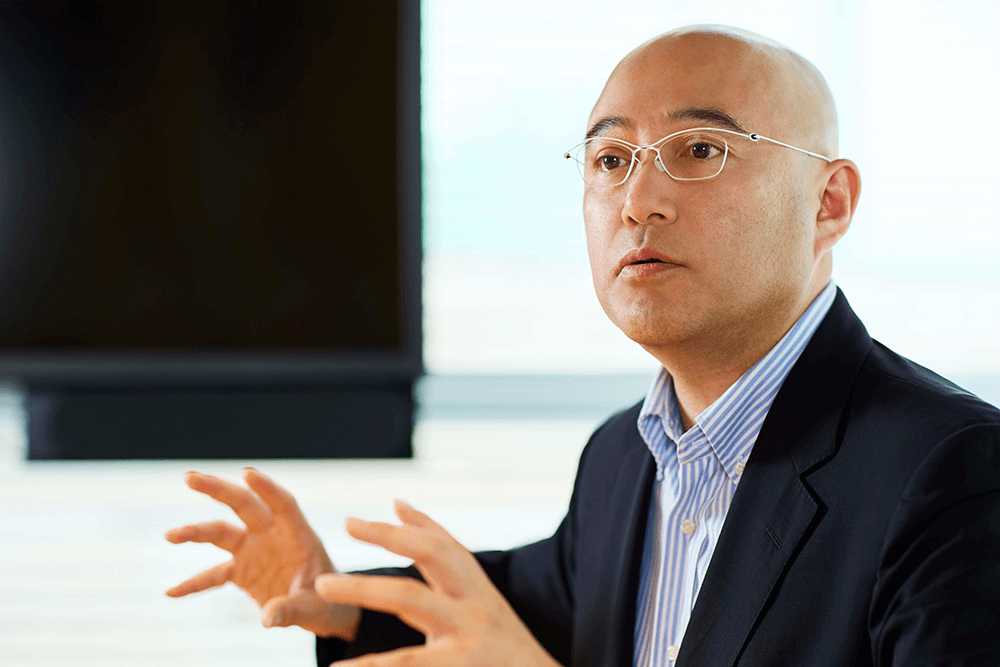
小林 正忠 氏
一人ひとりが「働きがい」を実感できる企業カルチャーへ
「働きがい」という カルチャーが重要
内田:数年前のコロナ禍で急速に普及した在宅勤務を、現在でも継続している企業は少なくありません。しかし楽天グループでは、早くから公式に週4回の出社に戻されていました。これも企業カルチャーと関係しているのでしょうか。
小林:企業カルチャーと強く関係しています。創業時代から我々が挑んできた事業は、常に「実現不可能」と評されるようなものでした。そのような事業は、普通のやり方では成し遂げられません。成功させるには、高い密度で仕事をすることが必要ですから、出社して対面することが役立ちます。対面でのコミュニケーションであれば、その場で気づいた点を尋ねたり確認したりすることが簡単なので、圧倒的に早く、臨機応変に動くことが可能です。注力事業ほど、出社比率は高くなる傾向にあります。
内田:最近は「ウェルビーイング経営」が注目され、働き方にその視点を取り入れる企業が増えていますが、小林さんはどうお考えになりますか。
小林:人生は一回きりしかありません。だからこそ、一時的な瞬間風速ではなく、自分らしさや幸福を追求することが大切だと考えています。当社は、従業員がそうした個人の生き方に真剣に向き合うことを前提としている会社です。ただし、気をつけなくてはいけないのは、ウェルビーイングという言葉に引っ張られて、「働きやすさ」ばかりに偏ってしまうことです。
内田:具体的には、どういうことでしょうか。
小林:ウェルビーイングには、「働きやすさ」と「働きがい」という二つの側面があります。「働きやすさ」は、例えばオフィスにカフェスペースを設置したり、社食でランチを無料提供するなど、どうしてもリラックス性に傾きやすい。もちろんそれも大事ですが、私たちがより重視したいのは「働きがい」です。新しいチャレンジに挑み、何かを成し遂げる喜び――そこにこそ、従業員の真のウェルビーイングがあると考えています。
内田:単なる快適さではなく、挑戦の喜びを軸にした方針に注力されているのですね。
小林:近年は、日本全体が「働きやすさ」に偏ってしまっているように感じますが、もう一度、一人ひとりが「働きがい」を実感できるようなカルチャーを作りたいです。
内田:最後に、Group CCuOとして、今後どのように取り組みを進化させていきたいですか。
小林:楽天グループは今、全世界で約3万人の従業員を擁するグローバルな企業となりました。『楽天主義』を上層部から伝達していくと同時に、ミドルマネジメント層が『楽天主義』を理解、実践し、語れるようにしていきたい。ミドルマネジメント層でも『楽天主義』のワークショップをまだ受けていない人、体系的に語れない人もいるので、今期はここを100%にするのが目標です。それができたら次は、『楽天主義』を体現するためのモニタリング手法を考えていきたいですね。
内田:それをGET THINGS DONEの精神でグローバルに展開していくわけですね。世界で戦う楽天グループの活力に触れた気がします。ありがとうございました。
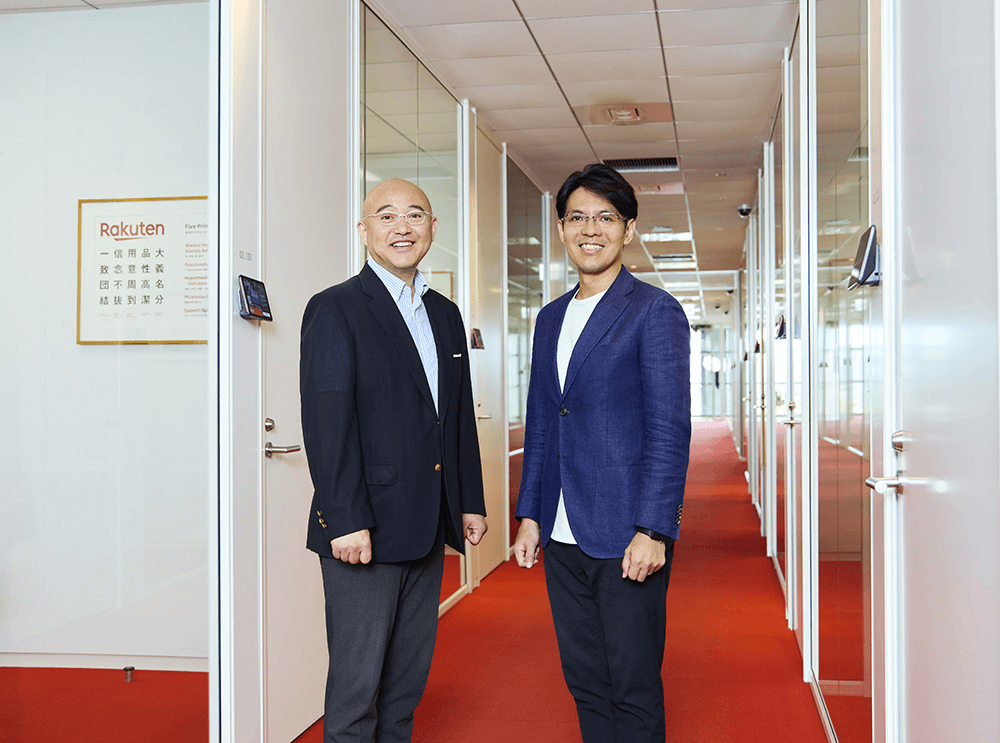
楽天のオフィスに伺うと、本当に多様で多国籍な人材が集う組織であることを感じますが、今回はその多様性をどのようにして一つの大きな力にしているかを伺いました。小林さんからは、トップの三木谷さんが大事にされている価値観・行動指針である『楽天主義』がいかに多様な人材を束ね組織力に変えているかをお話しいただきました。特に、全社員が例外なく市場に向き合い新サービスの会員数獲得に向けて目標を持って動く営みは非常に印象的で、これほどまで社員の一体感や起業家精神を育む営みは中々ないであろうと感じました。楽天のようなグローバルな大企業において、いかに自社が育みたい組織文化を醸成できるのか、そのヒントが満載です。(内田)