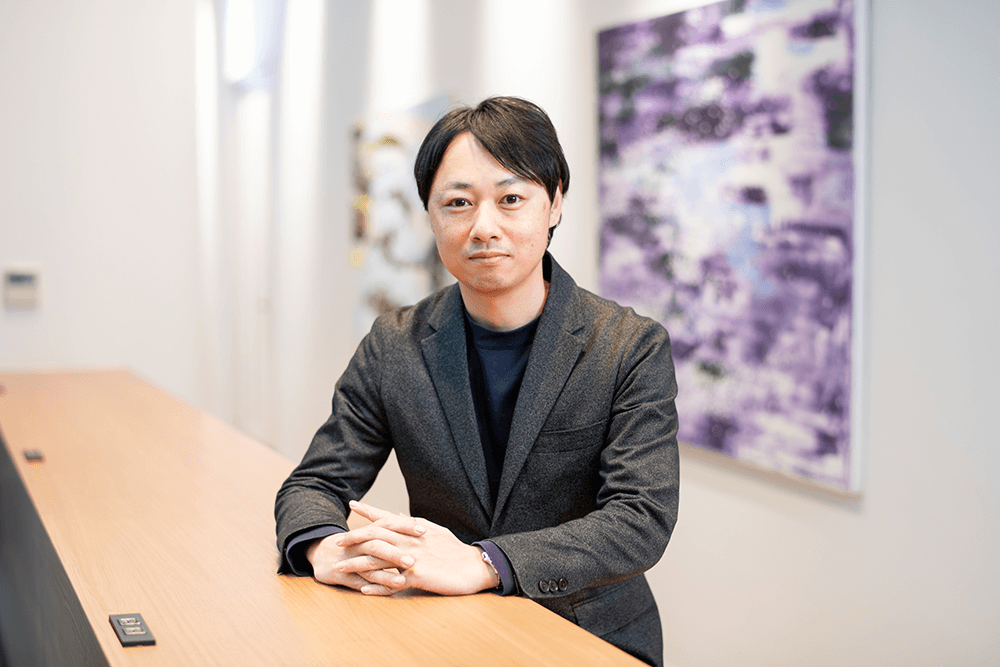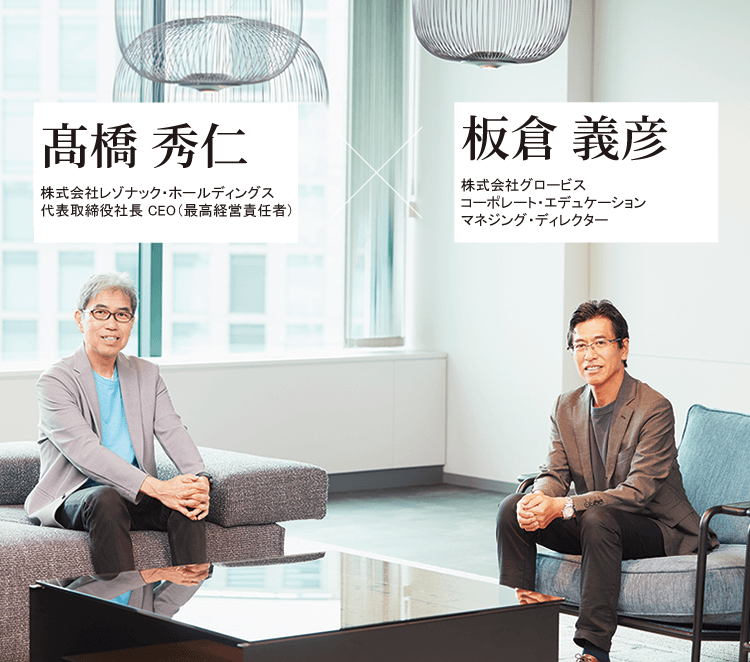- 組織風土改革
すべての人の「しあわせ」に寄り添う 社会課題解決企業への挑戦

日本のクレジットカード企業の嚆矢でもある丸井グループは、小売と金融が一体になったビジネスから商業ビル、証券、物流など、業態を広げてきました。1970年に丸井健保会館を開設するなど、早くから社員の健康に注力してきた企業でしたが、2011年頃からこれをさらに発展させたウェルビーイング経営に取り組み、高く評価されています。その指揮を取ったのは、代表取締役社長の青井浩さん。「すべての人が『しあわせ』を感じられるインクルーシブな社会を共に創る」というミッションへの思いや経営の発想について、グロービスの内田との対談で語っていただきました。
経営危機から企業文化の改革へ
経営危機をきっかけに企業文化を見直す
内田:丸井グループは健康経営、より現代的な表現で言えばウェルビーイング経営に取り組み、数々の賞を受賞されています。そもそもウェルビーイングに力を入れるようになったきっかけは何だったのでしょうか。
青井さん:実は経営危機に起因しています。私が社長に就任したのは2005年。このとき当グループは上場以来初の赤字決算を2回記録し、その後、いつ買収されても不思議ではないような状態が続きました。結局は7年かかって業績を回復できましたが、この間、私は危機に陥った原因を正確に認識しなければ根本的な解決にはならない、と考えたのです。
内田:そこで何が見えてきましたか。
青井さん:危機を招いた最大の原因は、財務や戦略ではなく、企業文化や風土だったということです。過去の成功体験から抜け出せず、業績至上主義に陥り、お客様、株主などのステークホルダーの声に耳を傾けなくなっていました。
内田:それを変えようとされたのですね。
青井さん:そうです。言わば、病んでいた企業文化に健全さを取り戻そうと考えました。ですから社員一人ひとりの健康も大切ですが、組織そのものを健康にしなくてはと考えたのです。
内田:「健康経営」ではなく「Well-being経営」と表現するようになったのも、それと関係していますか。
青井さん:ウェルビーイングを推進するうえでキーパーソンとなったのが、13年ほど前に当社に専属産業医として来られた小島玲子さん(現取締役・上席執行役員 CWO、ウェルビーイング推進部長)です。たまたま食堂で話していたら、小島さんは、「一人ひとりがやりがいを持って働ける活力のある組織を作りたい」と言われた。これは私の思いとぴったり重なっていましたから、ぜひやりましょう、と。そこから二人三脚で進めてきました。当時は「健康経営」が一般的な呼び方でしたが、それだともう一つ、しっくりこないわけです。しかしあるときWHO(世界保健機関)の、「健康(Health)とは、単に病気でないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にある(Well-being)ことである」という定義を見て、これだと思い、そこから「ウェルビーイング」を使うようになりました。
内田:なるほど。この方針は自然に社内に浸透していきましたか。
青井さん:自然に浸透した一方、社会的潮流として広めていけたら、と考え、積極的に取り組んでいきました。

働きがいはフローが決め手
フロー状態がやりがいにつながる
内田:肉体的な健康は、健康診断のように客観的な指標で判断できますが、精神的、社会的な幸福感は人によって異なりますからなかなか判断がむずかしいのではないでしょうか。
青井さん:確かに幸福の定義は人によって異なり、一律には決められません。ただ、どのような条件が整ったときに幸福感を得られるかはある程度共通します。これには二つの条件があって、一つは個人が多くの選択肢を持てること、もう一つはそれに対して自己決定できることです。また企業としての取り組みですから、目指すのは仕事におけるウェルビーイングが中心となります。では、仕事において幸福ややりがいを感じるためにはどうしたらよいのか。これはフロー状態に入れることが大きいと言われます。フローとはハンガリー出身の心理学者チクセントミハイ(※1)が提唱した概念で、何かに夢中になっている、没頭している状態のこと。スポーツではゾーンに入るという言い方がありますが、これに近いですね。
内田:仕事を通じてフロー状態に入れる社員が多いと、幸福度の高い組織になるということですね。
青井さん:そうです。特に現在の自分の能力より少し高い能力を必要とする挑戦をすると、フローになりやすい。そこでそういう機会を増やそうと考えました。
内田:具体的にはどのような施策を行ったのですか。
青井さん:まずはアンケートや質問表によって、能力と挑戦を定量化し、そのバランスを調整していきました。ウェルビーイングには、主観的ウェルビーイングと客観的ウェルビーイング(※2)がありますが、近年は特に本人が幸せや充実を感じているかという主観的ウェルビーイングの重要性が言われるようになっています。その測定に力を入れました。
内田:調査にも工夫が必要ですね。
青井さん:そうです。10年以上に亘って毎年、社員のストレスチェックをしているほか、任意で、基本27、拡大版では70以上の質問をして確認します。職場で能力を発揮できていますか、仕事の中で挑戦する機会がありますか、といった質問を重ねていきます。
内田:そうした施策を続けてこられて、現在の社員の能力と挑戦のバランスはどうなっていますか。
青井さん:縦軸に挑戦の度合いを、横軸に能力をとってグラフ化してみると、能力と挑戦のどちらも発揮している領域にいる社員、つまりフローに入れる社員は、全社員の42%ほどになります。また非常に高いレベルで両方を実現できている超フローと言える社員は約4%です。当グループでは今の42%を2030年までに60% 以上にすることを目標としています。
手挙げ文化を醸成する
内田:フローに入る社員を増やすための施策としてはどんなことがありますか。
青井さん:能力、挑戦のどちらも大切ですが、特に挑戦が重要です。しかし伝統的な日本の企業文化では上意下達が普通で、当グループでもその傾向が強かった。これが行き過ぎると、指示を待つ受け身の姿勢になってしまいます。自ら判断しないから、進化やイノベーションも起きにくい。
内田:上からの指示・命令がなくても自律的に動ける文化にしていくことが大切というわけですね。
青井さん:そうです。言われなくても自ら主体的にビジネスに参加できる企業文化を作りたい、と考えました。これが「手挙げの文化」です。それを醸成するために8つほどの施策を打ちました。
内田:いくつか紹介していただけますか。
青井さん:従来、経営幹部だけが参加していた中期経営推進会議を希望者なら誰でも参加できるものに変えました。また、多様性の推進などといった本業とは異なる社内横断的活動に希望者が参加できるようにしました。それに続いて、昇進や部署異動に関しても手挙げを反映させるようにしました。また、失敗をのびのびと語れるようでなくては挑戦はしにくいですよね。そこで失敗を許容し、挑戦を奨励する文化を定着させようと、2022年に『フェイルフォワード賞』を始めました。挑戦による失敗をあえて讃える賞です。
内田:なるほど、前のめりの失敗なら胸を張ってよいということですね。
青井さん:失敗しても、そこから学んだことを共有すれば、新たな知識やノウハウにもつながります。それもあってフェイルフォワード賞の発表は人気セッションになりました。また、挑戦は数をこなすことも大事です。新規事業立ち上げなどの挑戦を打席に立つことにたとえ、2030年までに個人やチームで5000打席に立つことを目指しています。打席数を増やすことと失敗を恐れない姿勢をセットで考えているのです。
内田:打席数を増やす意味でもフェイルフォワード賞は効果的ということですね。ただ、どういう活動をチャレンジと規定するかは結構むずかしいところではないでしょうか。
青井さん:そこはおっしゃる通りで、現在、これまでのチャレンジの具体例を調べながら、整理しているところです。
内田:さまざまな制度や施策を通じて、手挙げ文化はスムーズに広まっていきましたか。
青井さん:最初から全員とはいきませんでした。まず手を挙げたのは若手社員が多かったですね。多くの人がそうだと思いますが、学生時代は夢や志や理想を持っていても、社会人になると一旦それらを傍に置いて、現実の場に対応することになります。それでも内心では、志を活かしたり、社会に影響を与えられる場があったら参加してみたい気持ちは持っているのでしょうね。だから手が挙がったのだと思います。
内田:なるほど。入社して年月を重ねてしまうと、なかなかそうはいかないということですね。
青井さん:少し先輩の社員は、手を挙げた若手社員を遠巻きに見ているんですよ。で、若手社員たちが何らかの活動をして楽しそうに戻ってくる。すると、だんだんそれに影響されて先輩社員も手を挙げるようになっていくんですね。
内田:若手社員の上にいる管理職がこれを許容する風土はあったのでしょうか。
青井さん:これについてはイエスともノーとも言えます。若手社員を応援する気持ちは彼らにもあったと思います。しかし、それが自分の評価につながらないと積極的に応援しづらいことも確かです。そこで、ほぼ業績(パフォーマンス)のみだった従来の評価に加え、自身の成長やチームへの貢献につながったかを見るバリュー評価も設定しました。この二軸で評価するようになってから、上司も若手社員の手挙げを応援する流れになったと思います。
内田:評価の方法を変えることで、手挙げ文化も促進されたということですね。
青井さん:ええ。これに近いものとして、グループ間の職種変更や異動を奨励する制度も設けました。当グループには、小売、フィンテック、物流、ネット通販、不動産、証券、ビルマネジメント、商業空間プロデュースなど、多種多様な事業があります。採用面接のときに、学生に応募動機を尋ねると、この会社はいろいろなことにチャレンジできそうなので、多様な経験をして時間をかけて成長したい、という意味のことを答える人が少なくありません。その発想は私たちの考え方とも重なりこの制度を設けたのです。
内田:実際にどのくらいの数の社員の方々が職種異動されたのでしょうか。
青井さん:過去8年間で、社員の約80%が職種異動を経験しています。また異動した社員の約85%が成長を実感しているという結果が出ています。

能力と挑戦の最適バランスを追求
自ら実験台となって社会にインパクトを
内田:丸井グループでは、組織として自らが実験台となり「社会課題解決企業」へ挑戦することを掲げていますね。この「実験台」という表現には、どのような思いがあるのでしょうか。
青井さん:日本には三千数百社の上場企業がありますが、その中で当グループは中規模クラスです。時価総額でも5000億円ほどで、1兆円規模の大企業と1000億円規模の企業の間くらい。グローバル企業ではないし、専門領域に特化した企業でもありません。しかし企業として世の中に存在感を示したい、社会にインパクトを与えられる企業になりたいという思いはありました。そこで、自らを実験台にして新しい経営を実践してみせることで、少しでも社会に変化を起こすことができたら、と考えたのです。前述した小島さんをCWO(Chief Well-being Officer)に任命し、執行役員として取締役会に迎えたのは、その象徴の一つでもありました。
内田:企業の価値を経済的側面だけでなく広くとらえて、社会全体に良い影響を与えようと考えているのですね。
収益と社会的インパクトの二項対立を乗り越える
社会実験を通じて、収益と社会的インパクトの両立をめざす
青井さん:社会実験を通じて、収益と社会的インパクトの両立をめざしています。そのために、現在は財務 KPIとインパクトKPIの二つの指標を設けて取り組んでいます。
内田:この二つは自然にうまくつながりましたか。
青井さん:残念ながらそう簡単にはつながりません。ですからここには相当知恵を絞っています。大切なのは当グループの強みやリソースを最大限に活かすこと。数多くの社会課題の中で、当グループならではの強みを活かせば解決できそうなものを探り、しかも、まだ実現したことがないビジネスモデルを構築すれば、二項対立を乗り越え、収益と社会的インパクトを両立できると思います。
内田:今後、注力したい取り組みはありますか。
青井さん:二つ挙げたいと思います。先ほど述べたフローの概念は、基本的には社員一人ひとりを想定していますが、ビジネスはチームで動かす営みなので、創造的な、成果を上げられるチームづくりに取り組みたいですね。チームとしてのフローの探究とも言えます。もう一つはこれに関係しますが、個人の苦手や弱みを他のメンバーが共有して補い、苦手や弱みに起因する失敗を減らしていく、そういうチーム運営方法を開発したいですね。
内田:今、ウェルビーイングを自社の施策に反映させたいという経営者の方々も少なくないと思います。そうした方々にアドバイス、メッセージがありましたらお聞かせください。
青井さん:経営にもトレンドがあり、ウェルビーイングに限らずさまざまなキーワードが登場します。そうしたキーワードに振り回されず、それが出てきた背景や普遍的な理由を考えることが大切ではないかと思います。言葉の表面を追うのではなく、本質をとらえて自社なりに定義し直し、実行すれば、多くの人の共感を得られるでしょう。当グループのウェルビーイング経営の実現も、そうした模索や探求の成果だったと感じています。
内田:本日は貴重なお話をありがとうございました。
(※1) チクセントミハイ:ミハイ・チクセントミハイはハンガリー出身のアメリカの心理学者。 フローの概念を提唱、研究し、いわゆるポジティブ心理学の創始者の一人となった。
(※2) 主観的ウェルビーイングと客観的ウェルビーイング:主観的ウェルビーイングは個々人の感覚や認識でとらえているもの、 客観的ウェルビーイングは生涯賃金、GDP、平均寿命など客観的数値で測定できるものを指している。
ウェルビーイングはここ数年で一気に脚光を浴び始めた概念ですが、まだまだ健康経営という枠を超えたウェルビーイングの本質に迫る経営ができている企業は多くはありません。青井社長のお話からは、人がどのようにして輝けるかという深い人間理解と、企業が社会に果たすべき真の役割と価値を見極められていることが理解できました。だからこそ、本質的なウェルビーイング経営を実現されているのだと感じます。今、ポストSDGsはウェルビーイングであると言われ始めています。人間一人ひとりにとって、そして社会・地球にとって、ウェルビーイングな経営を実現するべく、本対談をご参考にして頂けたら幸いです。(内田)