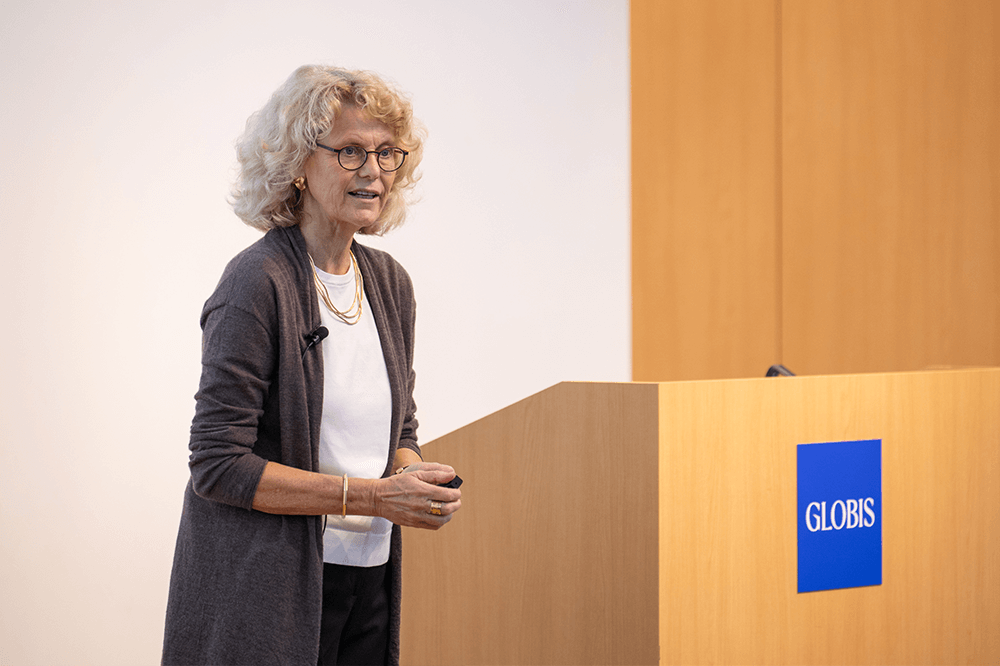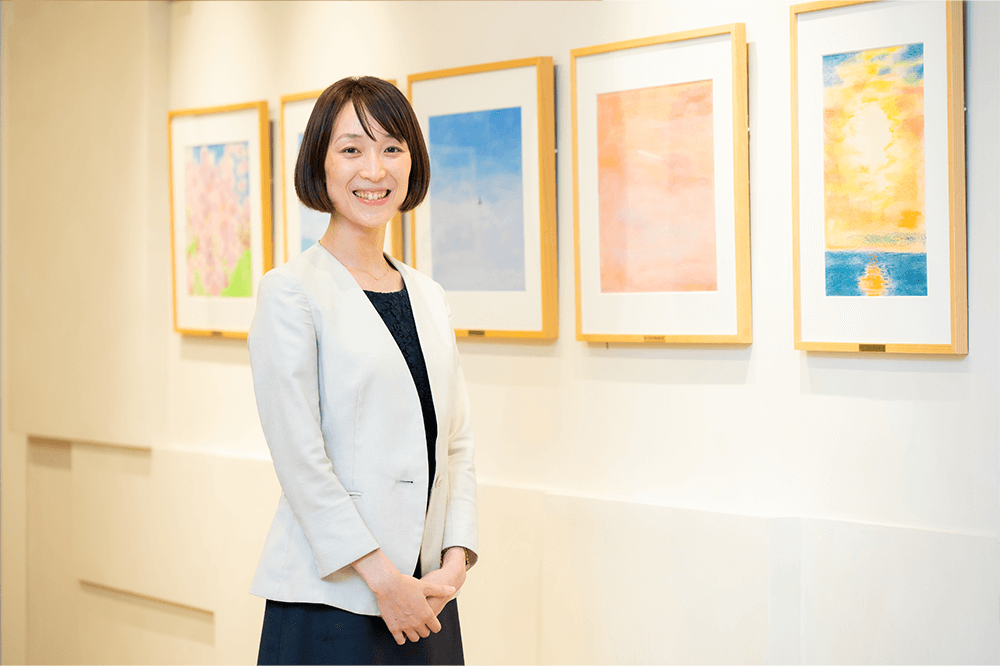- グローバル・D&I
- 経営人材
多国籍人材に対する育成施策のコツ
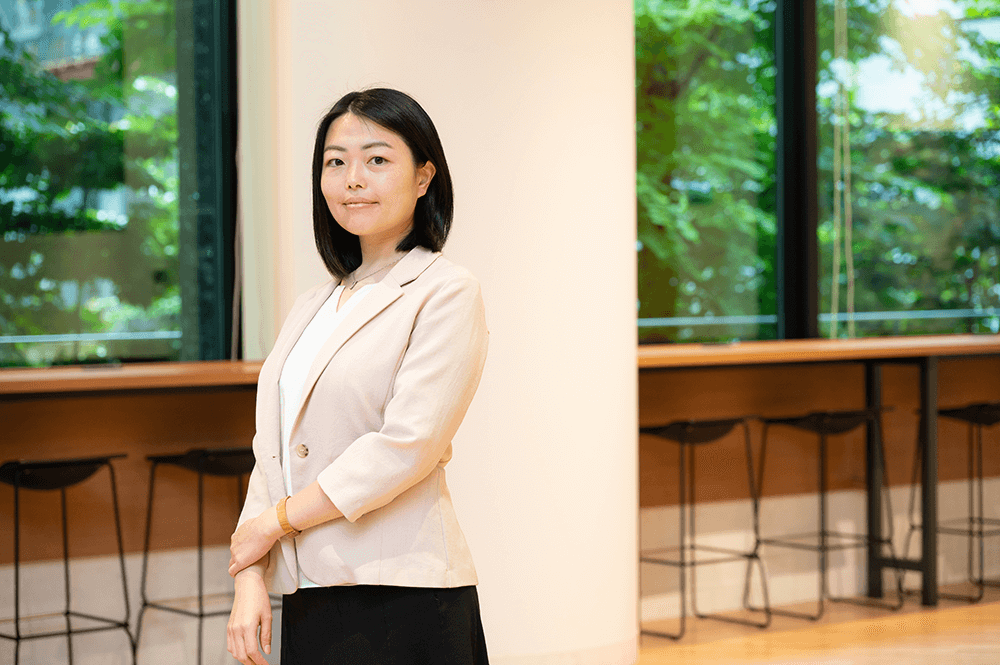
グローバル人材に対して研修を行う際、日本国内で成功した育成施策をそのまま多国籍人材に適用してしまうケースがみられます。しかし、文化や前提条件が異なるなかでの「言語を変えただけの横展開」は、しばしば期待通りの成果に結びつきません。
そこで今回は、多国籍人材を対象とした育成施策を担う際にはどのようなことを考慮すべきなのか、具体的な視点と配慮のポイントを解説します。(本コラムは、「企業と人材」2025年11月号の連載記事を一部編集のうえ、掲載しています)
「内面的な差異」への配慮が重要
多国籍の人材を育成施策の対象とする場合には、考慮すべき変数が増え、複雑性が高まります。最もわかりやすいのは、第一言語や得意言語の違いです。日本人を対象とした育成施策であれば、ほとんどが日本語を第一言語としているので、事務局・受講者・講師間の意思疎通を円滑に進められるでしょう。一方で多国籍人材を対象とした場合、全員が共通の言語を得意としているとは限りません。そうなると、同じことを言っても伝達度合いが90%、80%と落ちてしまいます。時には、誤った解釈をしても、そのことに当事者自身が気づかない可能性もあるのです。また、時差対応の必要性も生じます。オンライン研修で全世界から参加する場合、全員が業務時間内にそろうことは不可能なため、各地域との調整が必要になります。こうした「表面的な違い」は、比較的イメージがしやすいのではないでしょうか。
しかし、実は見落としてしまいがちな「内面的な差異」への配慮こそが、成果を左右する重要な要素となっています。そこで、ここでは特に注意すべき3つのポイントを「LCC」としてご紹介します。
3つのポイント「LCC」
①Learning Style:学習スタイルの差異を考慮できているか?
最初の「L」は「Learning」(学習) についてです。
孔子式とソクラテス式といった表現もされるように、西洋と東洋では学習スタイルが大きく異なります。例えば、日本を含むアジア圏は年長者からの教えを素直に受け止めようとする一方で、欧米圏は議論をベースにした意見交換から学ぶ傾向がみられます。このような違いがあるため、「受講者の発表内容に対して講師が何度もフィードバックを行い、アウトプットの質の改善を目指す」といったプログラムは、アジア圏のメンバーには受け入れられても、欧米圏のメンバーには理解が得られない可能性があるのです。つまり、受講者の学習スタイルが多様になることで、企画側があたり前と思っていたプログラムのデザインも、受講者にとっては居心地の悪い設計になってしまう恐れがあります。
多国籍人材を対象とする際には、参加者のバランスをみながら、プログラムデザインの調整を行うことが必要です。加えて、プログラムの冒頭に、事務局やプログラムディレクターから「文化の差異によって学び方が異なる」ことを言及し、どのような意図でプログラムがデザインされているか丁寧に説明することをお勧めします。
②Career Ownership:自らのキャリアに対する主体性の差異を考慮できているか?
次の「C」は「Career」(キャリア)に関することです。
「企業が従業員に投資し、研修の機会を与える」というと、日本では、従業員の成長やキャリア開発を支援しているとポジティブに受け止められやすいものです。一方で文化圏によっては、個人がキャリアオーナーシップを高く有するがゆえに、企業から提供されるトレーニング・プログラムに招かれるのは、不足しているスキルを補うためだと解釈されてしまう場合もあります。
このように、能力開発について、雇用主が支援することが一般的な文化圏もあれば、個人の責任であると考える文化圏もあります。そのなかで「研修に招くことはポジティブである」という前提で企画してしまうと、対象者によっては「何のためのプログラムなのか?なぜ対象に選ばれたのか?」と、意に反してネガティブに受け取られる可能性があります。「企業による人材育成」に対する受け止め方はさまざまであることを理解し、企画側からの丁寧な事前コミュニケーションを行うことが必要です。
③Cultural Difference:生活スタイルや信条の差異に十分配慮できているか?
もう一つの「C」は、「Culture」(文化)に関する差異です。
食べられる食材が限られていたり、勤務時間中に祈祷の機会を設けるなど、考慮しておかなければならないことがあります。また、文化圏が同じでも、究極的には個々人で異なります。そのため、適切な対応を行うには、一人ひとりに「何を配慮できるとよいか?」を丁寧に確認する必要があります。
世界中から参加者が集まるイベントでは、全参加者に事前アンケートでベジタリアン、ハラール(イスラム教の食事規定)、食物アレルギー、グルテンフリーといった希望を細かく確認するケースもみられます。中国はお茶文化のため白湯を求める人が多いのですが、必ずしも全員がそうとは限りません。各文化に対する事前知識を得ることは重要ですが、その思い込みだけで進めてしまうと、受講者の期待にそぐわない対応をしてしまう可能性があります。手間はかかりますが「事前に直接、配慮の希望を確認する」という心がけが重要です。
多国籍な人材を対象とした育成施策では、考慮すべき変数の多さに戸惑うこともあるかもしれません。しかし、こうした文化的多様性を踏まえた丁寧な育成設計は、企業の人的資本経営における重要な基盤にもなります。特性の違いを楽しみながら、国・地域を越えて活躍するグローバル人材の育成にチャレンジしていきましょう。