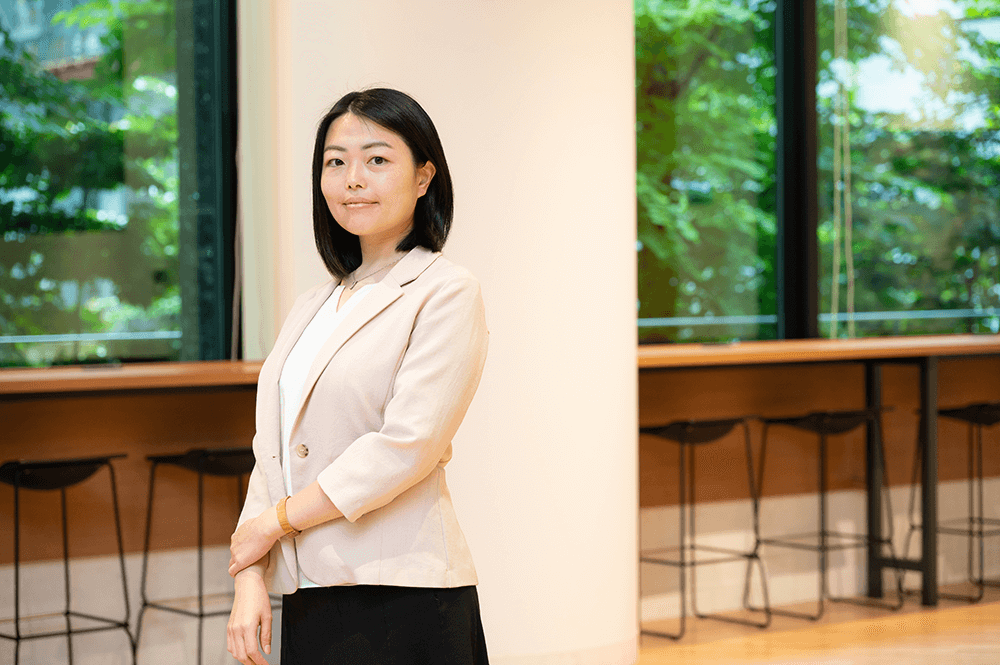- 経営人材
正解なき時代に、経営幹部の「覚悟」をいかに育むか~経営者育成の現場から考える、認識変容のステップ~

経営環境の変化は、いまや予測不能なほど加速しています。市場や技術の動向は数年先を見通すことが難しく、経営者は常に「正解のない問い」に直面しています。 こうした時代において、経営者や経営幹部を育てていくには、何が必要でしょうか。従来のように、経営知識や高度なスキルを身に付けることは必要条件ですが、それだけでは複雑な現代に応えきれないでしょう。それ以上に求められるのは、自らの認識を揺さぶり直し、リーダーとしての使命や覚悟を言葉にする力、そして揺るぎない自らの“経営の軸”を育てることです。
グロービスの経営幹部向けプログラム「知命社中」では、異なる業界のリーダーたちが半年間の対話を通じて、「私は何者か?」「経営者としての使命は何か?」といった根源的な問いに挑みます。その過程で培われるのは、肩書や役割を超えて、自らの使命を引き受ける覚悟です。こうした覚悟は、困難な局面でも折れずに踏みとどまる経営者としての胆力につながっていきます。
本コラムでは、プログラムディレクターを務める筆者が、これまで数多くの経営幹部と対話を重ねてきた経験をもとに、経営幹部としての覚悟がいかにして育まれるのか、具体的なストーリーを交えて変容の軌跡をお伝えします。
「覚悟」とは、不安を抱えながらも前に進むこと
「正義のために、矢面に立つ覚悟はあるか」。
これは知命社中の最終セッションで、ある経営幹部が口にした一言です。一見すると力強い言葉のように聞こえますが、私が心を動かされたのは、その言葉の奥に漂う迷いや不安でした。
「自分の視座の低さや、経営幹部として迂闊に過ごしてしまった悔いがある。これからは“組織はリーダーの器次第”だという自覚を持って本気で思って生きていく。しかし、自分にそれができるのか…本当は不安もある」
本人から発せられたこの吐露に触れたとき、私は改めて、「覚悟」の本質について考えさせられました。
一般的に「覚悟」という言葉には、確信や動じない「強さ」のようなイメージを持たれます。しかし実際には、覚悟とは確信の中にあるのではなく、「わからなさ」を抱えながらも一歩を踏み出そうとする姿勢そのものに宿るものです。経営の現場では、未来を完全に予測することは不可能でしょう。それでも決断を先送りすることは許されません。経営者に求められる「覚悟」とは、揺らぎや迷いを抱えながらも前に進む姿勢そのものなのです。
役割としての義務から「私の選択」へ──覚悟の転換点
この三年間、私は知命社中を通じて、大企業から中小企業まで様々な経営幹部と対話を重ねてきました。その中で、多くの方が最初に口にするのは、次のような言葉です。「なぜ自分が経営幹部に選ばれたのか、正直わかりません」、「経営者になりたかったわけではないし、偉くなろうとも思っていませんでした。」
実績と評価を積み重ねるなかで、気がつけば重責を担う立場に立っていた──実は、自分でその場所を「選んだ」という実感を持てずにいるリーダーは少なくありません。目標達成や役割遂行といった外的基準に拠ってきたからこそ、役職が変わると「何を基準に意思決定すればよいのか」「自分は何者としてここにいるのか」が曖昧になり、存在意義を見失いやすくなるのです。
しかし、半年間のプログラムの終盤に差しかかると、「ようやく、自分の“覚悟”が定まった気がする。」と多くの方が語りだします。その覚悟とは、役職や肩書きによって義務感から発せられるものではなく、「自分の人生として、この役割を引き受ける」という実感を伴っています。「会社から任された役割」から「私の選択」に切り替わったとき、経営者としての覚悟が芽生えていくのです。
「私は何者か?」自身のアイデンティティに向き合う
では、経営者としての覚悟を生むためには、何が必要なのでしょうか。その出発点となるのは、自らの根源的な問いに向き合うことだと言えるでしょう。たとえば、次のような問いが挙げられます。
・私は何者なのか?
・私は何を成し遂げようとしているのか?
・私は組織や社会に何を遺すのか?
これらはスキルや能力の話ではなく、自身のアイデンティティそのものを考える問いです。人は誰しも、矛盾や未熟さといった人には見せたくない側面を抱えています。「視座が低かった」「短期的な成果ばかりに囚われてしまった」といった反省に直面することもあるでしょう。そうした現実から目をそらさず、自分の弱さや未完成さをも引き受ける過程で生まれるのが「自己受容」です。
自己受容とは、単に「自分を肯定すること」ではありません。できない自分、不完全な自分をも受け止めた上で、「それでも前に進む」と覚悟することを意味します。自己受容を通じて培われた覚悟は、変化や失敗に直面しても折れず、揺るぎない強さを持っています。
成功と目的を捉え直すことで、覚悟は強固になる
こうした問いに向き合い、自らの未熟さも含めて受け入れるプロセスの中で、「自分は何に応えようとしているのか」という感覚が輪郭を帯び始めます。この「目的との接続」こそが、覚悟の出発点となるのです。
一方で、「何に応えようとしているのか」という目的に向き合うとき、私たちは同時に「何をもって成功とするのか」という価値判断と正面から向き合わざるを得なくなります。多くのビジネスパーソンにとって、成功とは「与えられた目標を達成すること」でした。しかし、経営者の立場に立つと、それだけでは足りなくなる瞬間が訪れます。「誰に、どんな意味で、どれだけ貢献できたか」――改めて「“成功”とは何か」を再定義することが、覚悟をさらに強める鍵となるのです。
私が出会ってきた経営幹部の方々は、成功を次のような“層”で捉え直していました。
・経営者としての責務を果たす(成果・責任)
・人や組織にポジティブな影響を与える(つながり・共創)
・社会課題の解決や未来の創造に貢献する(使命)
大事なのは、これらの層を順に積み重ねるのではなく、状況に応じて往復しながら、「自分は今、どこに立っているのか」を問い続けることです。覚悟はまさに、このような問い直しの中で磨かれていきます。
「揺らぎ」の経験が、認識をアップデートする
では、実績や評価を積み重ねてきた経営幹部に対し、これまでの固定観念を揺さぶるようなきっかけを、どのように作るのでしょうか。その一つに、多様な「知のシャワー」を浴び、認知をアップデートする刺激を与えるという方法があります。たとえば知命社中では、約半年間を通じて、「経営者による講演から、葛藤や決断の軸を学ぶ」「経営の良書を味読し、偉大さと永続性を追求する経営の原理に触れる」「宗教や哲学の中にある普遍的な生き方に思いを馳せる」「現代アートの「わからなさ」に身を置き、異見を受容する」といった経験を提供しています。
こうした日頃の業務だけでは得られない外からの刺激が、成功や目的に対する認識を揺さぶり、アップデートを促すきっかけとなります。その「揺らぎ」の中から、変化に応答し続ける意志として、自分自身の覚悟が磨かれていくのです。
覚悟を育むには、仲間が必要
覚悟は、一人きりの孤独な内省から生まれるもの――そう思われがちです。しかし実際には、「覚悟は、仲間との探究の中でこそ育つ」ものと言えるでしょう。仲間とともに正解のない問いに向き合い、揺らぎや迷いを率直に語り合う中で、少しずつ輪郭が形成されていきます。
仲間との対話には三つの効用があります。
1.多様な視点に触れることで盲点が補正され、視野・視座が広がる
2.自分の考えを言葉にして発することで、意志が公になり、実行が支えられる
3.仲間の存在があることで、不安や迷いを抱えながらも続ける情緒的な持久力が得られる
多様な知に触れ、異業種の仲間と対話し、自らの未熟さや矛盾をも引き受ける──その積み重ねが、役職やスキルを超えたリーダーとしての覚悟を育んでいきます。
正解のない時代に新たな未来を切り拓けるのは、覚悟を持つリーダーだけです。迷いや揺らぎを抱えながらも歩みを止めない経営者、経営幹部を育てることが、企業の未来をつくる力につながります。本コラムが、経営者、経営幹部の育成を「知識や経験、スキルの習得」だけにとどめず、「自己認識を揺さぶり、覚悟を育む営み」として捉え、その機会を創り出す契機となれば幸いです。
<関連ページ>
「知命社中」について知りたい方はこちら