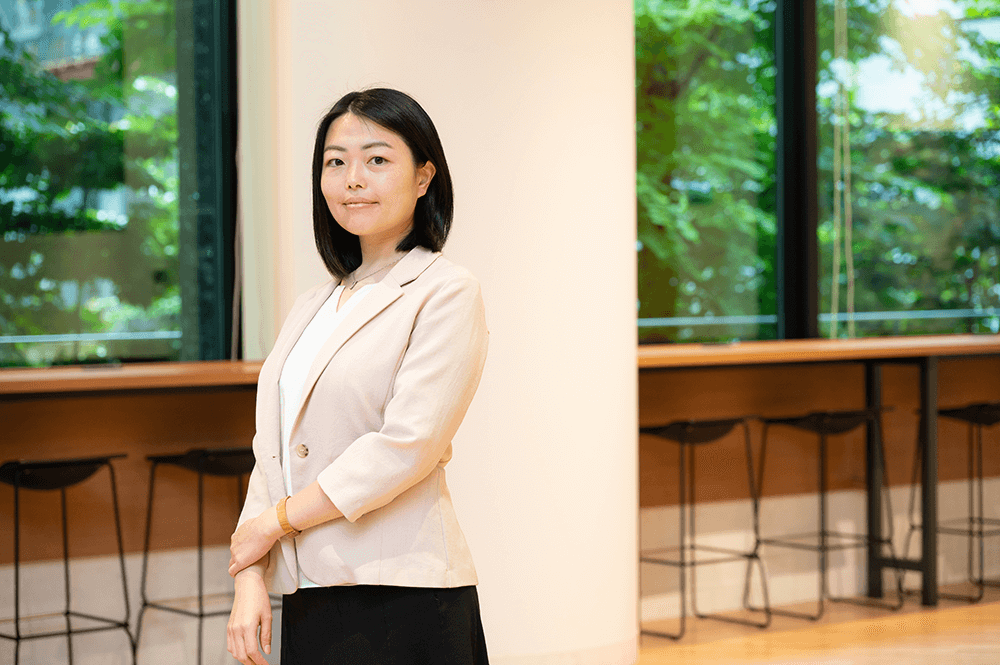- 経営人材
次世代リーダー育成研修のポイント

「人事の皆さんにとって、次世代リーダー研修は毎年実施するものかもしれません。でも、私たち受講者にとっては、この研修は人生でたった一度きりの、やり直しがきかない機会なんです」
これは、ある次世代リーダー研修の受講者からふと漏れた言葉です。企業・人事にとっては繰り返される育成プログラムの一つでも、受講者にとっては、かけがえのない時間。多くの人事の方が真摯に企画・運営されていると承知しつつも、この言葉は「ぐさり」と心に刺さるものでした。
本コラムでは、これまでの次世代リーダー育成の企画・運営から得た学びをもとに、受講者個人と組織が共に成長するために何を考えるべきかを考察していきます。
(本コラムは、「企業と人材」2025年8月号の連載記事を一部編集のうえ、掲載しています)
次世代リーダー育成研修の企画
次世代リーダー育成は、丁寧な設計から始まります。土台作りが成功のカギを握ります。ここでは、そのポイントを3点お伝えしていきます。
1.未来を見据えたあるべき姿とギャップの整理
次世代リーダー育成の出発点は「あるべき姿」の明確化です。これは、理想論ではなく、未来の経営を見通せるメンバーで具体的な認識を揃えるべく、丁寧に議論を重ね描く必要があります。「何年後にどのような役職を担う人材が必要か」「そのために、今どのようなスキルやマインドを身につけるべきか」問いはシンプルですが、その答えを出すのは容易ではありません。未来は不確実です。また、経営視点を持たずに議論すると、目の前の課題に引きずられたスキルアップに終始しがちになるからです。
一方で、すべての未来が不透明なわけではありません。人口動態、法改正、気候変動といった“確実に来る未来”はある程度予測ができます。こうした前提と、企業のビジョンや経営計画も踏まえ、今後求められるリーダーの「あるべき姿」を描くことが準備の第一歩です。その上で、現状とのギャップを明らかにし、経営に近いメンバーも交えて深く議論することが不可欠です。
2.育成の目的・ゴールの綿密なすり合わせ
「あるべき姿」が描けた後はすぐに育成プログラムの設計に進みたくなりますが、その前に育成の目的とゴールを、受講者が所属する各部門の役員や上長といった関係者間で綿密にすり合わせることが必要になります。また、目的とゴールの共有は、プログラムの設計段階だけでなく、受講者への参加依頼時、研修の開始時、中間、終了時に至るまで、繰り返しすり合わせることが求められます。
関係者が多くなるほど「次世代リーダー育成」に対する期待はばらつきます。ゴール設定が曖昧なままでは、「思ったより成長していない」「何のための研修だったのか」といった不満が、関係者や受講者から噴出してしまうリスクが生じます。育成の目的とゴールを“共通認識として握る”ことが研修を成功に導く鍵となります。
3.対象者の丁寧な選定
対象者の選定も重要なステップです。次世代リーダー候補となる人材は、業務に対する期待役割が大きく、多忙を極めていることが多いでしょう。半年~1年と長期にわたる研修との両立には相応の負荷がかかります。
だからこそ、「仕事と両立できる精神状態であるかどうか」「今、受講させるべきか」といった見極めが重要です。育成の目的が受講者の精神的な強さを見極めることであれば別ですが、そうでない場合、受講者の不調や離脱が生じれば、他の受講者にネガティブな影響を与えかねません。
また、研修開始後も、一人ひとりが真摯に研修に向き合えているか、人事が継続的に目を配り、必要に応じて個別にフォローすることが大切です。
次世代リーダー育成研修の実行
丁寧に準備を整えてきた後の実行段階でも細やかな対応が肝になります。細部への配慮が成功を左右するのです。そのポイントを2点お伝えします。
1.研修初日の「場づくり」
どのベテラン講師も「初日が一番緊張する」と口を揃えるほど、研修初日の空気は極めて重要です。初日で受講者の心を掴めるかどうかで、その後のコミットメント度合いや、プログラム全体の深度が大きく変わってきます。研修の意味合いを受講者自身が「腹落ちできるか」が成功の分かれ道です。そのため、経営や人事からの真摯なメッセージや、プログラムの意義づけを丁寧に伝え、受講者の意識に火をつける場をつくることが求められます。
2.受講者と人事の関係性づくり
受講者同士の関係性づくりはすでに考慮されていると思いますが、意外と見落とされがちなのが受講者と人事の関係性です。この関係に溝が生じると、研修全体に冷ややかな空気が漂い、せっかくの受講者の成長機会が形骸化してしまいかねません。
受講者は「お客様」ではありませんが、不満が出た時には真摯に耳を傾け、丁寧に対応することが求められます。受講者と人事がお互いにリスペクトし合える関係性を醸成することが、プログラムの効果を最大化する鍵になります。
ここまで、次世代リーダー研修の企画・実行におけるポイントを、これまでの経験をもとに整理してきました。次世代リーダー研修は、多くの関係者の思いや期待が交差するがゆえに、ときに迷いや戸惑いを伴うこともある取り組みです。それでも、試行錯誤を重ねながら向き合い続けることが、受講者や組織の成長を形づくる確かな一歩につながっていきます。