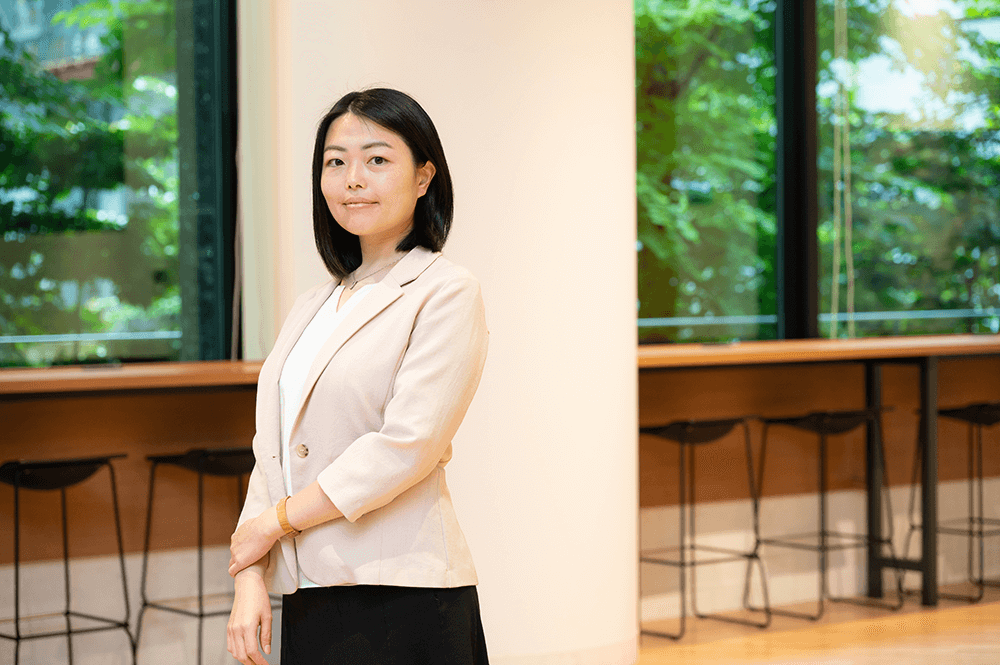- 経営人材
これからの若手育成のあり方

人事・人材開発分野のトピックは多岐にわたります。この連載では、人材育成や組織開発に携わる皆さまの実務に役立つ具体的なヒントを提供していきます。今回は、「これからの若手育成のあり方」です。(本コラムは、「企業と人材」2025年5月号の連載記事を一部編集のうえ、掲載しています)
「若手育成」を巡る幻想と現実
今ドキの若手(Z世代)社員の特徴は何でしょうか?「経済的成長より社会貢献を重視」「定年まで勤める意識は薄い」「会社への貢献を重要だと思わない」といった言説を耳にする方も少なくないでしょう。しかし、パーソル総合研究所の「OJTに関する定量調査」では、今の新卒社会人は想定よりも経済的成長を重視し、長期雇用を希望し、組織への貢献意識も低くはないとの結果が示されています。
こうした食い違いの原因は単純で、「若手」を十把一絡げにとらえる解像度の低さです。社会貢献を重視する人もいれば、そうでない人もいる。「若手」などという存在は幻想であり、多様な個人が同世代に混在しているだけなのです。育成においても、目の前の「若手」個人の志向やニーズを解像度高くとらえ、対応する必要があります。
では、皆さまの組織における若手育成はいかがでしょうか?入社時研修は画一的になりがちで、個人の志向やニーズに対応するのが難しい場合も多いのではないでしょうか。また、それをOJTで補おうとしても、教える側である現場のミドル層が多忙で育成に十分な時間を割けない、ミドル自身が「背中を見て学べ」で計画的に育成されておらず、どう教えたらいいか見当がつかない、という状況に陥っている場合もあります。結果として、個人の志向やニーズを解像度高くとらえ育成するどころか、「いきあたりばったり」な対応になっているのではないでしょうか。
このような状況が続いてしまうと、若手、特に優秀層は成長実感をもてず、今後のキャリアに不安を抱え、退職を考えるようになるかもしれません。
「自ら育つ・学ぶ」環境を人事がつくる
「いきあたりばったり」な育成は、多くの問題点を孕んでいます。端的に整理すると、以下の4つが絡み合っていると考えられるでしょう。
①計画性のなさ
育成の営みが現場と人事で分断されており、新人期間が過ぎたら現場にお任せ。多忙な現場では、OJTも短期間かつ属人的になりがちで、結果として成長にバラつきが出る。また、次世代にも現状の問題が再生産されてしまうおそれが高い。
②偶発性のなさ
現業の知識・ノウハウのインストール(職務充実)がメインで、そこでの想定を超えた新たな職務拡大の機会が生じづらい。結果、若手の伸びしろ、成長の振れ幅が小さくなってしまう。
③余裕のなさ
上長や特定の先輩社員に負荷が集中している。結果、リソースが逼迫して改善もままならない。
④自発性のなさ
「教える側/教えられる側」「会社が若者を育てる」という関係性が前提になっており、「何もかも教わるものだ」と思考停止に陥ってしまう。結果、若手が自発的に学び、育つ土壌となりづらい。
上記のいずれも重要な問題ですが、人事としてはまず、「若手自身の自発性」について考えることをおすすめします。なぜならば、自発性は若手本人が有し、発揮するものであるとともに、環境や周囲からの働きかけによっても変わり得るものだからです。しかし、「自発的に成長せよ」と号令をかけるだけでは、「自発」からはほど遠く、若手に成長責任を丸投げするだけになってしまいます。
人事は、「会社が若手を育てる」でも「若手に成長の責任を丸投げする」でもなく、「若手自身の自発性を引き出し、自ら育つ・学ぶ状態を、いかに会社という環境を活かして支援できるか」という視点へのアップデートが必要です。
支援の際に留意すべき点は多々ありますが、私は「若手自身が最初の小さな具体的行動を起こしやすくするために、若手を仕組みや関係性のなかに埋め込むこと」が重要だと考えています。人事施策を用意しても、本人が行動しなければ意味がありません。しかし、最初から明確な目標や強い意思を持って自発的に行動できる若手は、そう多くないでしょう。小さい一歩でも行動を起こせば、成長の「弾み車」が回り始めます。学び、育つための最初の小さな行動につながる仕組みや関係性を、人事主導の打ち手として準備しておきたいです。
打ち手の一例としては、「部門や年代を超えた横断プロジェクトへのアサイン」「アクションラーニング研修を通じた提言」「部門を超えたメンター/逆メンター制度」「ロールモデルだけでなく、若手のやりたいことの実現機会を提供する支援者(スポンサー)の設定」などが考えられます。これらは、若手一人ひとりが組織内外の多様な人間関係を築く機会を得て、これまで接点がなかった人や業務に触れることにより、自らのキャリアや成長機会に気づくための「仕掛け」です。
もちろん、仕掛けを用意しただけでは十分ではなく、それを活用してもらえるよう、個人に照準を合わせた小さな後押しも必要です。例えば「君もどう?」といったように促す、勇気づけるなど、人事や上司、同僚からのフォローが考えられます。加えて、若手自身が経験を内省し、教訓化し、次の実践につなげていく経験学習サイクルの設計も重要です。
人事は制度や枠組みを作って終わりではなく、想定外の事象に対処しつつ、泥臭く現場と関わり合う「地上戦」が肝になります。現場で頑張る社員の皆さんを支援していけるよう、じっくりと考え抜いて泥臭く取り組む「いきあたり“バッチリ”」な育成を進めていきましょう。