新規事業のグロースに向け新戦略立案・実行に邁進。そのために必要な「経営の全体像」をMMPで学んだ

- インフラ/物流
- サービス業
- ミドル・マネジメント・プログラム(MMP)
- オンライン
- 事業部長として、自社の「第二の柱」を目指す新規事業の責任者を務める
- 経営会議で自分の意思が伝わらず本質的な議論ができない場面があり、「経営の全体像」を理解する必要性を痛感
- 書籍で断片的に知っていたフレームワーク同士の関係性を理解し、知識が「使える」状態に
- 多様なクラスの仲間と交流することを通して、自分のキャリアの現在地を改めて感じた
- 学びを生かし、競争が激化する市場において事業戦略を再構築。これから実行フェーズへ
- 情熱と客観的視点のバランスを取りながら、事業をグロースさせていきたい
背景と課題
自社の「第二の柱」となる新規事業の成長にコミット
2022年にウォンテッドリーへ中途入社し、企業の従業員エンゲージメントを向上させる「Engagement Suite」事業の責任者を務めています。この事業は当社の「第二の柱」を目指す新規事業で、立ち上げ直後から一貫して携わっています。
私が社会に出たのは、リーマンショックが起きた直後でした。新卒時に組織の急激な変化を目の当たりにした原体験から、人材領域で社会に価値提供することを志しました。前職までは採用サービスに携わっていたのですが、社員の定着や活躍、エンゲージメント領域のビジネスにも取り組みたいと思い、今に至ります。
経営会議で自分が意図した議論ができない苦悩
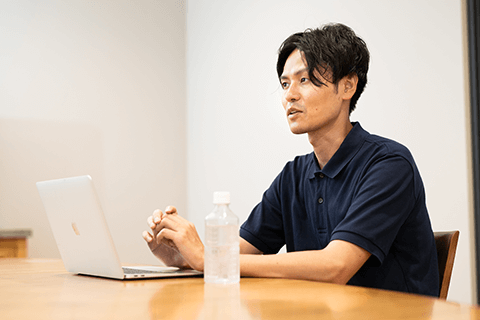
ミドル・マネジメント・プログラム(MMP)を受講したきっかけは、当社の人材開発制度です。対象者が社外で学べる制度があり、通学するスクールは自ら選ぶことができました。
数あるスクールの中からMMPを選んだのは、経営を体系的・網羅的に学ぶ機会を求めていたからです。事業部長として経営会議でCEOやCOOとディスカッションする中で、経営の全体像を理解していなかったり、自分なりに環境分析をしても論理が欠けていたりして、本質的な議論に至らないことが度々ありました。経営陣に自分の意思を伝え切るには、論点をぶらさずに話すことは必須であるにもかかわらず、消化不良のまま終わってしまう場面も多かったのです。我流であるがゆえに再現性にも乏しく、経営を体系立てて学ぶ必要性を感じていました。
MMPは、事前課題をもとにディスカッション形式で学ぶスタイルにも惹かれました。学んだことを即実践したいと思っていた私にとっては、座学ではなくアウトプットしながら学べる環境が最適だと考え、受講を決めました。
事前準備と受講内容
限られた時間で最大限のアウトプットを出す意識
MMPで学ぶ3か月間には経営会議や経営合宿など大きなイベントが予定されており、その前後は仕事と学習の両立が難しそうだと考えていました。そこで、休日にまとまった時間を確保し、予習をかなり前倒しで進めました。数回分を一気に予習することもありましたね。予習・受講・復習のサイクルをこまめに回すのが理想なのかもしれませんが、私の場合は、仕事が立て込んでいる時期でも、予習をきちんと終わらせてクラスに参加することを優先した形です。
1つのアサインメントにかける時間も、自分で決めていました。2時間で「悪くない」アウトプットを出すと自らに課し、仕事と同じように、限られた時間で最大限の成果を出すように心がけていました。
断片的に理解していた知識がどんどん繋がった
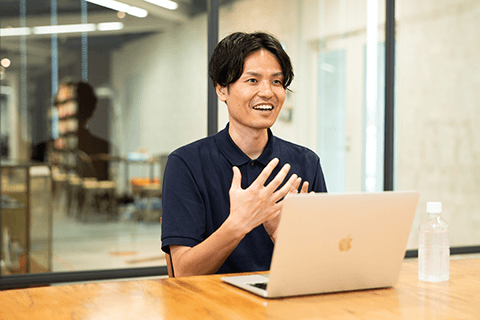
以前からビジネス書を多く読んでいたこともあり、予習時点で知らないフレームワークはほとんどありませんでした。ただ、予習をもとにクラスでディスカッションしてみると、個別の知識はあっても、「いつ、どういった場面でどのフレームワークを使うのか」「フレームワーク同士の関係性はどうなっているのか」を理解していなかったことを痛感したのです。
そこで、復習時に「経営の全体マップ」を自分なりに作成し、経営の各要素を接続して捉えるように心がけました。この取り組みが、経営の全体像が見えていないという自分の課題を乗り越えることに大きく役立ったのです。
受講して感じるのは、やはり独学だと知識が断片的になりやすいことです。ファッションで例えると、受講前の自分は、洋服をたくさん買ったものの、コーディネートができていない状態でした。個々の要素の関係性を理解してコーディネートができなければ、経営をリードできないのだと思い知りました。
自分のキャリアと現在地を確認できた
私はオンラインクラスを選択したので、全国各地、そして海外の受講者もいる環境で学びました。大企業でマネジメントをしている方、グローバルで活躍する方など、さまざまな環境でビジネスをしている方々とディスカッションする経験を通して、自分の現在地を感じる貴重な機会になったのです。クラスの中では私がほぼ最年少で、企業規模も小さいことがわかり、「年齢が若いうちから、チャレンジングな環境に身を置きたい」と望んでいたキャリアを今まさに歩んでいるのだと改めて実感しました。
成果と今後の展望
競合優位性を実現するために戦略を再構築
当初の期待通り、学んだことを即実践しています。受講中から、学んだことを経営会議の資料作成に取り入れ、クラスでも経営会議でもフィードバックをもらい、その気づきを次の機会に生かすサイクルを回せたことは、大きな経験になりました。感覚的に分析し提起していた状態を脱し、客観的根拠に基づいた判断をもって経営陣と議論できるようになったと感じています。根拠が不足していたとしても、立ち戻るべき「定石」があるので、議論においてきちんと“戦える”ようになりました。
担当事業の戦略を見直したことも、MMPで学んだからこそできた点です。我々が身を置く福利厚生市場は老舗企業が業界リーダーであり、後発である当社はユニークなポジショニングが必要になります。そこで、学びを生かして複数のKBF(重要購買決定要因:Key Buying Factors)を設定し、独自のポジショニングを確立しようとしているところです。競合の動きや新規参入企業をふまえ、劣位を解消するだけでなく優位を創出できるポジショニングを考え、営業戦略も再設計しました。これからいよいよ、新たな戦略の実行フェーズに入ります。
経営の定石があるからこそ、メンバーと共通認識を持てる
メンバーと共通認識をもちやすくなったことも、学びによる成果のひとつです。私と同時期にエンジニア部門のリーダーもMMPを受講したことで、事業戦略とプロダクト戦略を整合させる議論がしやすくなりました。機能開発の計画においても、事業成長に資する機能であるか、同じ判断軸で考えられるようになったと実感しています。
経営の定石に沿って環境分析し、事業戦略を立て、客観的な根拠をもとに説明することで、メンバーに納得してもらいやすくなったとも感じます。さまざまな立場の人に対してアウトプットする機会が多い中、経営の原理原則に基づいてコミュニケーションする重要性を実感する日々です。
「思い」と「客観性」のバランスを取って事業をグロースさせていきたい

今後も引き続き、担当事業のグロースにコミットしていきます。現状を俯瞰し、何をすべきかを導き出せるようになった今、事業家として戦略を確実に「実行」すべき局面にあると考えています。
既存事業が強い当社で「第二の柱」となるビジネスを育てるには、責任者である私の「やりたい」という思いが先行しすぎるのは好ましくありません。メンバー全員が納得して事業に向き合うために、会社のミッション・ビジョン・バリューと整合する事業戦略が必要です。また、0から1を生み出すフェーズではリーダーの情熱が重要ですが、成長期においては客観的な根拠に基づいて日々の判断を行い、事業を伸ばしていくべきだと考えています。「Engagement Suite」事業は、成長期に差し掛かっています。MMPで学んだ環境分析や戦略立案スキルを生かし、思いと客観性のバランスを取りながら事業の舵取りをしていきたいですね。
私自身のキャリアとしては、今後も人材領域で価値を発揮していきたいと考えています。そのために、人事・組織分野を専門機関で学ぶことも検討中です。これからも自己成長し続け、大企業だけでなく、ベンチャーやスタートアップで活躍する方々とも一緒に日本を元気にしていけるといいなと思っています。
▼橋屋さんがMMPでの受講体験を綴ったブログはこちら
