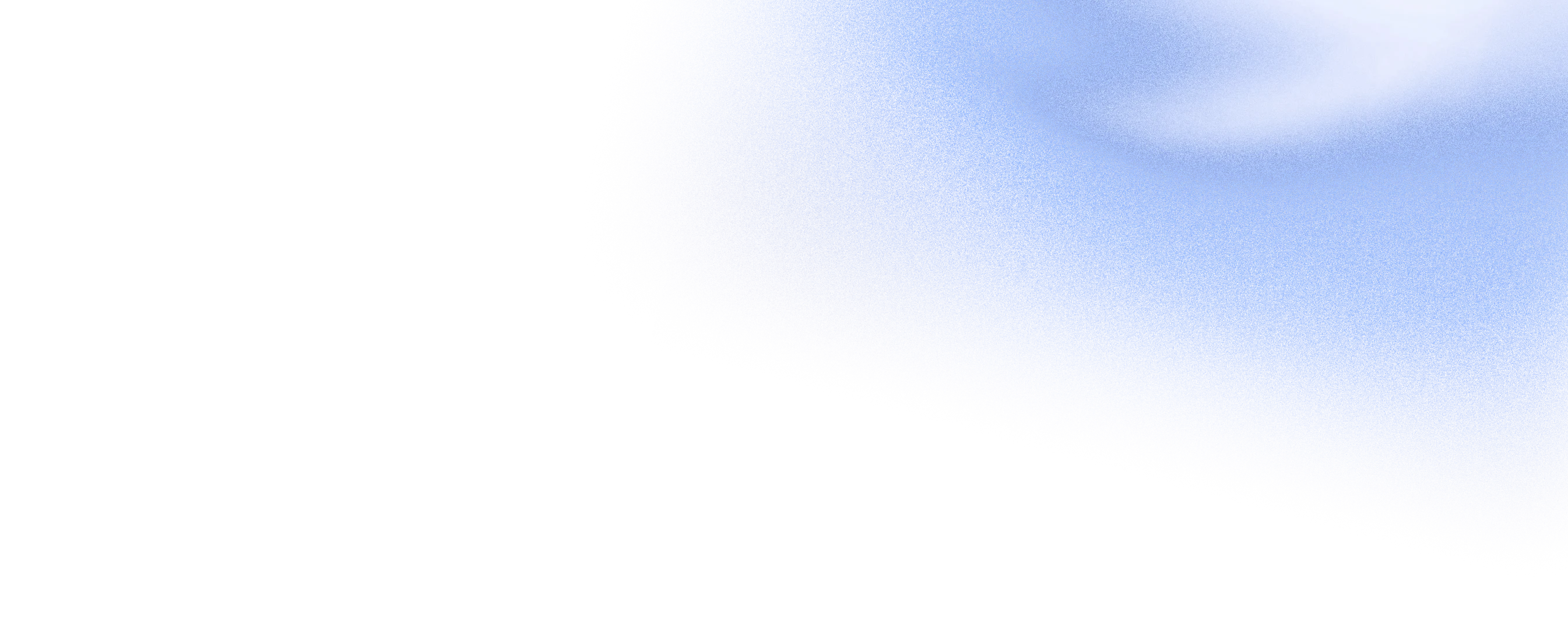

心の健康を守り、生産性の高い職場を作る
「ストレス放置はNG。周囲と自身の心の不調に気づいていますか?」
メンタルヘルスは、働く人々の心の健康と活力を維持し、生産性の高い職場環境を築くための重要な基盤のひとつです。近年その必要性が広く認識されるようになりましたが、「具体的に何をすべきか」を理解している人はまだ少ないのが現状です。
働く人々のモチベーション低下を防ぎ、職場の生産性を上げるためには、マネジャーやリーダーがメンタルヘルス対策について学ぶ必要があるでしょう。
当科目では、職場におけるメンタルヘルスの基礎から具体的な実践方法まで、社会人として知っておくべきメンタルヘルスの基本を学びます。ラインケアやセルフケア、ストレス管理、そして経営リスクとしてのメンタルヘルス問題など、ビジネス環境だけでなく日常生活にも応用できる知識とスキルを身につけます。
科目の構成
学びのストーリー
業務改革部のマネジャーとなった「あなた」は、部下である尾崎さんがメンタル不調になったことに戸惑いながらも、それをきっかけにマーケティング部の藤本早紀さんと共にメンタルヘルスに関する基本的な知識や企業への影響とその対応について学びます。
-
遅刻が増え、話しかけても元気のない様子の部下が。メンタルヘルスは大丈夫か?
-
職場の管理監督者にできるケア、何がある?
-
メンタル不調にならないために、自分自身でできることには何がある?

第1章 職場のメンタルヘルス
メンタルヘルスの基本的な知識を学ぶと共に、企業にとってメンタルヘルスが如何に重要であるかを学びます。
- メンタルヘルスとは
- うつ病
- 企業経営上のリスク
- 安全配慮義務違反
- 管理職への影響
第2章 ラインケア
職場でのメンタル不調のメンバーと向き合う上で、管理職が求められる具体的に対応について学びます。
- ラインケアとは
- 管理職に求められる4つの行動
- 対処後の三者連携
- 休職から復帰までのステップ
- 復職者の不安
第3章 セルフケア
部下のメンタルヘルスだけでなく管理職自身の心の健康を維持するためのセルフケアとして、ストレスやストレスに対するコーピング方法について学びます
- セルフケアとは
- 環境変化とは
- ハイパーチェンジ
- ストレス
- ストレスコーピング
- コーピング手法と性格傾向
- ハイパーチェンジへの対応
学習の進め方
インプットとアウトプットを繰り返して理解を深め、知識を定着させます。まず登場人物と対話しながらビジネスシーンでの課題解決を追体験し、理論や知識のインプットを行います。そしてミニクイズで学習内容を振り返りながら定着を促進。最後のスキルチェックテストでは学習到達度合いを測り、合格すると修了証が発行される仕組みです。

受講者の声
これまではメンタル不調は自分には無関係と感じていましたが、部下のケアだけではなく自分の健康を維持するためのセルフケアの重要性を知りました。講座でストレスへの具体的な対応方法について学んだので、自分自身への適切なケアとしても活用していきます。
職場で休職者が出る中で、職場復帰の対応が手探りの状態でした。研修で「復職者の不安」について具体的に学んだことで、部下の復職支援をスムーズに進めるためのイメージを付けられました。休職から復職までのプロセスを体系的に理解できたことで、関係者との適切なコミュニケーションが可能になったと感じます。企業の事例を題材にしていたので、自分の業務に置き換えて捉えることができました。
メンタル不調を正しく理解するだけでなく、個人のメンタルヘルスを保つためにどのように対策していくか、またどう組織づくりを行っていくかなど幅広く学ぶことができました。医学的な面からの理解を深めたことで、誤った認識を改められたと思います。なじみのない内容もありましたが、ストーリーを追って学ぶので取り組みやすかったです。自身のメンタルヘルスを維持するためにも、多くのメンバーに受講してほしい内容です。
学びの効果を高める科目の組み合わせ
メンタルヘルス+ミドルマネジメント実践
休職や復職のプロセスを適切に管理し、チームの負担を軽減する
部下がメンタル不調で休職した場合、復職までのサポートやチーム内の業務分担調整はミドルマネジャーの重要な役割となります。しかし対応を誤ると、復職後のパフォーマンスが低下したり、症状の再発を招く可能性があります。メンタルヘルスの「休職から復職までのステップ」を学ぶことで、復職者がスムーズに職場に戻るためのマネジメントに活用できます。
部下のメンタル不調を早期発見し、適切な対応を行う
ミドルマネジャーは、日常的に部下と接する立場にあるため、メンタル不調のサインに気づき、早期対応を行うことが重要です。しかし適切な知識がないと、部下の変化を見逃したり、逆に過度な干渉をしてしまうこともあります。メンタルヘルスの「ラインケア」(管理監督者による部下のメンタルヘルスケア)の知識を学ぶことで、部下の心の健康状態を把握し、適切にサポートするスキルの習得につながります。
ストレスマネジメントを活用し、職場の生産性と士気を向上させる
メンタル不調が増えると、職場の生産性が低下し、チームの士気(モチベーション)にも影響を及ぼします。ミドルマネジメントの「モチベーションマネジメント」(部下の動機づけを促進する手法)とメンタルヘルスの「ストレスコーピング」(ストレスへの効果的な対処法)の知識があると、部下一人ひとりのストレス要因を理解し、適切なサポートを行いながら、パフォーマンスの高い職場づくりに役立てられます。
メンタルヘルス+ハラスメント
ハラスメントを防ぎメンタルヘルス対策を行う
職場のハラスメント(パワハラ・セクハラ・マタハラなど)は、社員のストレスを増加させ、メンタル不調を引き起こす主要な原因のひとつです。ハラスメントの種類や具体的な事例などの知識を持つことで、適切な防止策や介入を講じることが期待でき、職場全体のメンタルヘルスの悪化を防ぐことにつながります。とくに管理職はハラスメントとメンタルヘルスをセットで学ぶことで、職場づくりに役立てられます。
管理職自身のメンタルヘルスを守る
ハラスメントを未然に防ぐために、管理職には「適切な指導」と「ハラスメントとの境界線」を理解するスキルが求められます。このような役割を担う管理職は、チームの目標達成や部下の育成責任などから、管理職自身が過度なプレッシャーを感じてメンタル不調に陥ることもあります。メンタルヘルスの「セルフケア」(ストレスの自己認識と適切な対処法)を学ぶことで、管理職自身の健康を守りながら、冷静で適切なマネジメントを行い、安全な職場づくりが可能になります。
社員へ適切なメンタルケアができるようになる
もしハラスメントが発生した場合、その被害者は強いストレスやメンタル不調に陥る可能性があります。メンタルヘルスの「ラインケア」(管理監督者による部下の心理的ケア)を学ぶことで、ハラスメントを受けた社員の心理的なサポートや適切な対処法を知ることができます。
メンタルヘルス+ダイバーシティマネジメント
多様性に配慮しながらメンタルヘルスのサポートをする
メンタルヘルスとダイバーシティマネジメントを同時に学ぶことで、多様なバックグラウンドを持つメンバーそれぞれの特性や状況に合わせたきめ細かなサポートが可能になります。例えば育児や介護などのライフステージに応じた柔軟な働き方を推進する際も、単なる制度設計だけでなく、心理的負担も考慮したアプローチが可能になります。このようなサポートは、多様な人材を活かすとともに、メンタル面での安定にも寄与します。
個人差を尊重した心理的配慮とチーム一体感の両立
個人の価値観やストレス耐性の違いを把握し、それらに心理的な配慮を行いながらも、チームの一体感を醸成するバランス感覚を養うことができます。メンタルヘルスの知識は個人への理解を促し、ダイバーシティマネジメントでは違いを強みに変える方法論を学びます。これらの知識を、各メンバーの心理的特性や強みを考慮しつつ、全員が共通の目的に向かって協働できる環境を整えることに役立てられます。
心理的安全性を基盤としたインクルージョンの実現
ダイバーシティマネジメントでは、無意識の偏見を排除して、心理的安全性の高いコミュニケーションの取り方を学びます。これにメンタルヘルスの知識をあわせもつことで、「自分と異なる他者」への理解と共感を促進しながら、感情面への配慮を可能にします。文化的背景や性格特性の違いによるコミュニケーションスタイルの差異を理解した上で、誰もが心理的に安全な環境で働く環境づくりにつなげられます。
ストーリー形式で学びやすいプログラム
お申し込み後すぐに
体験できます

導入企業の事例を用いながら
eMBAの効果的な活用方法を
提案します

科目の詳細や料金体系を
まとめてご覧いただけます
関連する他の科目
-
時代の変化に対応するためのショート科目
急速に変化する現代のビジネス環境において、
すべてのビジネスパーソンが新たに学ぶべき重要なテーマをピックアップしました。 -
ダイバーシティマネジメント
企業がダイバーシティマネジメントを推進する際の課題やその解決方法を、事例とともに学びます。
-
ハラスメント
ハラスメントを防ぎ、万が一起きてしまった場合の適切な判断基準を身につけるために、定義や事例を学びます。
-
メンタルヘルス
職場におけるメンタルヘルスの基礎から具体的な実践方法まで、知っておくべきメンタルヘルスの基本を学びます。
-
コンプライアンス
企業が持続的に成長し、社会から信頼を獲得するために必要なコンプライアンスの知識を学びます。
-
情報セキュリティ
すべてのビジネスパーソンに必須のセキュリティリテラシーを学び、「情報を守る力」を強化します。
