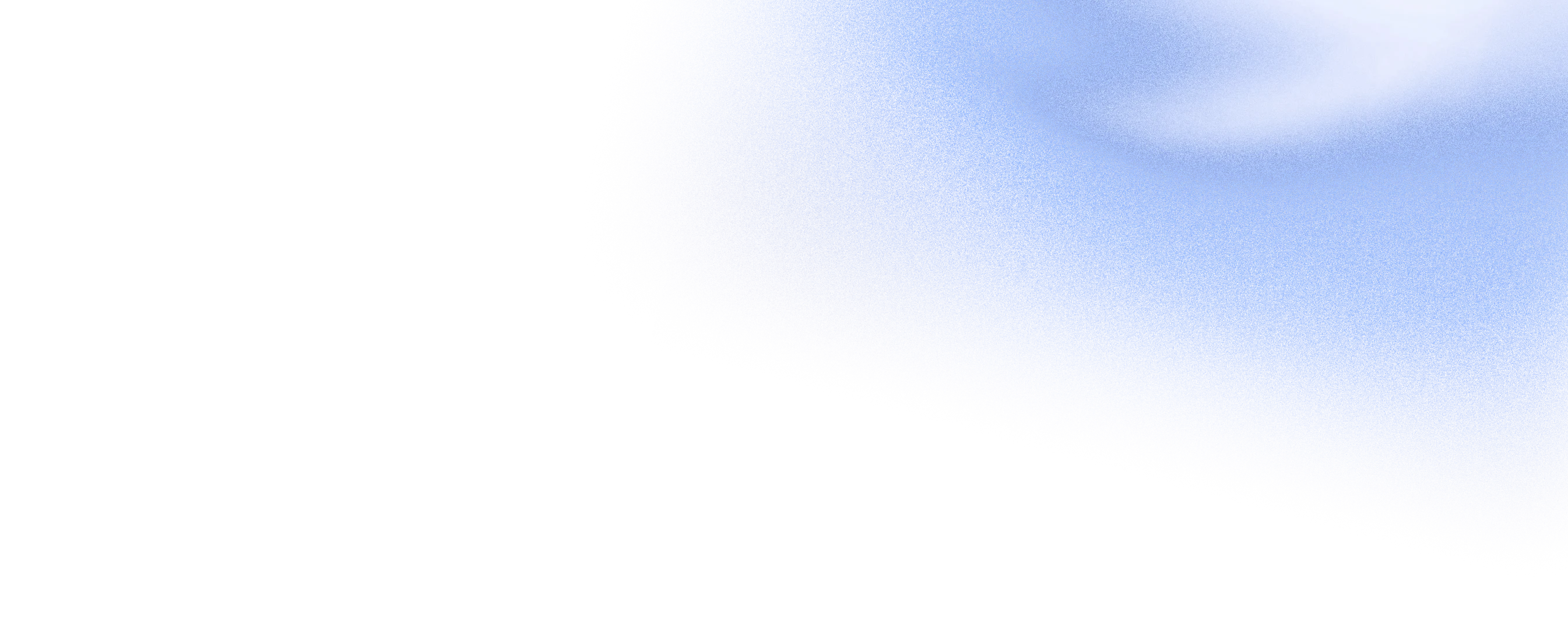

企業活動を「おカネ」の面から
読み取る力を身につける
「翌々月払いの予定が翌月払いに。自社として受けていいのか?」
このような問題に直面したとき、アカウンティングの知識があれば適切な判断基準を持つことができます。アカウンティングとは、企業活動における会計を意味します。
売上や利益といった「会社の数字」を理解することは、自社の現状を把握し、戦略を理解して実行するために必要な力です。会計の基礎知識を身につけることで、日々の業務における課題発見力や意思決定力を向上できるため、とくにリーダー層には必須の知識といえるでしょう。
本科目ではビジネスパーソンに必要な会計の基礎知識と、それをベースにした意思決定の方法を学びます。企業活動や事業におけるさまざまな課題を数字の面から分析し、解決への道筋を見出す力を養うことが目的です。簿記・会計学の細かなルールは扱わず、アカウンティングの全体像をつかむことに重点を置いた内容です。
※表ソフトの活用を想定した演習が含まれます。
科目の構成
学びのストーリー
大都市圏を中心に自然派のインテリアや服飾、雑貨を展開する「ウッドマーク社」。業務改革部で最近グループ企業になった「カグービス社」の財務分析を任されることになった「あなた」。業務改革部に異動した藤本早紀さんと、業務改革部発足時から所属する同期の長谷川学さんと一緒に、財務諸表を一から学習。先輩の教えも受けながら、予測財務諸表の作成にも取り組み、ビジネスに必要な会計の基礎を学びます。
-
財務諸表を見ると、売上と営業利益の伸びが連動していない。なぜ?
-
分かりづらいB/SやC/Fも見たほうが良い理由は?
-
新しく建てた店舗。予測P/Lと予測B/Sをどうやって計算する?

第1章 事業活動の測定
事業活動を測定するための財務諸表の位置づけと事業活動とのつながりを学びます。
- 損益計算書(P/L)
- 貸借対照表(B/S)
- キャッシュフロー
- ボックス図
第2章 利益の把握
財務諸表のうち、損益計算書についてです。利益の種類や財務諸表の着眼点、損益計算書作成時の原則を学びます。
- 営業利益、経常利益
- 当期純利益
- 収益性分析
- 発生主義/実現主義
- 費用収益対応の原則
第3章 資金繰りの把握
財務諸表のうち、貸借対照表とキャッシュフロー計算書について学びます。着眼点とそれぞれの意味合い、捉え方について理解を深めましょう。
- 資産、負債、純資産
- 安全性分析
- 効率性分析
- キャッシュフロー
- ワーキングキャピタル
第4章 現状分析
財務諸表から現状を理解するための指標分析について具体的に計算をしながら学びます。
- 総資産利益率(ROA)
- 自己資本利益率(ROE)
- 収益性
- 効率性
- 安全性
第5章 将来予測①
これまで見てきた財務諸表は過去のデータですが、将来を予測する考え方を学びます。特にコントロールしやすい費用面の予測を学びます。
- 損益分岐点
- 損益分岐点比率
- 直接費、間接費
- 変動費、
- 固定費
第6章 将来予測➁
5章で学んだ費用の将来予測などを活用し、予測財務諸表の作成手順を実際に計算をしながら学びます。
- 差額原価収益分析
- 関連原価
- 無関連原価
- サンクコスト (埋没原価)
学習の進め方
一般的なeラーニングとは異なり、ストーリー形式でインプットとアウトプットを繰り返すことで、深く学んでいく学習方法です。グロービスのケースメソッドを採用し、単なる理論のインプットではなく、実践的な学びを実現しています。
まずは実際のビジネスで起きうる課題解決を疑似体験し、理論や知識のインプットを行います。そして約100問の演習でアウトプットを行うことで、学んだ内容の定着を促します。科目ごとにスキルチェックテストを設けており、合格すると修了証が発行される仕組みです。受講者が科目ごとのゴールに向かって「学び切る」プログラムです。

受講者の声
非常にわかりやすい内容のプログラムでした。 他のアカウンティング講座と比較しても、満遍なく内容がカバーされていました。受講後は、社内会議で使われていた会計用語の意味が理解できるようになり、 自分自身で経営上の判断がある程度できるようになったと感じています。
技術職に就いていることもあり、実はP/LやB/Sという言葉を聞くのも初めてでした。ですがストーリーに沿って学んでいくうちに、財務諸表を分析する上で何がポイントになり、どういう点に注目すべきなのか、徐々に理解できるようになりました。自分が携わる事業の見方も大きく変わったと感じます。
アカウンティングは管理部門の仕事で、自分には関係ないと思っていましたが、受講後はイメージが大きく変わりました。自分たちの業務が財務諸表にどう影響するのか、経営指標である利益にどのように反映されていくのか、部下に対して自分の言葉でしっかりと説明できるようになりました。とくにリーダーには必須の知識だと思います。
学びの効果を高める科目の組み合わせ
アカウンティング+ファイナンス
経営の「過去・現在・未来」を財務データから読み解く
アカウンティングは「財務諸表を基に過去と現在の企業活動を分析」し、ファイナンスは「企業の将来価値を最大化するための意思決定」を行います。両者を組み合わせることで、過去のデータを活用しながら、事業や部門の成長戦略を立案できるようになります。
利益とキャッシュフローの両面から判断を行う
企業の成長には「利益の最大化」と「キャッシュフローの健全性」の両方が重要です。アカウンティングの視点では 営業利益やROA(総資産利益率) などが、ファイナンスの視点ではフリーキャッシュフローや資本コストなどが意思決定のポイントとなります。両方を学ぶことで、短期的な数字だけでなく中長期的な健全性も考慮した、バランスの取れた判断が可能になります。
アカウンティング+クリティカル・シンキング
財務データを論理的に分析し意思決定を行う
アカウンティングでは 財務諸表(P/L、 B/S、C/F) を読み解きます。そのデータの意味を正しく解釈し、適切な意思決定を行うにはクリティカル・シンキング(論理的思考力) が不可欠です。財務データの変化の背後には、経営戦略や市場動向が絡んでいることが多いため、数値の変動の根本原因を分析することで、適切なアクションを取る能力が高まります。
仮説思考を活用して、財務予測の精度を高める
アカウンティングでは予測財務諸表を作成しますが、その際にクリティカル・シンキングの「仮説と検証」 のアプローチが必要になります。例えば「来期の売上は伸びるか?」という問いに対し、「新規市場開拓が成功すれば、売上は〇%増加する」といった仮説を立て、それが確からしいかを検証していくことで、財務予測の精度を高めることができます。
アカウンティング+マーケティング
マーケティング施策の財務的インパクトを評価できる
マーケティングの目的は「顧客に買ってもらえる仕組みを作ること」です。その効果を正しく評価し持続的な成長につなげるには、利益やキャッシュフローへの影響などの財務的な視点が不可欠です。アカウンティングの視点を取り入れることで、マーケティング施策のROI(投資対効果) や損益分岐点を明確にし、経営に貢献するマーケティング戦略を立案できます。
財務指標と連動させた、経営陣を納得させるプレゼンができる
経営陣はマーケティング活動の結果を 財務指標(売上、利益率、ROA、ROE) と関連づけて評価します。アカウンティングの知識を身につけることで、マーケティング施策の効果を財務的なデータで説明することができます。これにより経営陣の理解と支持を得やすい、説得力のあるレポートやプレゼンが可能になります。
価格戦略をデータに基づいて最適化できる
マーケティングにおいては、製品の価格設定も重要な要素です。しかし最適な価格設定をするには、アカウンティングで学ぶコスト構造(変動費・固定費) や利益率の理解が不可欠です。両者の視点を併せ持つことで、市場の競争環境や顧客心理だけでなく、自社の財務状況も考慮した、利益を最大化する価格戦略につながります。
ストーリー形式で学びやすいプログラム
お申し込み後すぐに
体験できます

導入企業の事例を用いながら
eMBAの効果的な活用方法を
提案します

科目の詳細や料金体系を
まとめてご覧いただけます
関連する他の科目
-
グロービスMBA科目
グロービス経営大学院のMBAプログラムから9科目を厳選。
リーダーが身につけておくべきビジネスの理論やフレームワークを学びます。 -
クリティカル・シンキング
客観的な視点で物事を捉え、効果的なコミュニケーションを実現するための、一連の思考プロセスを学びます。
-
組織行動とリーダーシップ
社会学や心理学をベースに、戦略実現のためにどのように「人を動かす」かを考える力を身につけます。
-
人材マネジメント
戦略の実行を効果的に行うために、マネジメントの視点から組織構造や人事システムを活用する力を磨きます。
-
マーケティング
マーケティング戦略を体系的に理解し、お客様に継続的に購入していただける仕組みの構築方法を学びます。
-
経営戦略
経営戦略における基礎理論を理解し、成功確率の高い戦略策定に必要な思考プロセスを強化します。
-
アカウンティング
ビジネスの現場で必要とされる会計の基礎知識を学び、組織や事業の課題を数字の面から判断する力を身につけます。
-
ファイナンス
企業価値を高めるためのメカニズムやリスクについて学びます。定性的な経営分析による意思決定力の強化も行います。
-
ミドルマネジメント実践
経営の意図を現場に伝え、チームの生産性や士気を高めるための、リーダー層に必要なスキルとマインドを学びます。
-
ファシリテーション&ネゴシエーション
ファシリテーター・ネゴシエーターの基本的な役割や考え方、会議・交渉における具体的なスキルを学びます。
