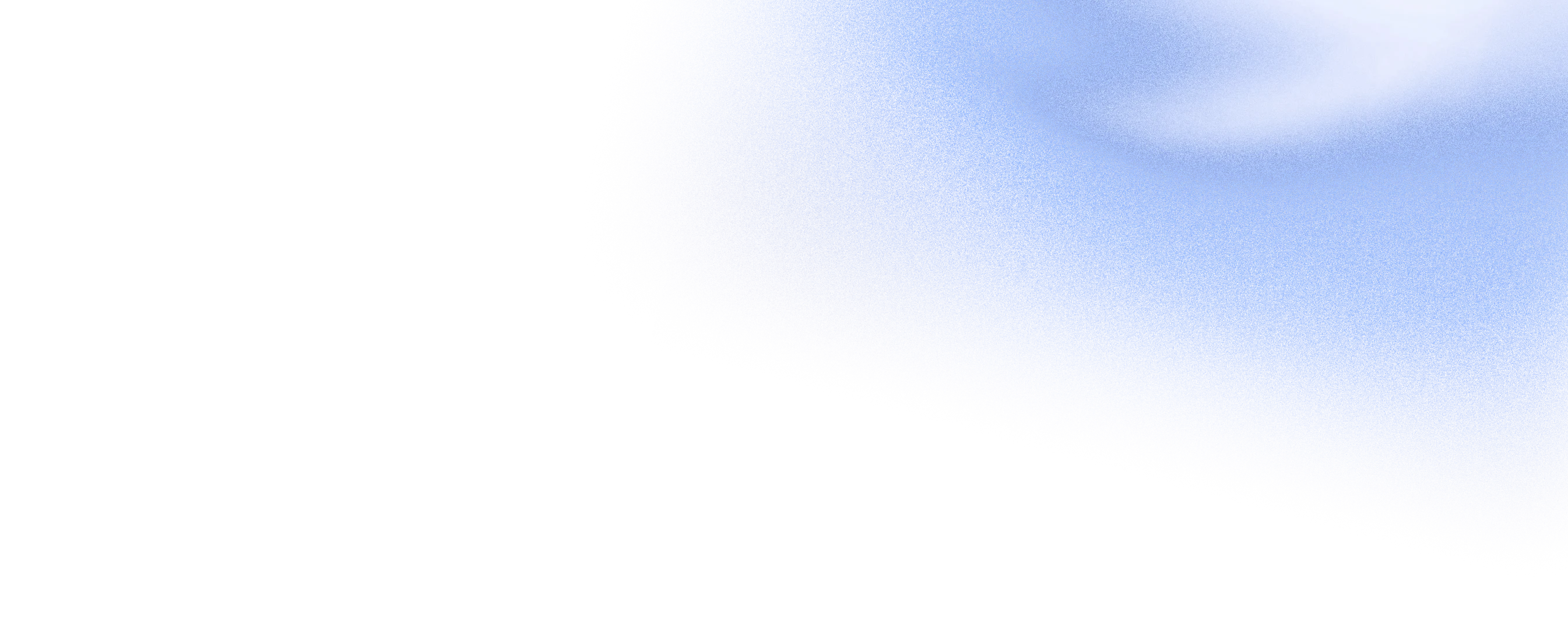

誰もが気持ちよく働ける職場を
実現するために
「ハラスメントの相談、正しく判断・対応できますか?」
近年、職場におけるハラスメント問題がメディアで取り上げられる機会が増えてきています。ハラスメントは、行為者本人の意識の有無に関わらず、相手に不快感を与えたり、尊厳を傷つけられたと感じさせる発言や行動を指します。意図せずとも誰もが加害者になる可能性があり、同時に被害者になるリスクも抱えています。
とくにリーダーの立場にある方々には、ハラスメントを正しく理解し、組織内で加害・被害の双方を予防する役割が期待されています。しかしリーダーが適切な判断基準を持っておらず、「相手がハラスメントだと言えば、すべてがハラスメントである」という誤解から、正しい指導ができなくなってしまっているケースも見られます。
当科目では、ハラスメントの定義や具体的な事例を通じて、正しい知識に基づいた判断基準を身につけます。これらによって、社員が互いを尊重し合い、気持ちよく働ける職場環境の実現を目指します。
科目の構成
学びのストーリー
日頃から付き合いのある商品開発部の星野さんから、パワハラに悩んでいることを相談された業務改革部マネージャーの「あなた」。マーケティング部マネージャーの藤本早紀さんとともに、さまざまな事例を通じてハラスメントに該当するかどうかの正しい判断基準や対応策、職場での防止策などについて学びます。
-
同僚が激しく叱責されている場面を目撃してしまった。これってパワハラ?
-
リモハラ/ケアハラ/ハラハラ/カスハラとは?
-
ハラスメントを受けたと思ったらどういう行動を取るとよいのか?

第1章 ハラスメント
ハラスメントの定義や種類、起こしてしまった時の周囲に与える影響について学びます。
- ハラスメントとは
- ハラスメントの種類
- ハラスメントを起こした時の周囲への影響
第2章 パワーハラスメント
パワーハラスメントの定義(3つの要素、6類型)や該当するかどうかの判断基準を学び、事例を通じて理解を深めます。
- パワハラの3つの要素
- パワハラの6類型
- パワハラの事例
- パワハラの判断基準
第3章 様々なハラスメント
セクハラから、近年話題のリモハラ・マタハラ/パタハラ・ケアハラ・ハラハラ・カスハラまで幅広く学び、ハラスメントに関する知識をアップデートします。
- セクハラとは
- セクハラについてのまとめ
- リモハラとは
- リモハラについてのまとめ
- マタハラ/パタハラとは
- マタハラ/パタハラについてのまとめ
- ケアハラとは
- ハラハラとは
- カスハラとは
第4章 ハラスメントの対応策
実際にハラスメントを受けた時どのように対応すればいいのか、日頃からどのように防止すればいいのかについて学びます。
- ハラスメントを受けた時の対応
- 職場での防止策
- ハラスメントについてのまとめ
学習の進め方
インプットとアウトプットを繰り返して理解を深め、知識を定着させます。まず登場人物と対話しながらビジネスシーンでの課題解決を疑似体験し、理論や知識のインプットを行います。そしてミニクイズで学習内容を振り返りながら定着を促進。最後のスキルチェックテストでは学習到達度合いを測り、合格すると修了証が発行される仕組みです。

受講者の声
パワハラの6類型と具体的な事例を学ぶことで、部下への指導方法を見直すきっかけとなりました。自分の立場や言動が持つ影響力をあらためて認識し、指示を出す際も「なぜそれが必要なのか」を丁寧に説明し、部下の意見にもしっかりと耳を傾けるようになりました。
ハラスメントの報告を受ける部署にいるので、学習のストーリーは、自分が直面する課題そのものでした。そのため「自社の場合はどう対応するか」と具体的な実践のイメージをつけやすかったです。正しい判断基準を身につければ、過度に怖がることなく、適切な指導を行うことにもつながると思います。
パワーハラスメントの定義を学んだことで、表面的な対応ではなく、周囲の状況を理解した本質的なコミュニケーションの実行につながりそうだと感じます。要所要所のミニクイズも、重要な点の振り返りに役立ちました。
学びの効果を高める科目の組み合わせ
ハラスメント+ミドルマネジメント実践
部下とのコミュニケーションを適切に行う
ミドルマネジャーは、部下のモチベーションを高め、育成する役割を担っています。しかしハラスメントの適切な判断基準を持っていないと、過度に恐れるあまり必要な指導ができず、育成に影響を及ぼすことがあります。ハラスメントの理解を深めることで、1on1や日々のコミュニケーションにおいて信頼関係を維持しながら、部下の成長を促す建設的なフィードバックが可能になります。
ハラスメント防止の最前線に立つ役割を担う
ミドルマネジャーは、上司と部下の間に立つ組織の橋渡し役であり、チームの職場環境を整える責任を負っています。パワハラだけでなく、セクハラ・リモハラ・マタハラ・カスハラなど、さまざまなハラスメントを理解することで、適切な指導とハラスメントの違いを理解し、組織全体でハラスメントを未然に防ぐ風土づくりに貢献できます。
ハラスメント問題が発生した際の対処をリードする
部下からハラスメントの相談を受けた際に適切に対応できなければ、問題が深刻化し、企業イメージの低下や法的なリスクを招くこともあります。ミドルマネジメントとハラスメント対策を併せて学ぶことで、問題が起きた際に公正かつ冷静な対応を行い、職場の健全性を維持するスキルを身につけることができます。
ハラスメント+人材マネジメント
ハラスメントのリスクを低減しながら、多様な人材が活躍できる環境を作る
多様なバックグラウンドを持つ人材(外国人、女性管理職、高齢者、障がい者、LGBTQ+ など)が増えると、組織内のコミュニケーションが複雑になり、意図せずにハラスメントが生じる可能性があります。例えば無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)や差別的な言動が、多様な人材のキャリア成長を阻害する要因になることがあります。ハラスメントと人材マネジメントの知識を組み合わせることで、多様な人材が公平に活躍できる環境の整備へつなげられます。
ハラスメントの相談窓口として機能する
ハラスメントが発生した際、人事部門が適切な対応を取らなければ、組織全体の信頼を失う ことになります。ハラスメント対応の知識を身につけることで、部下や社員からの相談に対して、公正かつ迅速に対応し、問題の拡大を防ぐことが可能になります。適切な対応は人事部門の信頼を高め、組織の健全性を保つことにも寄与します。
心理的安全性の高い職場を作り、組織のエンゲージメントを向上させる
ハラスメントが発生すると、職場の雰囲気が悪化し、社員のエンゲージメント(会社への愛着や貢献意欲)が低下します。ハラスメント防止策と人材マネジメントのフレームワークを組み合わせることで、社員が安心して働ける環境を整え、組織の生産性や定着率の向上に役立てられます。
ハラスメント+ダイバーシティマネジメント
多様な価値観や背景を尊重することで、ハラスメントのリスクを減らせる
組織では、異なる文化・価値観を持つ人々が協力しながら成果を出せる環境を整えることが求められます。しかし、その違いを理解しないままコミュニケーションを取ると、意図せずハラスメントに発展することがあります。一例として、ある地域では冗談として受け入れられる発言が、異なる文化圏では侮辱的と受け取られることもあります。多様性(ダイバーシティ)の視点を持つことで、ハラスメントを未然に防ぎ、より健全な職場環境を作ることに役立てられます。
無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)からのハラスメントを防ぐ
多くのハラスメントは、加害者が意識していない偏見や固定観念によって引き起こされます。例えば「若手だから意見は控えるべき」といった無自覚な思い込みが、結果的に職場における差別的な言動やハラスメントにつながることがあります。ダイバーシティマネジメントの知識を活用することで、自身や組織内の無意識の偏見に気づき、公平で尊重し合える職場づくりに寄与できます。
組織の持続的な成長と企業価値向上に寄与する
多様性を尊重し、ハラスメントのない職場を実現することは、単なるコンプライアンス対応ではなく、企業の成長戦略にも直結します。多様な人材が安心して能力を発揮できる環境は、従業員のエンゲージメント(職務満足度)を高め、結果として生産性やイノベーションの創出につながります。 ダイバーシティマネジメントとハラスメント対策を組み合わせることで、長期的な企業の競争力を高めることへつながります。
ストーリー形式で学びやすいプログラム
お申し込み後すぐに
体験できます

導入企業の事例を用いながら
eMBAの効果的な活用方法を
提案します

科目の詳細や料金体系を
まとめてご覧いただけます
関連する他の科目
-
時代の変化に対応するためのショート科目
急速に変化する現代のビジネス環境において、
すべてのビジネスパーソンが新たに学ぶべき重要なテーマをピックアップしました。 -
ダイバーシティマネジメント
企業がダイバーシティマネジメントを推進する際の課題やその解決方法を、事例とともに学びます。
-
ハラスメント
ハラスメントを防ぎ、万が一起きてしまった場合の適切な判断基準を身につけるために、定義や事例を学びます。
-
メンタルヘルス
職場におけるメンタルヘルスの基礎から具体的な実践方法まで、知っておくべきメンタルヘルスの基本を学びます。
-
コンプライアンス
企業が持続的に成長し、社会から信頼を獲得するために必要なコンプライアンスの知識を学びます。
-
情報セキュリティ
すべてのビジネスパーソンに必須のセキュリティリテラシーを学び、「情報を守る力」を強化します。
